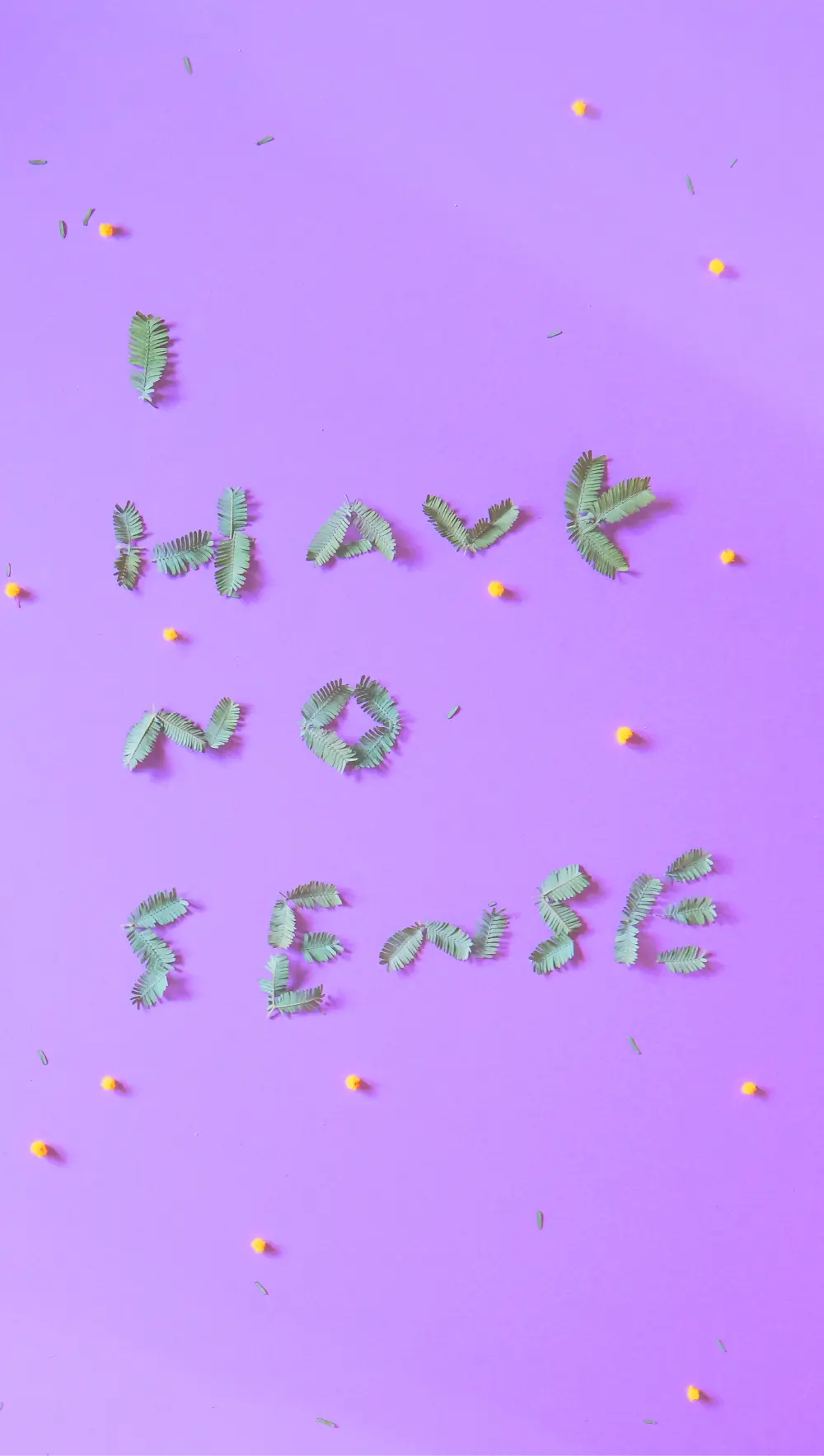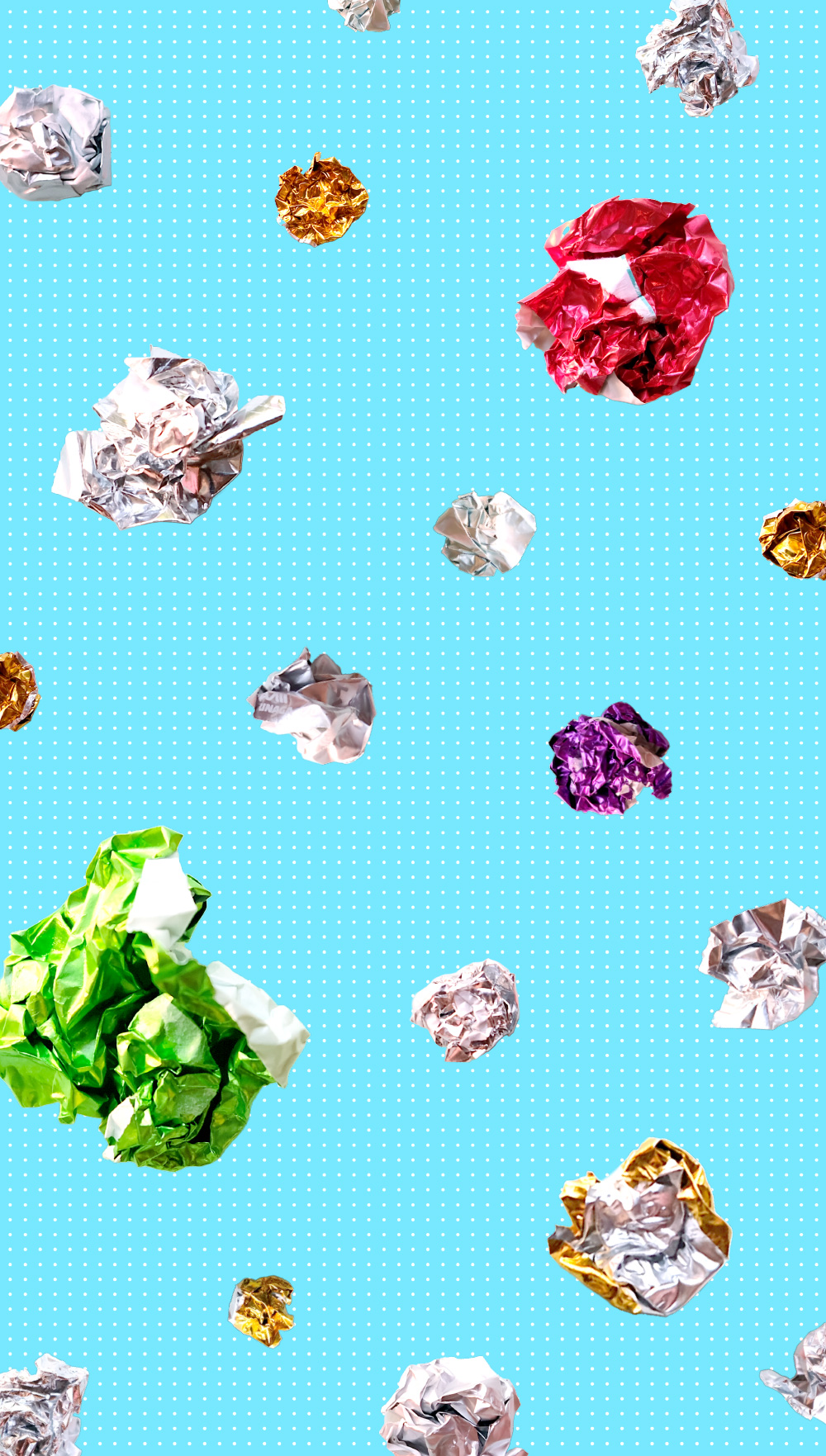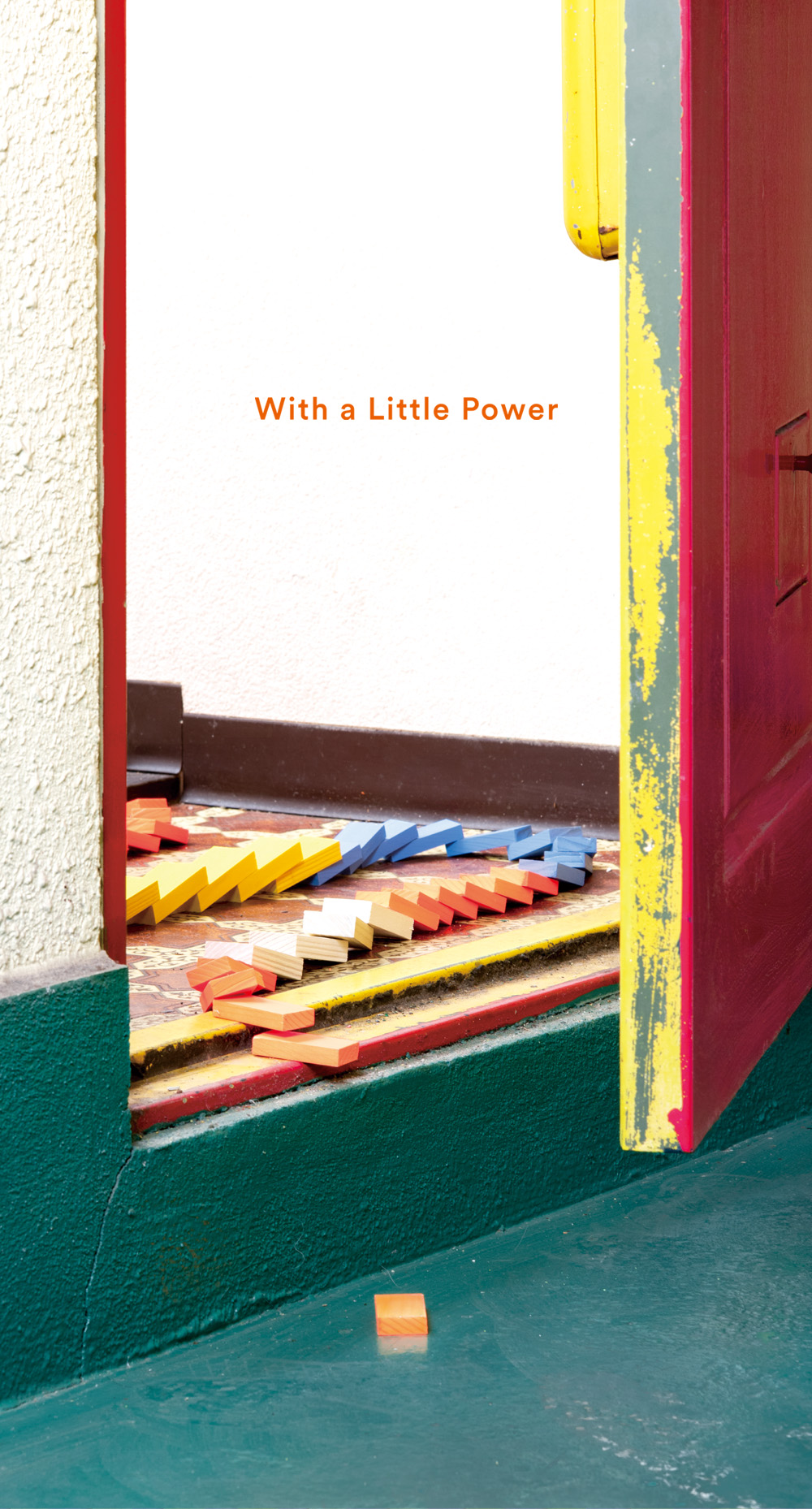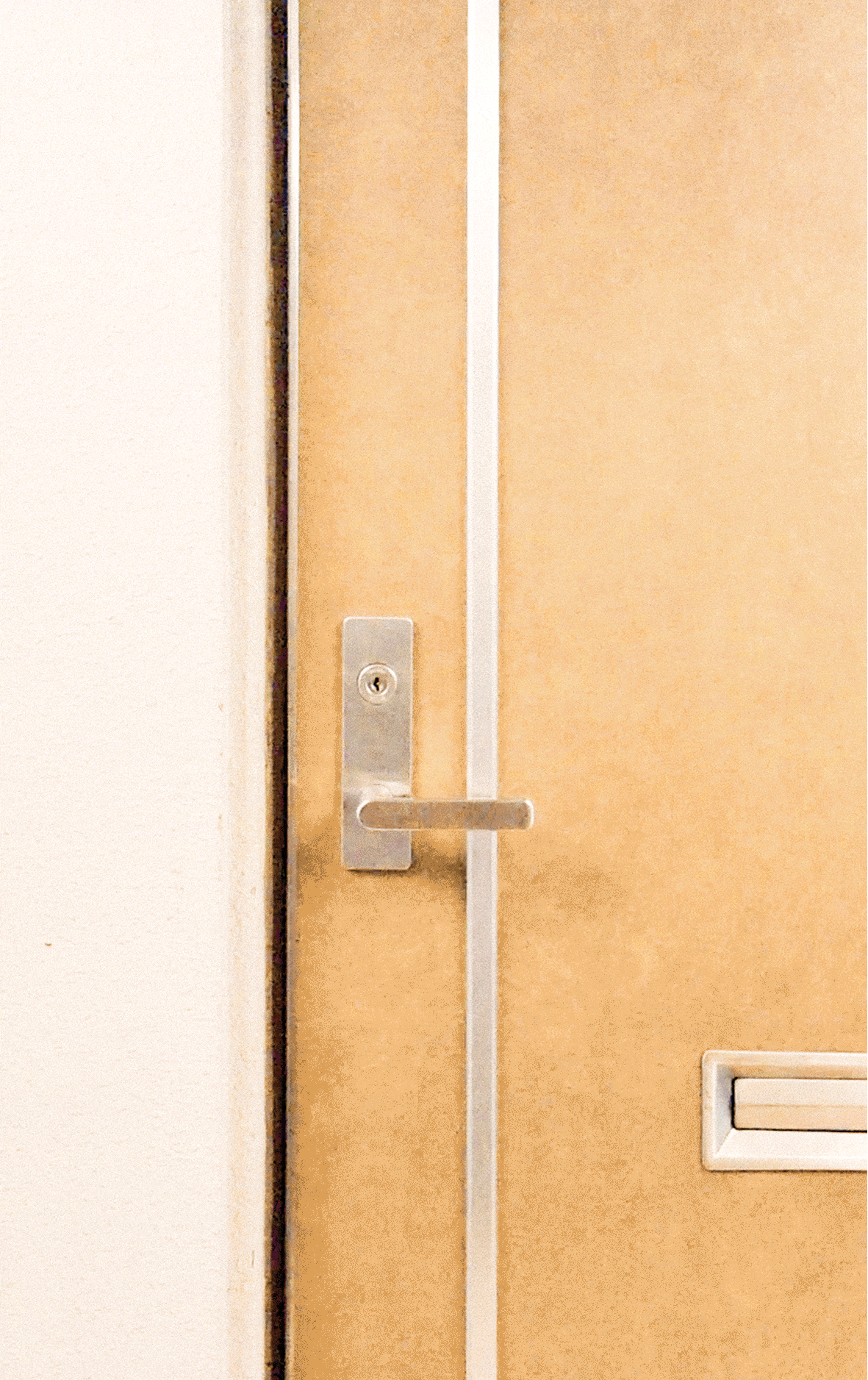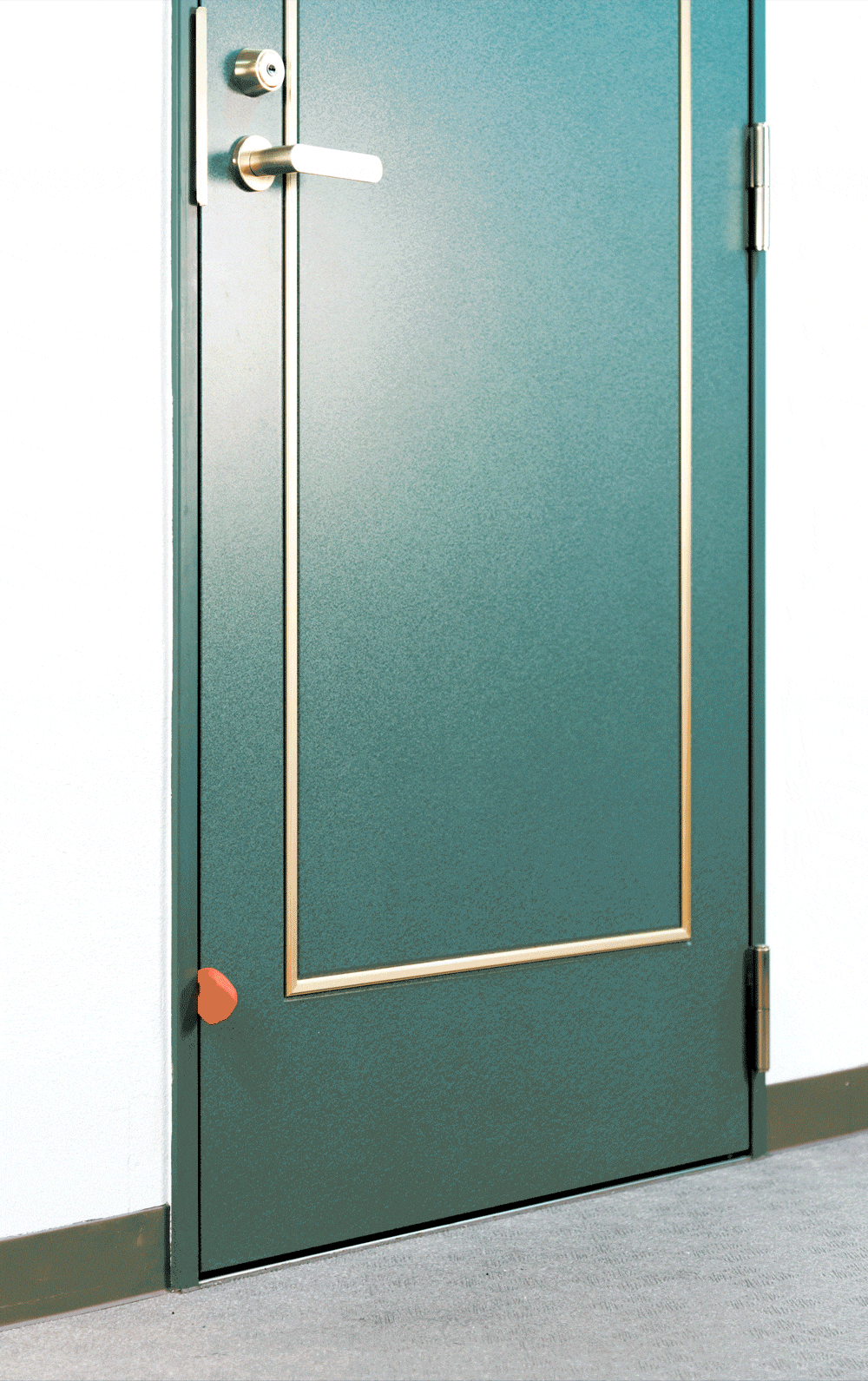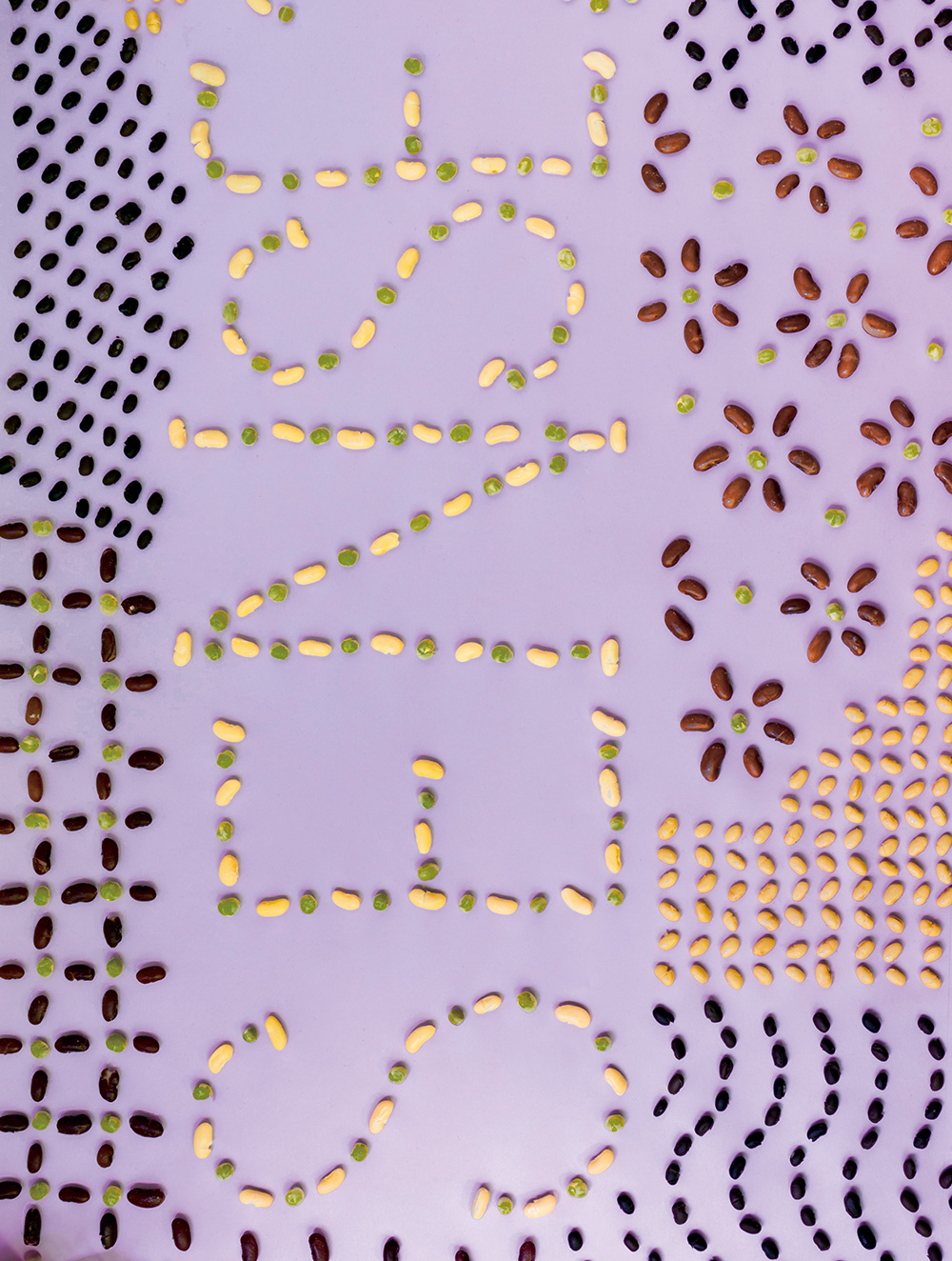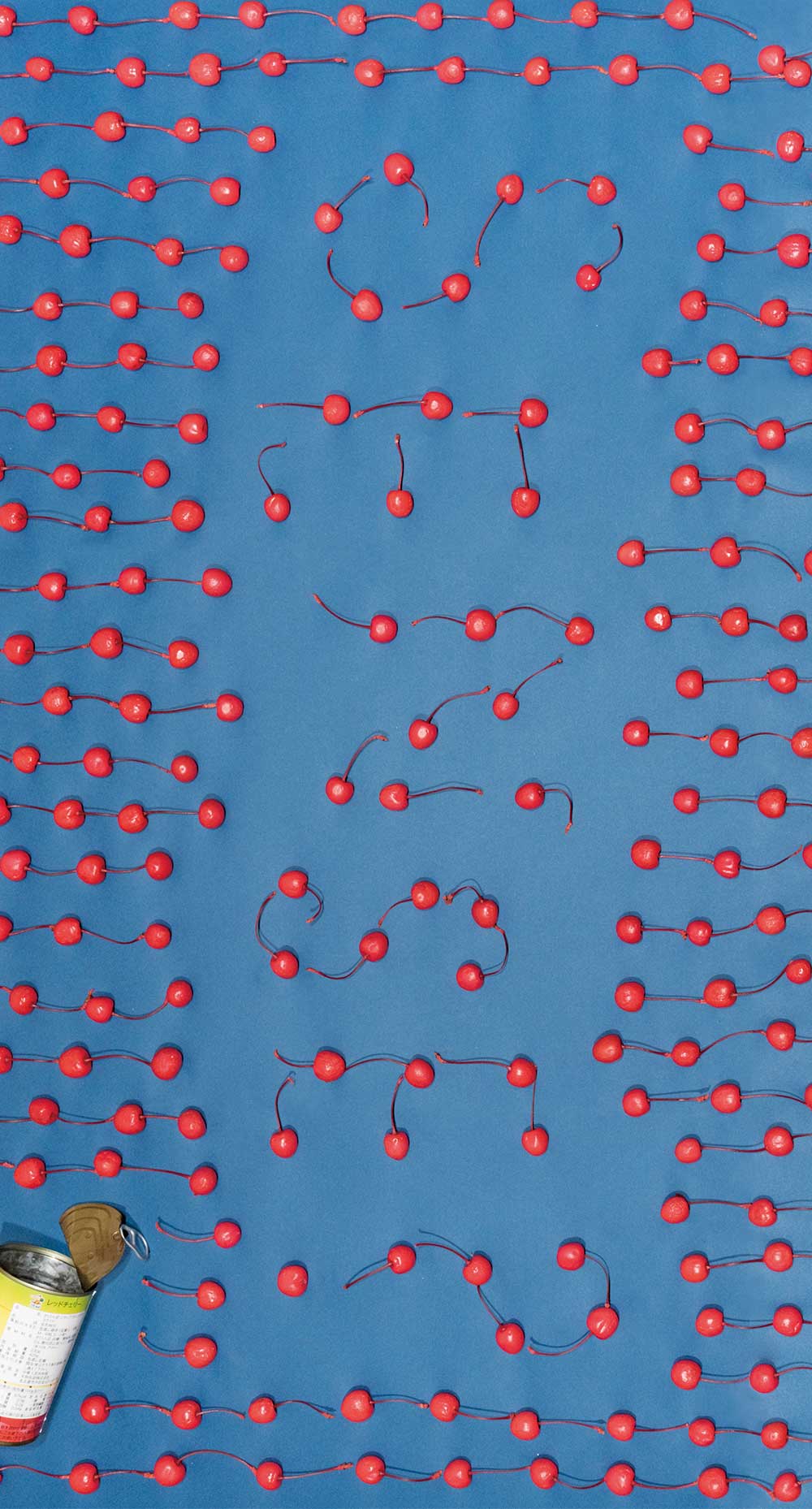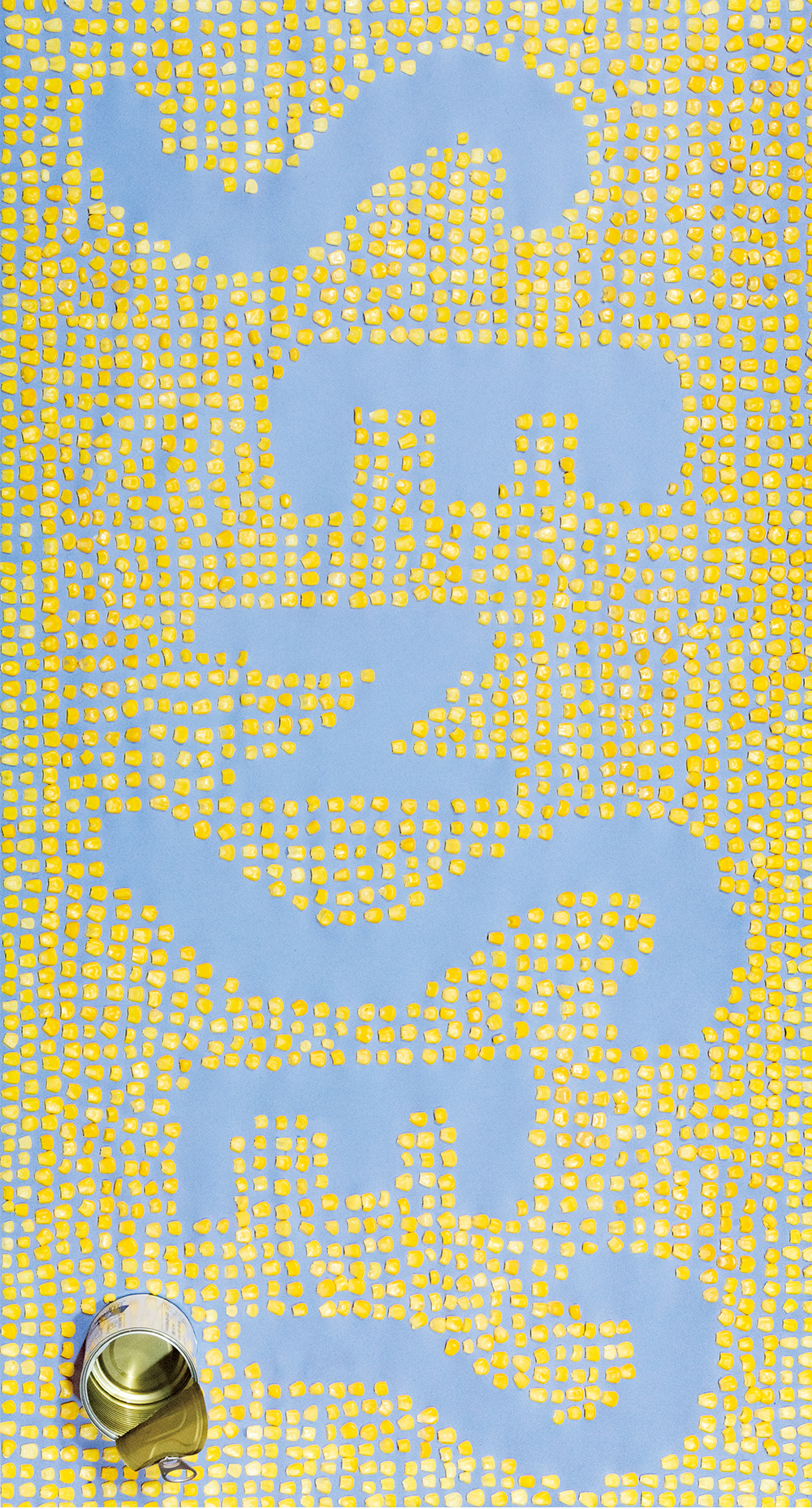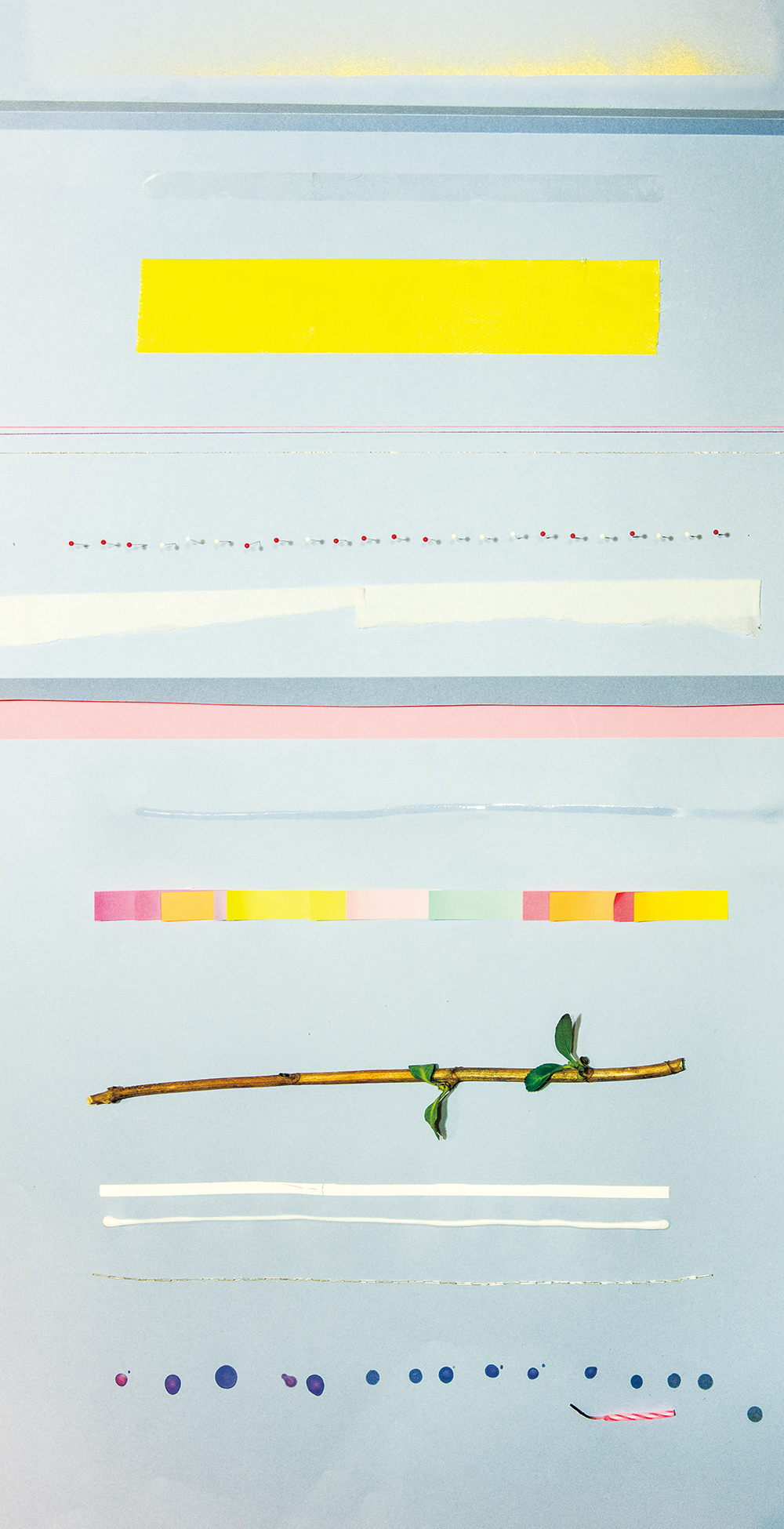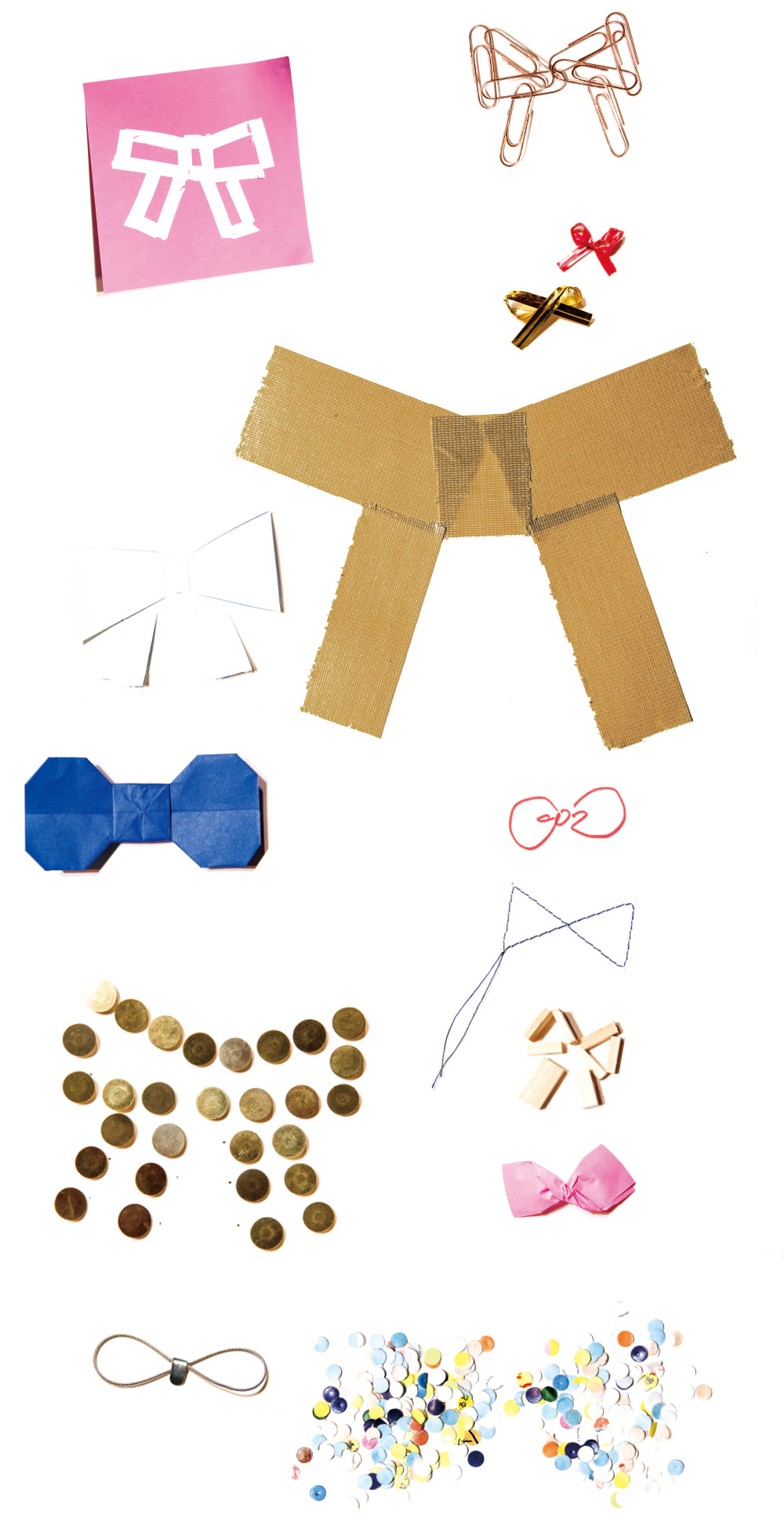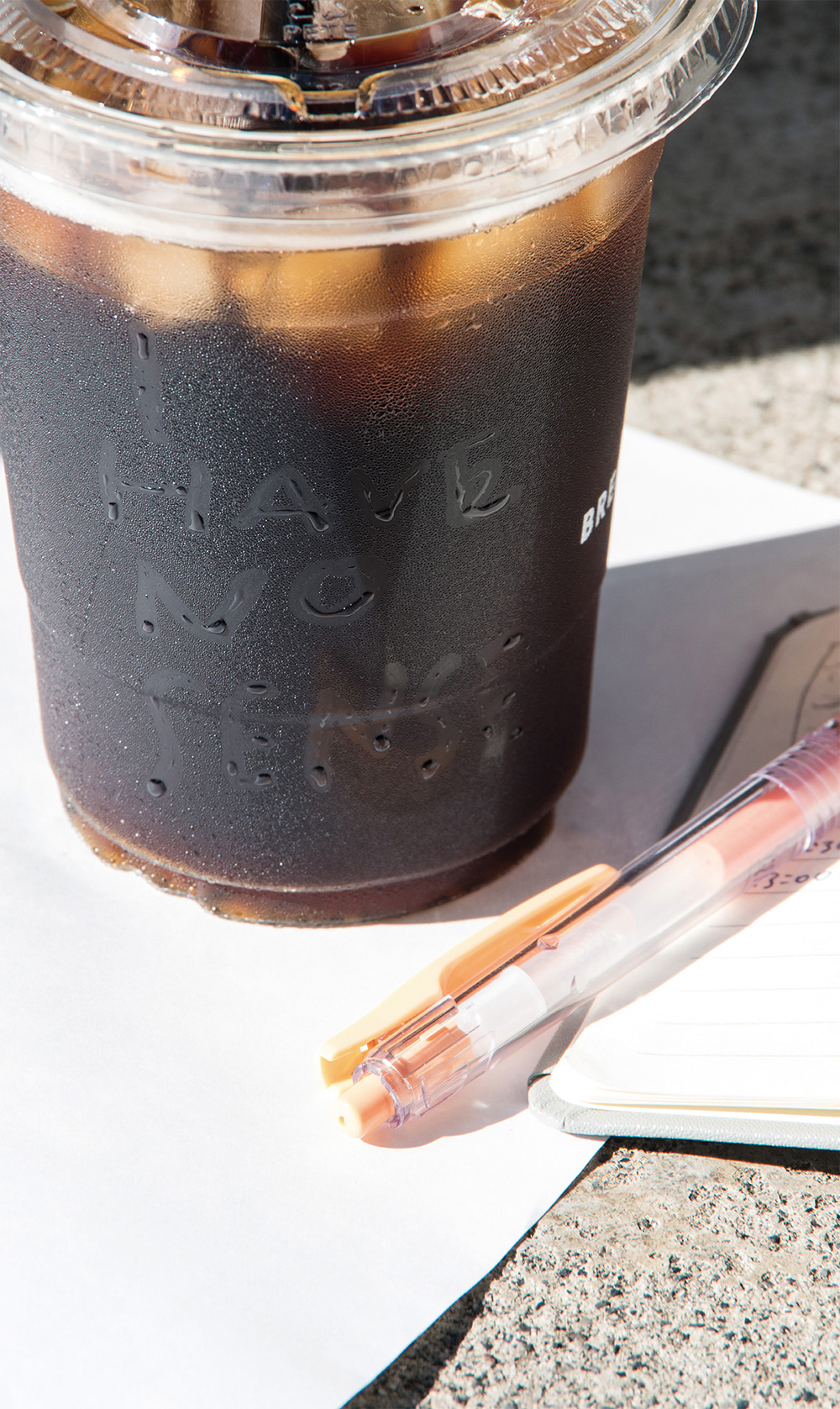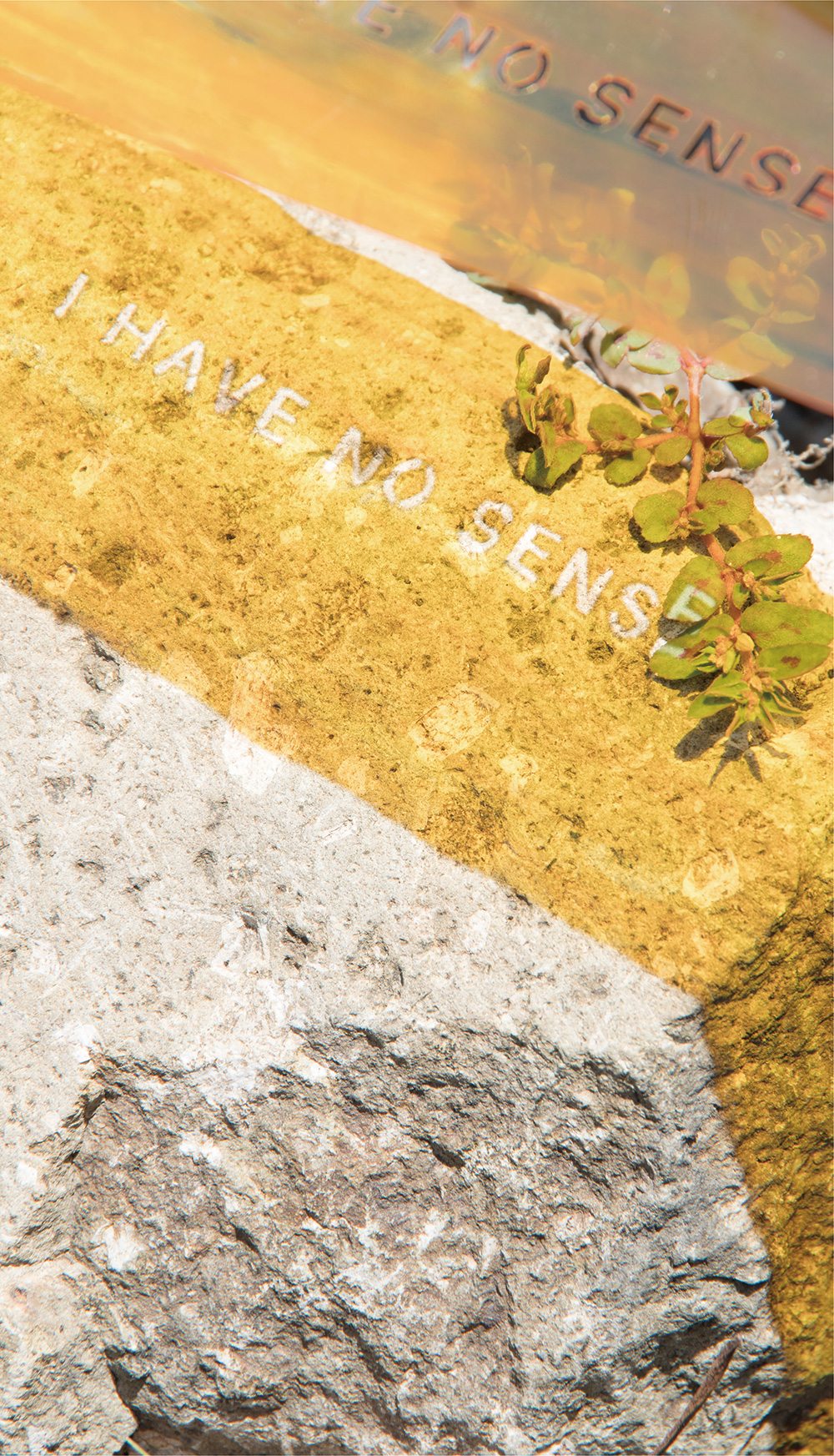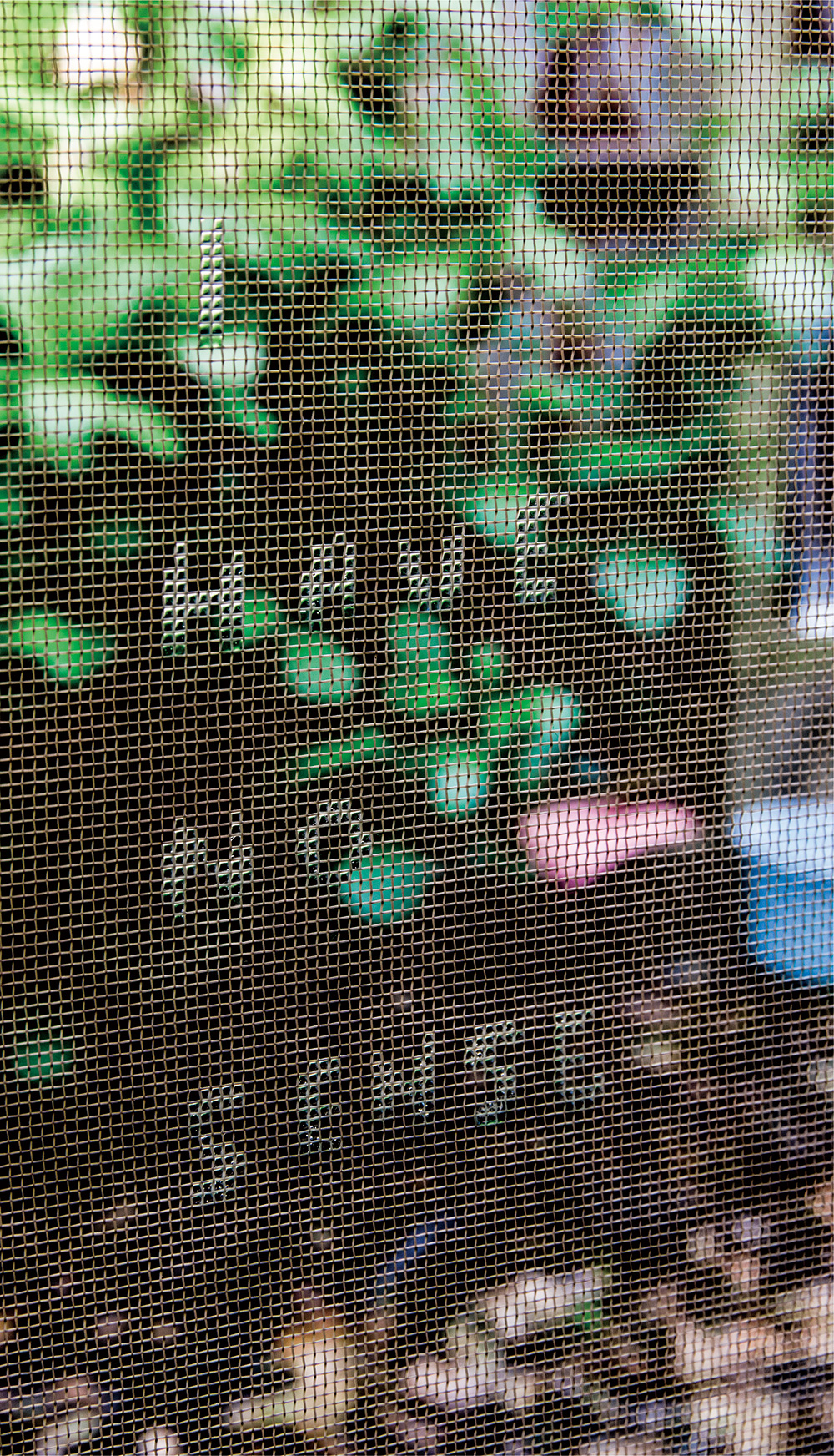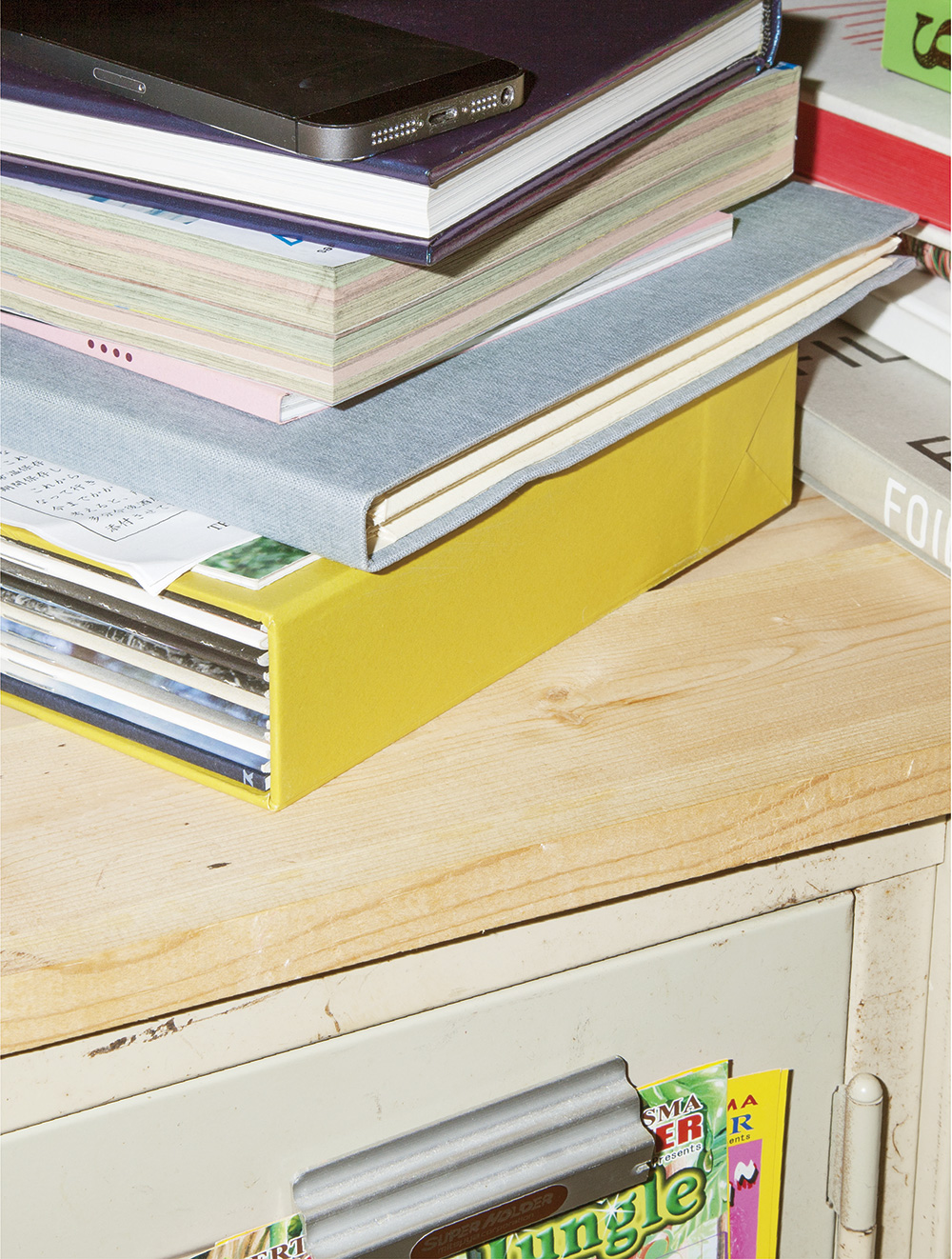VOL.31
“好き”のかけ算
私はデザインやアートより、生き物が好きです。
小学生の時は週末になると母と動物園に行き、高学年になると放課後は友達と近くの水族館へ自転車で行きました。中学生の時は職業体験で水族館を選び、好んで観るのは動物番組や自然系のドキュメンタリーばかり。おかげで今も芸能人や流行のドラマなどの話題にはあまりついていけません。高校生の時にはついに自分で生き物との共生を体感してみたいとニホンミツバチの養蜂に挑戦したこともあります。(結局は成功しませんでしたが)
そんな私はもちろん、高校卒業後の進路選択も動物学科や自然環境学科、畜産学科など動物や自然に関する学校を探していましたが、どれだけ調べても話を聞いてもピンときません。確かに生き物は大好きだし興味も尽きませんが、別に学者や農家になりたいわけではなかったのでそれだけを勉強する学科で果たして本当に良いか不安だったのです。
そんな中、「ランドスケープデザイナー」という仕事があることを知りました。自然を研究したり育てたりするだけでなく、人の生活の中にある自然をデザインできるということに驚き、早速ランドスケープデザインを学べる大学を調べたところ、京都芸術大学の環境デザイン学科を見つけました。芸大なんて1ミリも考えていなかったので、大学パンフレットを隅々まで読んだり、ランドスケープに関する雑誌をいくつか買ってみたりもしました。しかし私はランドスケープデザインという考えには惹かれるけれど建築物や街を設計したいとは思えず、代わりに実際に参加したオープンキャンパスで「空間デザイン」という言葉を知りました。
服から始まり、家具や家、街、そしてその中で暮らす人々のデザインまでなんでもできるという特徴が、全く将来の目標が決まっていない中で限られた専門知識だけを学ぶことに不安を感じていた私にはとても魅力的かつ変幻自在に見えました。そして、母が里山で藍染屋を営みながらまちづくりや地域活性化のような活動を行っていたのを見ていたので、私もデザインを学んで、自然やまちづくりに関わっていきたいと思い、空間デザインコースへ入学しました。
入学してから1年間は、デザインやアートに特別高い関心もなく、知識もおしゃれなセンスもなかったので、とりあえずできることを頑張りました。初めは面白いデザインができる人や知識がある人たちと自分を比べ劣等感を募らせることもありましたが、滋賀県日野町での産業の創出と地域づくりを行うことを目的とした「日野町プロジェクト」で空間デザインを通してまちづくりに関わったり、飛び抜けたアイデアでなくても丁寧に課題に取り組んだりして、他人ではなく自分と向き合うように心がけました。そうしているうちにあっという間に1年生が終わり、時間の使い方や課題のこなし方のコツがだいぶ掴めて心にも少し余裕が出てきました。しかし余裕が生まれたからこそ、もう1年が終わってしまったのに自分は何か成長しているのだろうかという焦りと、学んだことを活かして将来どうしていきたいのかという漠然とした不安が出てきました。
そんなものを抱えながら2年生に進級しましたが、履修する授業を探している際に、大学コンソーシアム京都という他大学の授業を受けて単位を取得できる制度を知りました。京都芸術大学での授業の合間に、コンソーシアム制度を利用して里山生態学を学びに京都産業大学へ毎週通い、自然環境に関する講義やフィールドワークに参加しました。また京都大学の農業栽培実習にも参加して、さまざまな大学の学生と3泊4日の合宿で学びました。
興味のあることをどちらも学んだことで、空間デザインコースで学んでいることが里山のデザインにも活かせると気付けました。今は京都芸術大学で学ぶ空間デザインに自分の“好き”をかけ合わせていくことで、将来への希望や自分らしいデザインの方法を見つけていけている気がします。
誰よりも自分の素直な気持ちに気づき、その気持ちに従って行動を起こす。難しいですが、とても大切なことです。学びを続けていく中で私の心が惹かれるものは案外身近なところにもたくさんあるので、それを地道に拾い集めて自分をわくわくさせてあげられる人になりたいです。
空間演出デザイン学科
空間デザインコース 2年生
荒井学園 新川高校出身
南部咲永