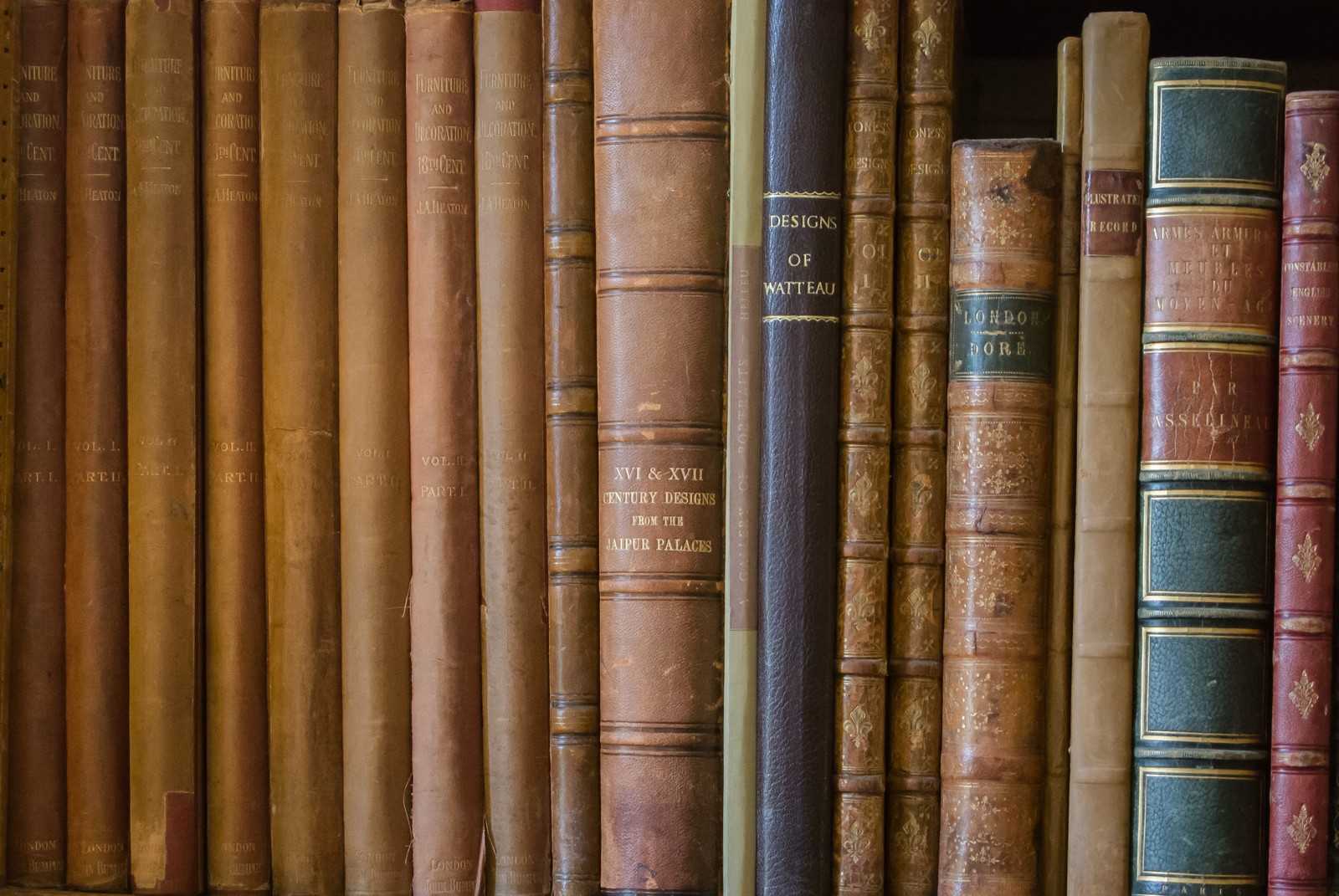
過去に中国や日本で詠まれ、そして現在までの長い時を読みつがれてきた全六首の漢詩作品を発送の源とし、新しく六篇の日本語現代詩を書き下ろしました。また、原作の漢詩の鑑賞を兼ねたエッセイ、および全体をまとめる「はじめに」「おわりに」を添えて卒業制作とました。
漢詩には、たとえば夜の宮殿や雪のお堂など、現在わたしが暮らしているのとは違う風景が詠まれています。その風景を自分自身の言葉で再構築することで、時代や地域の差異を超えて共通する人間の普遍的な感性の姿を捉えようとしました。あわせて、現実世界のわたしではない人物を主人公とした詩を制作することで、自身の表現力、発想力の向上を目指しました。
詩作品については、原作を下敷きとしつつも正確な翻訳ではなく自身の自由な発想を活かした「翻案詩」として制作しました。表現面では特に、改行の仕方や記号の使い方など詩の「見た目」についてもこだわって制作しました。エッセイについては、自身の経験に引き付けて書くことで、読者の方に漢詩への親近感を持っていただくことを意図しました。
芸術学科 - 文芸コース
田村 穂隆 【学科賞】
島根県
漢詩の鏡面 -漢詩翻案詩集-
【作品の抜粋】
夜の眼窩
旅夜書懐 杜甫
細草微風岸
危檣独夜舟
星垂平野闊
月湧大江流
名豈文章著
官応老病休
飄飄何所似
天地一沙鷗 (11)
ふとく ぬるい風が
岸辺の草や
わたしの頭髪にぶつかって
水の流れのようにほそくわかれ
草の隙間を 頭髪の隙間を あわあわと満たし
また ふとい風へと もどってゆく
旅を終えるための場所が
用意されているのかどうか
わからないまま
舟に はこばれている
見上げればどこまでも
背の高い、夜
満月が
眼のようだ
瞼のない
睫毛のない
瞳孔のない
たったひとつの
眼
あかるく おおきなその眼が
わたしにたずねる
(おまえはこれまで
何をしてきましたか)
(わたしはこれまで
ことばを書いてきました
ことばをつかって
はばたいて はばたいて
このおおきな世界を
両眼に収め
ことばをつかって
そのすべてを 書きおこし
すべてのことが わかった と、)
(……でもそれは 気のせいだった
いまとなっては
流木のようなこのからだ
砂のようにちいさな脳
ながされて はがされて
こんなにうすくなってしまっても
まだ いきているわたしは
これ以上どうやって
いのちをつかいきればよいのですか)
へんじはなかった
星々のひかりは
てのひらのように
空を覆っていた
月のひかりは
黒い川面へ溶け落ちて
ゆらめいていた
泣くときはいつも
なみだではなく
眼球そのものがあふれてしまいそうで
顔を手で覆うけれど
眼球はいまでも
この眼窩に溶けのこっていて
それは
あの月も いっしょなのだった
舟の前にゆらめくひかりを
一羽の水鳥が
つう と よこぎる
わたしは ちいさな眼をつかって
水鳥にたずねる
(おまえはこれまで
何をしてきましたか)
(わたしは――)
見上げればどこまでも
背の高い、夜
ふとく ぬるい 風
◆夜。仕事からの帰路、自転車で川の堤防を通る。川面は暗く、生き物の姿を視認することはできない。魚が跳ねるのか、ときどき、ごぽんっという粘度の高い水の音が聞こえてくる。朝にはたくさんの水鳥たちがこの川に集う。水鳥たちは、夜はどこにいるのだろう。わたしに見えないだけで、朝と同じように川面に揺られているのだろうか。
杜甫(七一二年〜七七〇年)は、中国の盛唐時代の詩人。「旅夜書懐」は杜甫の最晩年、舟にのり長江を渡りながら、人生の意味に思いを馳せる作。首聯(一、二行目)、頷聯(三、四行目)のおおきくひろびろとした夜の川の情景描写、対して尾聯(七、八行目)では自身の存在の小ささを鷗に託す。この大胆な対比構造によって、詩のなかの風景に呼び込まれるような感覚を覚えた。
暮らしのなかで見ている川の風景と、詩に描き留められた川の風景が、眼裏にまざりあう。その川べりに佇んでいたら、背の高い夜が、わたしにも人生の意味を問うてきた。それはもしかしたら、夜の貌を借りた杜甫が詩を通じて、月の眼を使って、わたしに問うてきたのかもしれなかった。
(11)石川忠久『漢詩の講義』大修館書店、二〇〇二年、一七〇頁


