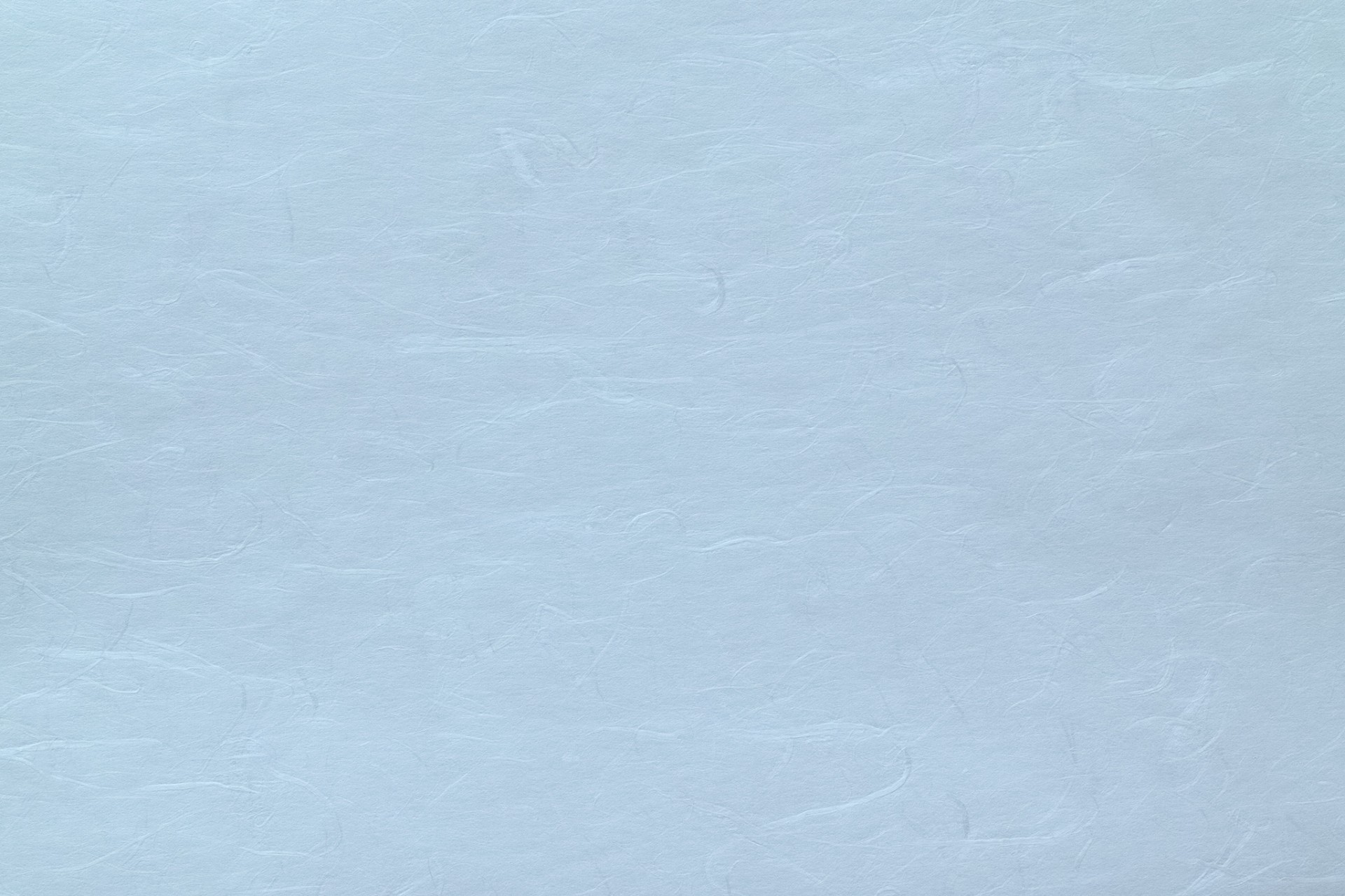
千葉県が発祥とされる万祝(マイワイ)は、漁師の晴れ着といわれる豪華な藍染の着物である。
江戸後期から昭和30年代まで、大漁や祝いの時に盛んに作られた。
しかし現在では、その存在を知る人はわずかになり、万祝を着る風習も途絶えてしまった。
千葉県の貴重な民俗文化である万祝の歴史や価値を、
何かの形で残しておかなければならないという思いがあり、
万祝を卒業研究のテーマに決めた次第である。
博物館の調査、万祝の染元への聞き取りなど、時間と労力は相当かかったが、
この研究をしていなければ出会えなかったであろう人々との交流は貴重な経験であった。
1年半にわたり、万祝のことばかり考え続けた日々であった。
芸術学科 - 和の伝統文化コース
仲西 とし子【卒展パネル展示論文】
万祝の染見本と見本帳
-紺屋が伝えた房総万祝の技-
千葉県

万祝(銚子市教育委員会所蔵)
≪要約≫
万祝(マイワイ)は、縁起の良い絵柄が描かれた藍染の着物で、大漁時に漁師や関係者に配られた。漁師のボーナスともいわれる豪華なもので、房総半島が発祥の地といわれている。発生年代は文化年間(一八〇四~一八一八年)頃と推定され、静岡県から青森県までの太平洋沿岸地域に広まった。江戸時代後期から昭和初期頃まで盛んに作られたが、昭和三十年代には万祝の製作や万祝を着る風習も途絶えてしまった。先行研究では、万祝のルーツや図柄、型紙などについて論じたものがある。しかし、房総万祝の特徴である吉祥柄を極彩色で染めた粋な着物に発展していった経緯についての分析は進んでいない。また、見本帳や染見本を詳細に検討する視点はほとんどなく、紺屋がその技や美を伝えるために果たした仕事について考察したものもない。
本研究では、国指定の重要有形民俗文化財「房総半島の漁撈用具」の万祝十点と、千葉県指定の有形民俗文化財「房総半島の万祝及び製作関連資料」の染見本三点と見本帳二点の調査を中心に、紺屋の仕事や足跡をたどる。また、県内各地に残された万祝や見本帳、調査報告書なども参考に紺屋と万祝について考察する。特に江戸時代後期の創業で平成十六年(二〇〇四)まで続いた丸京染物店の万祝と染見本を分析し、紺屋が房総 万祝の技をどのように伝えていったのかを論考していきたい。
第一章では、万祝の先行研究をまとめた。万祝の図柄が小袖の雛形本や木綿の筒描きの影響を受けているとしたもの、紺屋が型染めに使用した型紙を研究する意義を述べたもの、図柄の解析により万祝には漁師の世界観が表現されているとしたものなどがある。房総の紺屋については、分布と営業状況、紺屋同士のつながりを述べた安斎氏の論文(一九九八年)があるが、二十年以上が経過した現在では紺屋の数はさらに減ってしまった。万祝の技を受け継ぐ染元は、鴨川に二軒残るのみである。
第二章では、江戸との交流と房総の紺屋という視点から、万祝の発展した要因を考察した。地理的に江戸に近く、海の交通網も発達していたことから、物資や人の交流が多くあった事例を挙げた。房総の紺屋が江戸から万祝を染める藍を仕入れ、万祝の注文を受けていたことや、江戸の絵師が逗留し、万祝の絵柄を描いていた紺屋があったことも明らかになった。
第三章では、万祝、染見本、見本帳に分けてその調査結果を分析した。おもに製作した年代や紺屋がわかる資料を詳細に検討することにより、紺屋の果たした役割を考察した。「房総半島の漁撈用具」に指定された万祝についての報告書から、図柄の傾向や紺屋の分布を整理した。さらに他には類例のない、丸京染物本店の染見本を分析し、紺屋の技と工夫について明らかにした。染見本をもとに製作したと思われる新たな万祝の存在が明らかになったことは、大きな収穫である。
第四章では、房総万祝の技の伝承と題して、万祝の特徴と技法を整理し、初期の藍染技法と図柄や小袖との関連性について考察を加えた。最後に、丸京染物本店の足跡をたどり、紺屋の果たした仕事について考察した。
今回の調査により、万祝、染見本、見本帳を分析して得られた成果は、以下の三点である。
一、万祝はよろずの祝い、漁師の大漁祝だけに作られたのではない。農業の豊作や長寿の祝いなど、人々の生活に密着した祝い事のためにも作られた。「御誂模様御好次第」の題目に象徴されるように、紺屋は注文主の依頼に応じて、いろいろな図柄を染めていた。見本帳には、紺屋の歴史と技が残されている。
二、房総の初期万祝の図柄は、着物のルーツといわれる小袖の模様から影響を受けていると考えられる。見本帳に残る着物の形の枠線や多彩な図柄は小袖雛形本の影響であり、染見本に小袖屏風を模した図柄が存在していることなどがその論拠である。
三、丸京染物本店の足跡をたどり、紺屋が情熱と自負を持って万祝製作に励んでいたことが確認できた。高い技術と技を伝える工夫によって、房総万祝の文化的な価値が高められてきたことも想像できる。
万祝の需要がなくなり紺屋が激減した現在では、房総万祝という民俗文化がどのように受け継がれてきたのか、残された資料からたどることが年々難しくなっている。しかし、染見本や見本帳を丹念に調査研究することで、紺屋の技の伝承への努力や新たな万祝の価値を見出すことができるのではないだろうか。その一端を明らかにしたことが、本論文の成果である。

