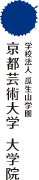大学では漆芸の実技を学んでいました。様々な道具を用いて漆器をつくる中、それらの道具をつくる職人さんが姿を消しつつあるという現状を知り、「実態をきちんと調べ、保存につなげられたら」と考えるようになりました。大学院に進み、実技から研究へ。調査を重ねるうち、漆塗りに使われる「漆刷毛」の職人である漆刷毛師が、全国に2軒しかないことが分かりました。各工房を訪ね、制作の現場を取材させていただき、現在に至るまでの足跡についてお話を伺いました。さらに、漆刷毛師のつくる刷毛が、漆芸作家や職人の手元に届いた後、どのように使われていくのか。自分の足で一つひとつ生きた情報を集め、修士論文としてまとめ上げました。
地域の人々が、
何を大切に生きてきたのか。
想いまで、伝わる展示を。
物の背景には、たくさんの物語が広がっていること。ひとつの道具と深く向き合えた2年間は、物の見方を豊かにしてくれました。担当教員を務めてくださった伊達仁美教授からは「保存」だけでなく「活用」という視点も学びました。もともと暮らしの中で使われてきた民俗文化財を、いかに身近なものとして感じてもらえるか。鍵屋資料館に勤める今も、地域の方々を訪ねてお話を聞き、記録し、お預かりした物をどのように生かすべきかと思考を巡らせています。地域の皆さんが何を想い、何を大切に生きてきたのか。資料を通して地域の魅力や人の暮らしにまで想像が広がっていくような展覧会をつくっていきたいです。

中野 祥子
歴史遺産研究領域 2011年度修了
漆芸のおかれている状況について調べるため、本学へ。漆塗りに使用する漆刷毛の研究を行う。修了後は、石川県輪島漆芸美術館で学芸員を務め、現在は市立枚方宿鍵屋資料館で民俗資料の展示に携わる。本学の伊達仁美教授とともに修復材料の研究も行い、民俗資料の保存促進に努める。
プロフィールはインタビュー時の経歴となります。
芸術文化研究領域 ARTS AND CULTURE STUDIES

「本物」と対峙し研究を通して
新たな「未来」をデザインする
この領域では、京都を中心に、様々な人々によって育まれてきた有形・無形の芸術文化の「今」を肌で感じ、各自の研究を通してその価値を捉え、芸術文化の持続的活用を考えていきます。単なる論文執筆に留まらず、実践的な授業・研究活動を通してコミュニケーション力や表現力を鍛えます。自身の専門性をもとに、時空を超えた芸術文化と人との関わりを、より多くの人々に魅力的に伝える力を育みます。