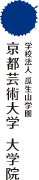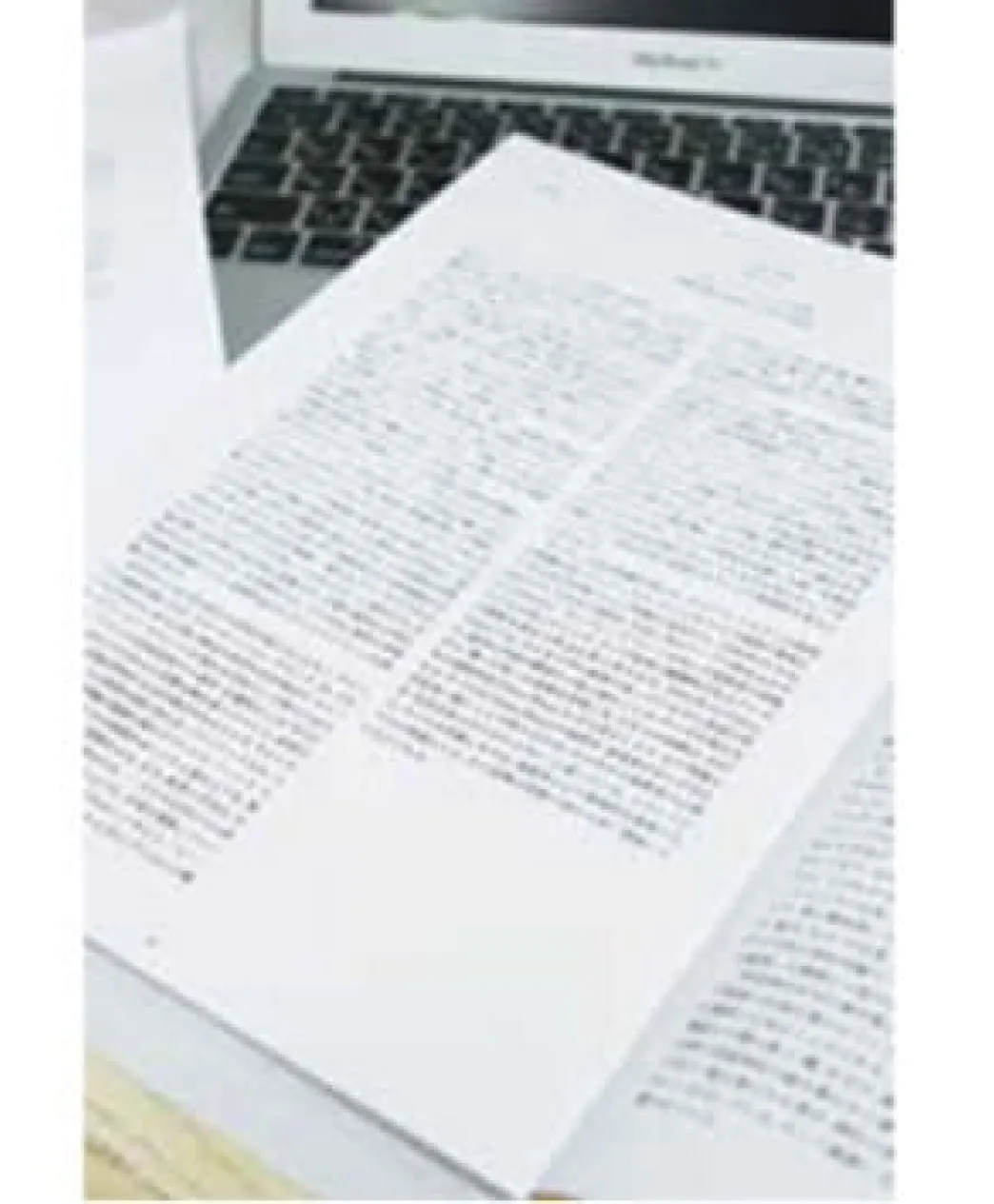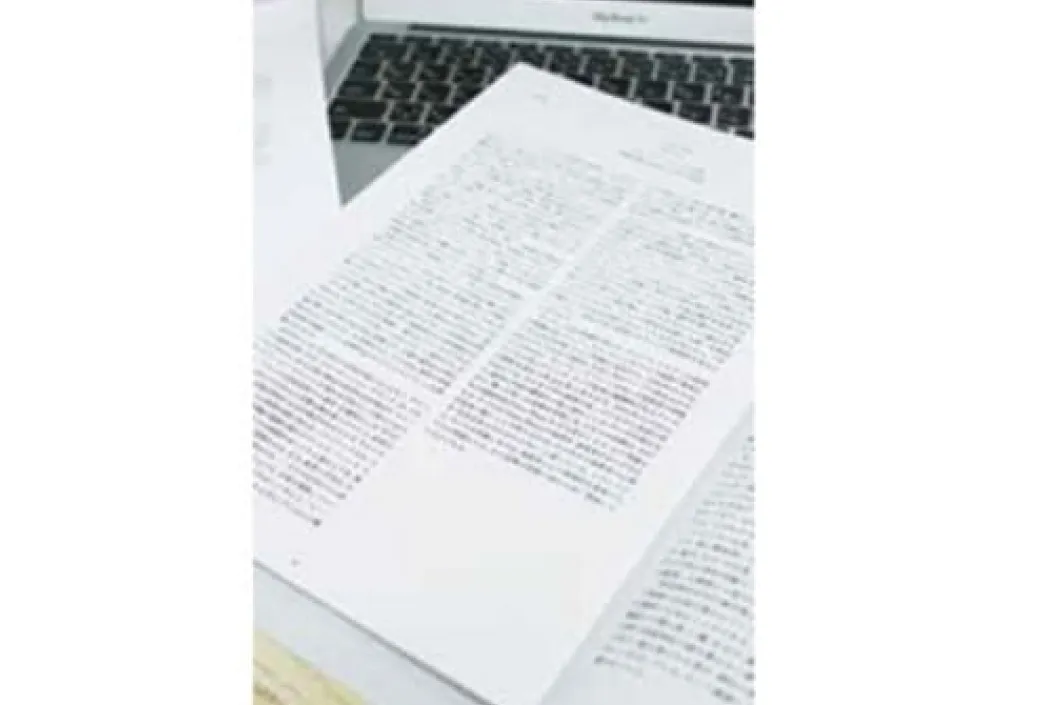学部2年生のとき、浅田彰先生の「音と芸術」という授業で、スティーヴ・ライヒの「木片のための音楽」という曲に出会いました。音も演奏風景もすごくシンプルなのに、強く惹きつけられるものを感じて、その年の進級論文の題材にすることを決意。しかし、はじめは文献を読んでもなかなか頭に入ってきませんでした。先生に相談すると、「まずは、自分がいちばん音楽を聴きなさい」というアドバイスをいただき、何度も曲を聴きこむうちに、自分でも驚くほど研究が楽しくなっていきました。「スティーヴ・ライヒの非ミニマリズム性」という卒業論文では、コース賞をいただくこともできました。スティーヴ・ライヒの音楽に出会えたことで自分の感受性が広がったような感覚があり、さらに研究を続けるために大学院へ進学。一人でじっくりと考える時間がふえたため、曲をさらに聴きこみ、発見をノートに書き留めていきました。ゼミを担当していただいた先生は、私の発見をもとに考えを深めてくださって、さらに新しい発見を導き出してくださいました。「芸術文化論特論」では、様々な領域で活躍するアーティストの作品や考え方にふれることができ、スティーヴ・ライヒが何を感じながら音をつくっていったのかを考えるうえで、大きな手がかりを与えてくれました。はじめは、ただの興味からはじまった研究が、自分の感性や考えが深まることで、さらに面白いものに感じられていく。そんな過程は感動の連続で、とても貴重な経験になりました。修了後は、ザ・シンフォニーホールに就職。スティーヴ・ライヒという作曲家に出会えたことで自分自身が豊かになれたように、素晴らしい作家や音楽との出会いを多くの人に広げていきたいと考えています。

三原 麻由
芸術文化領域 2011年度修了
文化デザイン・芸術教育領域
CULTURAL DESIGN
AND ART EDUCATION FIELD

創造する力が、
人と地域の可能性を育てる
私たちの領域では、芸術を「個人の表現」や「鑑賞の対象」にとどまるものとは考えていません。芸術は、人と人、人と地域が出会い、学び合い、共に成長していく過程の中で、育まれていくものだと捉えています。本学が創立以来大切にしてきた「芸術による人間形成」や「地域との協働による文化創造」という姿勢を継承しつつ、今日の複雑で多様な社会課題に応答する、実践的な教育と研究を展開しています。
本領域には、二つの分野があります。学生はそれぞれの関心に応じて、ワークショップの企画・運営や、フィールドワークに基づく調査研究、文化資源を活かしたプロダクトやプロジェクトのデザインに取り組みながら、創造的かつ協働的に問いを立て、実践を通して学びを深めていきます。
修了後は、デザイナーやクリエイティブ・ディレクターとして活躍するだけでなく、美術館や文化施設、学校教育、地域プロジェクトの現場など、多様な場で芸術の実践知を活かし、人や地域の可能性を育てる担い手となることを期待しています。