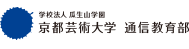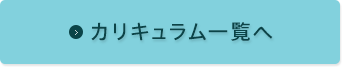| 授業概要 | まず古代の『万葉集』から近世の俳句にいたる歌や文学作品、あるいは能や狂言を採りあげて、日本芸能の流れを通史として概観します。そして各時代、各地域を象徴する作品の様式や技法といった基礎的な知識を修得します。つぎに個々の文学作品や芸能が生み出された背景を、当時の政治、経済、宗教といった様々な社会状況から多層的に考察します。 講義では約1000年の間に生み出されてきた多様な芸術作品を動画とテキストによって解説します。 | ||
|---|---|---|---|
| 授業目標 | 上代から近世に至る歌謡・和歌・音楽・俳諧、物語・日記・随筆・浮世草子、能・狂言について、各時代、各分野の流れを把握していただきます。各章の学習を通して、個々の韻文、散文、芸能それぞれの特質を把握することが、一つ目の目標です。 それと同時に、同時代の異なる分野間の相互関係にも気を配る共時的観点と、同分野の芸術が時代を超えてどのように繋がっているのかという通時的観点との両方から、日本における芸術の流れを総合的に修得することが、もう一つの目標です。 | ||
| 授業の流れ |
・1章 上代文学と歌謡-歌い舞い書かれる歌 ・2章 和歌の伝統-和歌・歌謡・連歌の流れ ・3章 雅楽-古代のみやび ・4章 仏教音楽・声明の世界-祈りの荘厳 ・5章 源氏物語の世界-世界に冠たる『源氏物語』の達成 ・6章 中古の物語-作り物語・歌物語・歴史物語の特質 ・7章 中古の日記と随筆-日記文学および随筆『枕草子』の文学的特色 ・8章 中世の説話-広がる文学的活動 ・9章 中世の物語・日記・随筆-文学的舞台と物語の受容 ・10章 歌謡と軍記物語-芸能の時代中世の幕開け ・11章 能の成立と発展-観阿弥・世阿弥の大成 ・12章 能の物語と演出-能の演技を成り立たせる諸要素 ・13章 狂言の笑い-庶民のたくましさを描く ・14章 井原西鶴-浮世の観察者の文芸 ・15章 松尾芭蕉-永遠の旅人の芸術 |
||