2013年7月26日
イベント
【ASP学科】今週末はオープンキャンパス!
今週末の27・28日はオープンキャンパスです! アートプロデュース(ASP)学科ってどんな学科?何を勉...
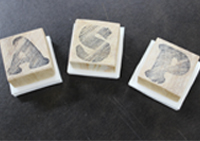

2013年7月26日
イベント
今週末の27・28日はオープンキャンパスです! アートプロデュース(ASP)学科ってどんな学科?何を勉...
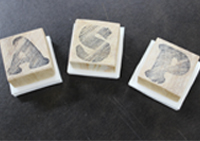
2013年7月24日
ニュース
卒業生の古川拓也さん(07年度卒業)がジャパン・アップデートに掲載されました! ➤「イギリスに暮らす」(...
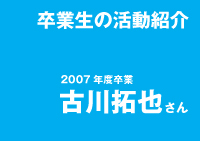
2013年7月22日
日常風景
日頃は”庭師”をされている山内朋樹先生...

2013年7月19日
日常風景
ACOP(芸術表現演習1)恒例の「仮装行列」が行われました! 昨年よりパワーアップしたイベントとなりました。 ...

2013年7月18日
日常風景
上写真の”...
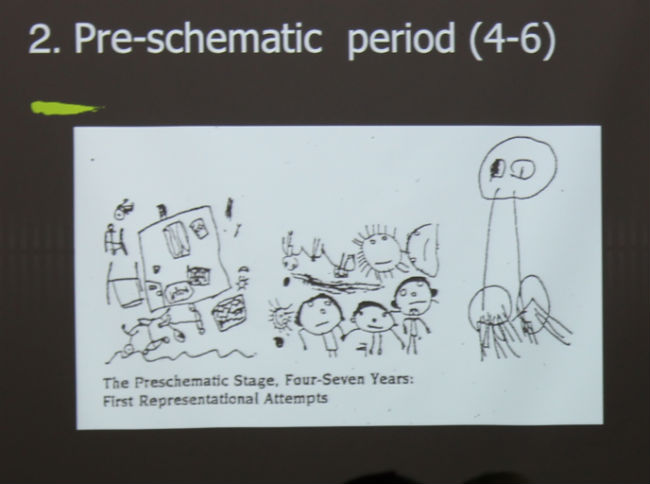
2013年7月16日
日常風景
7月12、13...
