2017年10月23日
日常風景
【ACOP】スラックライン体験!
昨年からACOPの授業で開催されている「スラックライン」が今年も行われました! 「スラックライン」とは、ライン状...


2017年10月23日
日常風景
昨年からACOPの授業で開催されている「スラックライン」が今年も行われました! 「スラックライン」とは、ライン状...

2017年10月20日
日常風景
10月18日(水)に『古美術を鑑賞するってどういうこと?』というテーマで特別講義を開催しました。ゲストでお越し...

2017年10月16日
日常風景
10月4日(水)に行われた特別講義は、ゲストに株式会社大と小とレフ取締役の鈴木一郎太さんをお招きし、『目の前に...
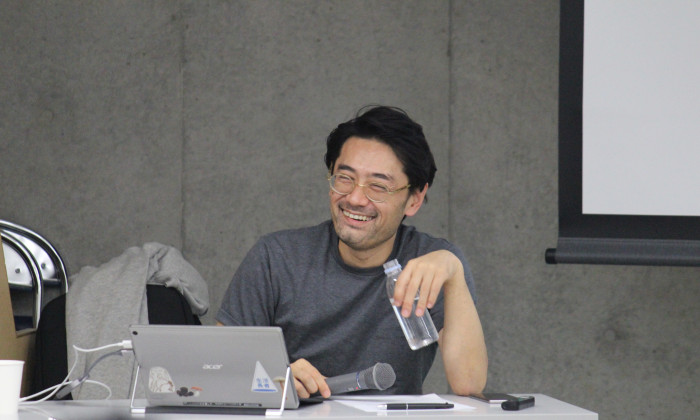
2017年10月6日
ニュース
昨日、本年度の蒼山会 創作・研究補助制度授与式が行われました。この制度は、本学学生の自主的な活動を支援するこ...

2017年10月2日
イベント
毎年たくさんの方々にご参加頂いている「ACOP鑑賞会」を今年度も開催します。 アートは「難しい、わからな...
