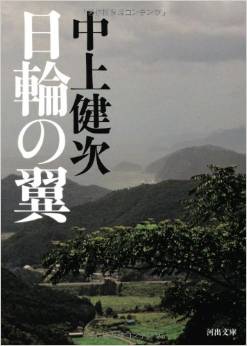- 2014年12月3日
- イベント
【中上健次シンポジウム】再び漂泊する路地のために―やなぎみわの『日輪の翼』トレーラー公演計画
大学院学術研究センター公開講座
「中上健次シンポジウム:再び漂泊する路地のために―やなぎみわの『日輪の翼』トレーラー公演計画」が、ギャルリ・オーブにて開催されました。
講師として、
やなぎみわ(京都造形芸術大学教授)、四方田犬彦(京都造形芸術大学大学院学術研究センター客員研究員)、渡部直己(早稲田大学文学学術院教授)、浅田彰(京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長)が参集し、
中上健次について、横浜トリエンナーレで披露されたやなぎみわ移動式舞台車について、多角的に語っていただきました。
(以下フライヤー掲載文)
今年のヨコハマトリエンナーレで、台湾製の移動式舞台車が、やなぎみわの作品として披露された。台湾では庶民に親しまれているネオンもけばけばしい貸し舞台車は、ある演劇を上演するために特別に意匠を凝らし、台湾で製造して日本に輸入されてきたものだ。
将来、このトレーラーで日本中を移動しながら中上健次の『日輪の翼』を上演しようというのである。
よく知られているように、中上健次(1946-1992)は、フォークナーがアメリカ南部に設定したヨクナパトーファのような神話的な場所として、故郷である新宮の被差別部落の「路地」を根拠地とし、『枯木灘』(1977)や『千年の愉楽』(1982)のような傑作群を生み出した。しかし、その「路地」が地上げされ、良かれ悪しかれ普通の場所になってしまったとすれば、一体どうすればいいのか。
そこで書かれた『日輪の翼』(1984)では、「路地」の若者らが老婆らを冷凍トレーラーに載せて日本各地の聖地巡りの旅に出る―いまやいたるところに「路地」があるとでも言うかのように。だが、むろんそれは幻想であり、続編『賛歌』(1990)では東京にたどりついた若者らが新宿で「性のサイボーグ」つまりはホストとして働き始めることになるだろう。それに伴い、中上健次はかつての神話的な輝きを自らかなぐり捨て、確信犯的にマンガ的な表層の世界へと傾斜していったかのようだ―1992年の早すぎた死にいたるまで。
横浜でのお披露目では、中上健次の想像した花である夏芙蓉が描かれた舞台がそれ自体巨大な花のように開花し、ポール・ダンサーが達者な芸を披露して見せた。
こうしてひとまず幕をあけたやなぎみわの壮大な計画が、今後どう展開されてゆくのか。
次のステップである来年の「PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015」を控え、やなぎみわに集英社版中上健次全集の編集委員から四方田犬彦・渡部直己・浅田彰の3名を加えて、物語の漂泊、演劇の交通をいまどう読むか、そのヴィジョンをどう舞台化すべきか、多面的に検討する。
やなぎ先生の移動舞台車の制作過程の動画をまずは拝見。
台北、京都、山形、台中、横浜とロードムービー的に続いていきます。
(コチラでも見れます→)https://www.youtube.com/watch?v=ULTZK2j-jdc
『ステージトレーラープロジェクト 京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 國立台北芸術大学 共同企画』
中上健次の示す「路地」とは何だったのか。
現代ではあまり感じられにくくなった感覚だからこそ、今こそ検証されるべきであり、
やなぎ先生はそれをあえて演劇という手法で取り組まれています。
来春は、中上健次朗読ナイトを舞台トレーラーで開催することが予定されているようです。
話は尽きることはありませんでしたが、この壮大なステージトレーラープロジェクトの旅はまだまだ続きます。
※以下、移動舞台車雙六(ポスター)に掲載されている宮島達男先生(本学副学長)のテキストを紹介いたします。
------------------------------
震災後東北の「賛歌」として呼び覚まされる《あの感覚》
宮島達男(現代美術家)
中上健次『日輪の翼』は「路地」と呼ばれる地から押し出された七人の老婆(オバ)と四人の若者が、改造冷凍トレーラーに乗って伊勢、諏訪、出羽、恐山、皇居へとあてどもない巡礼の旅を繰り広げるロードムービー的小説。それを演劇に仕立てるやなぎは、劇中、重要なトポスになっているトレーラーを、移動する舞台として使うというアイデアを考えた。さらに、トレーラーを台湾で親しまれている派手なデコレーション・トラック(デコトラ)と読み替え、制作を台北と京都、そして震災後の東北の学生に託した。この選択は決して偶然ではない。
そもそも『日輪の翼』におけるトレーラーは「移動式路地」とも言え、被差別部落出身のオバや若者たちが存在を許される唯一の場所であり、日本中どこにでも降り立つことのできる特別な装置だ。だから、演劇舞台も「路地」のまま、移動しなければならなかったし、「路地」特有の《あの感覚》が充満しているものでなければならなかったはずである。
ところで、そのオバや若者が訪れる出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山)は、東北、山形県に位置する山岳信仰のメッカ。また、森敦が越冬し、小説『月山』を著した注連寺があり、鉄門海上人の「ミイラ」がいまだ残るような場所。そして、市内には、今回デコトラを描くことになった学生達が在籍する東北芸術工科大学もある。私自身、この地に通って八年経つが、地の持つ性質(さが)とも言える生と死が交配するような濃密な《あの感覚》を感じてきた。それは圧倒的な「山」の存在。縄文の血。過酷な自然。そこにしがみつく人間。貧しさと摂取(仏、特に阿弥陀仏が慈悲の力によって衆生を受け入れて救うこと)の歴史。姥捨、娘売り、出稼ぎ。限界集落。繰り返し襲ってくる災害。人は祈るしかなかった。残るミイラの数はその想いの数かもしれない。そして、すべてを忘れるかのように爆発する夏祭り。それらが渾然一体になって成形される「生と死」のトポス。それは、かつて、パリから帰国した岡本太郎が、日本の原初エネルギーをここ東北と沖縄に再発見した《あの感覚》を指すのだろう。あるいは、中上が社会に抗い続け、伝えようとしていた世界の複雑性の《あの感覚》と言ってもいいかもしれない。
いずれにしても、東北は、やなぎが今回見ようとしている世界とどこか繋がっている。だから、彼女はデコトラ制作そのものを演劇化/祝祭化すべく、東北の学生を加えたのだし、それは、若者を引き受けることであり、《あの感覚》に満ちた東北というトポスそのものを抱えることでもあったはずだ。そして台北で、まるで小説さながらの合宿をし、デコトラ制作という祝祭を挙行したのだ。そうした意味で、やなぎの演劇はすでに始まっていたのかもしれない。
それにしても、なぜ、やなぎは中上の《あの感覚》へと向かわねばならなかったのか?
そして、彼女はなぜ得意とする写真ではなく、演劇という形式でそれをしなければならなかったのか?
あえて説明を試みれば、《あの感覚》とは、血と死と肉と生と性の過剰なる物語であり、中心が融解し、あらゆるものが関係し合う構造を持ち、意味が宙吊りにされ、圧倒的に存在が否定され肯定されるような、計算式が役に立たず偶有性が時間と空間を支配するような、しかも、エネルギーに満ち溢れ、躍動し、底なしの危機感と莫大な希望の、そんな感覚。
逆説的に言えば、現状のセカイが《あの感覚》を追いやり、認めなくなってしまったから。だから、やなぎはそこに向かうのだ。もっと言えば、《あの感覚》に満ちていたはずの、アートですらそれを語りにくくなったからではないのか。つまり、もしかしたら、アートそのものが中上の言う「路地」だったのかもしれない。しかし、いまではもはや《あの感覚》は呼び覚まされない。それを突破するには、もっと根源的なトポスへと身を移動させること、また、年を重ねた者と、若い人が出会うこと、さらに、肉弾戦でリアルにぶつかること。だから、彼女は演劇/祝祭という形式を選んだのだし、中上というテクストを援用するのだろう。そして、《あの感覚》が揺り起こされ、暗い口を広げた東北の、「生と死」が混在するトポスを発見したのだ。
やなぎはその「移動式路地」をひっさげ、横浜に降誕し、京都へ舞い降り、台北へと飛翔し、人々に《あの感覚》を呼び覚まそうとしている。しかも、それは、苦しみと痛みと悲しみと絶望を味わい尽くし、今また、中心によって忘れ去られようとしている震災後の東北の、それでも、尚、生きなければならない人間のための「賛歌」として呼び覚まされるべきなのだ。