2013年6月29日
イベント
【ASP学科】7/7は授業公開オープンキャンパス!
大学の授業ってどんなかんじ? パンフレットやホームページをみても、いまいちわからない・・・ そんなみなさ...


2013年6月29日
イベント
大学の授業ってどんなかんじ? パンフレットやホームページをみても、いまいちわからない・・・ そんなみなさ...

2013年6月28日
ニュース
青森県立美術館で働く高橋洋介さん(本学科09年度卒業)がご担当された 「すばらしい新世界_再魔術化するユートピ...
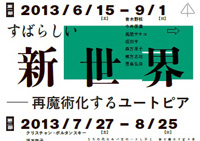
2013年6月27日
ニュース
卒業生の山城大督さん(05年度卒業)がアサヒ・アートスクエアのアーティスト支援事業「Grow up!! Artist Project...

2013年6月26日
日常風景
~博物館実習報告2013 4回生佐伯香菜~ ...

2013年6月24日
ニュース
「もう一つの」世界を創りだすための社会起業家の国際的ネットワークHUB。その京都版HUB Kyotoが先日正式にオープ...
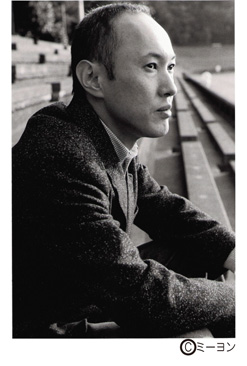
2013年6月24日
イベント
ARTZONEにて、...
