2014年5月30日
ニュース
【明日開催!】ARTZONE 展覧会・イベント情報
展覧会概要 タイトル: 今そしてこれから、それぞれの支援のかたち 会期: 2014.5/31 時間: 18:00ー20...
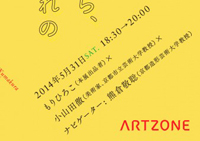

2014年5月30日
ニュース
展覧会概要 タイトル: 今そしてこれから、それぞれの支援のかたち 会期: 2014.5/31 時間: 18:00ー20...
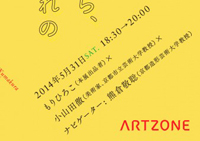
2014年5月26日
ニュース
例年に続いて、今年もASP学科の卒業生を招いてのキャリアイベントを開催します。 これまでのASPの先...

2014年5月25日
ニュース
展覧会概要 タイトル: tanaproject展 会期: 2014.5/31〜6/8 時間: 平日 13:00〜20:00 / 土日祝 12:30〜...

2014年5月23日
イベント
ARTZONEで大好評開催中の『舞妓の美』展。 会期も残すところ今日を入れて3日となってしまいました。 まだご...

2014年5月22日
イベント
21日の特別講義は、本学教授の藤本由紀夫先生にお越しいただき、ASP学科の山下里加先生との対談形式で行わ...

2014年5月21日
ニュース
10年度卒業生の渡川智子さんが『The Post and Courier』(アメリカ/チャールストン)のネット新聞で、紹介...
