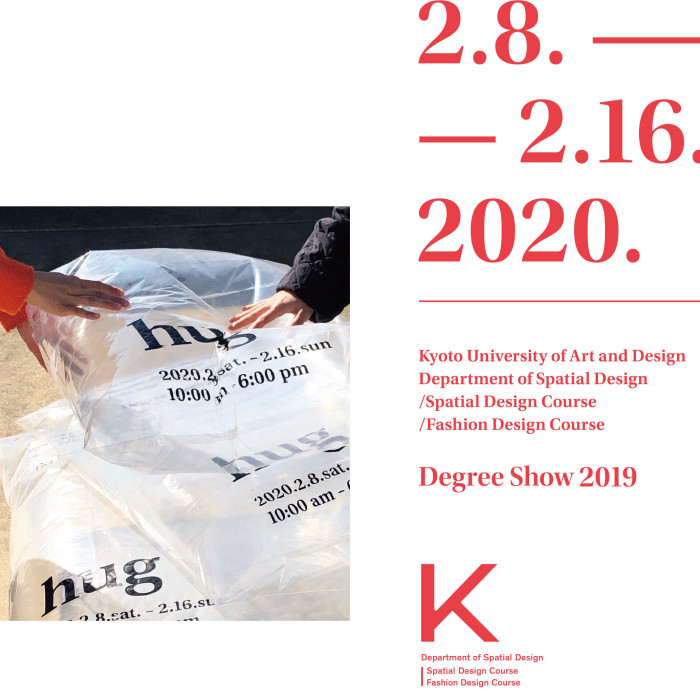2020年2月27日
ニュース
2019年度卒業展ふりかえり【奨励賞紹介】
こんにちは、空デ研究室です。 コロナウイルスに対する警戒心が高まり、大学としても対応に...


2020年2月27日
ニュース
こんにちは、空デ研究室です。 コロナウイルスに対する警戒心が高まり、大学としても対応に...

2020年2月14日
ニュース
こんにちは、空デ研究室です! 本日は「優秀賞」を受賞した 滝口茉由子さん と ヌルアフィファー ルシダ...

2020年2月13日
日常風景
こんにちは、空デ研究室です! 本日は見事「学長賞」を受賞した齋藤慧山くんの作品を紹介し...

2020年2月11日
ニュース
こんにちは、空デ研究室です。 9日は学長内覧と講評会がありました。 朝から、学長が展示スペースに...

2020年2月7日
イベント
こんにちは、空デ研究室です。 昨日は卒業制作のノミネート作...

2020年2月3日
イベント
こんにちは、空デ研究室です。 ついに今日から、大学全体での卒業展搬入がスタートしました! 午前中には、...