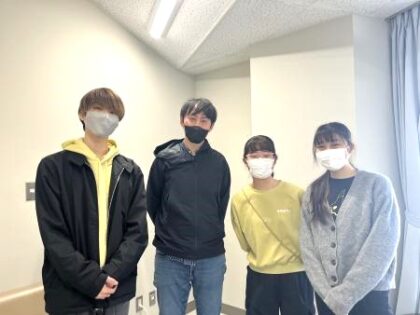- 2023年12月12日
- ニュース
舞台「鬼滅の刃」技術監督 小野先生にインタビュー Part.1
こんにちは!
舞台芸術学科です。
舞台芸術学科 准教授の小野哲史先生が技術監督を担当している『舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入』が2023年11月・12月に上演されました!
舞台「鬼滅の刃」は、吾峠呼世晴さんによる大人気漫画『鬼滅の刃』(集英社ジャンプ コミックス刊)を舞台化した作品です。
公演の詳細はこちら
今回は、技術監督を担当している小野先生のインタビューをお届けします!
舞台芸術学科 舞台デザインコースの1年生3人がインタビューしました♪
左から、川西沙羅さん、谷口華奈子さん、河原大起さん
小野先生は舞台「鬼滅の刃」の現場と大学でのお仕事でお忙しい中、学生の質問に熱く真摯に答えてくださり、非常に白熱したインタビューになりました!
技術監督のお仕事とは?公演中の仕事量は?といった質問から、2.5次元ミュージカルについて、キャリアや人とのつながりの作り方、アイディアの出し方などなど、とっても盛りだくさんな内容になっています♪
まずは、Part.1 『技術監督のお仕事とは?編』です!
Q:技術監督とは主に何をする仕事で、どのような仕事内容ですか?
A:技術監督は、舞台セットの施工の方法や、どういう段取りで施工していくのか、その舞台セットはどういう強度が必要なのかなど、我々の言葉で言えばどうやって仕込んで、どういう転換を実現させるのかということを考えるセクションです。技術的な面を統括していると考えていただけるとわかりやすいかなと思います。
Q:技術監督と舞台監督の違いは何ですか?
A:まず、日本の舞台監督というのは、結構特殊な立ち位置なんですよ。海外では、舞台監督の仕事は、ステージマネージャーとテクニカルディレクターに分かれていることが多いんですね。
日本では、これまで舞台監督がその二つの役割を担っていることがほとんどでした。従来のやり方では、公演の規模によっては1人にかかる負担が大きくなりすぎるので、欧米のように仕事量を分担して、舞台監督と技術監督に分けるのを導入する現場が増えてきているという感じですね。
ステージマネージャー(舞台監督)は、マネージャーと名前についているように、マネージメントしていくことがメインなんですね。作品の運営や、たとえば転換のきっかけをだすこと、役者のケアなど、作品作りのマネージメントをしていくことが舞台監督の大きな仕事です。舞台監督は作品作りの中身をケアします。テクニカルディレクター(技術監督)は、その作品作りの過程で、「ここをこう転換しないとできないね」、「これはこういう仕様に変えないとできないよね」、というようなことを統括していく、というのが大まかな流れです。
もともとはどちらも舞台監督の仕事でしたが、公演によっては、ちょっと手に負えない業務になるので、舞台監督が2人、技術監督が1人という3人体制に分担することもありました。
Q:技術監督は、例えば大道具づくりなどの知識なども必要なんですか?
A:もちろんもちろん、大道具だけではなく、照明も音響も美術もヘアメイクも衣裳も、ありとあらゆることを、どのセクションの人のことも知っていないとできないですよ。
舞台「鬼滅の刃」では、鬼などの人間じゃない役がでてくるのですが、その鬼が次のシーンでは遊女になっていたりするわけですよ。それを実現させるためには、舞台だけでも照明だけでもどうにもなりません。衣裳、ヘアメイク、出演者も含めて、デザインをどうするのか、どこに何がいるのか、何の弊害が起こるかということがわからないとできないですよね。
1つの要素だけをつきつめて作品作りはできません。他のセクションにどういう影響があるのかということを、きちんと各セクションの人と話し合いをしていかないとうまくはいかない。舞台監督や技術監督はそういうことを統括していくから、幅広く知識を持っていないとなかなか難しいです。
Q:実際に現場で何かをするというよりかは、例えば図面を書いて送るような作業のほうが多いんでしょうか?
A:それは仕事のフェーズにも担当する人にもよりますね。
全く釘すら打てない舞台監督もいるし、大道具さん以上に現場でバリバリやれる舞台監督もいます。
だから、どういう人になりたいかによると思う。こうでなければならないというのはないかな。公演をうまくまわしていくために、自分の力をどう発揮するかというのがポイントになります。
これは舞台監督の授業でも話しているんだけど、キャラクターってあるでしょ、人間の。それぞれの個性。これを逸脱するのって結構難しいと思うんですよ。でもそこで無理する必要はないと考えています。自分のスタンスでどうやって効率よく作品作りができるかということを考える方がいい。こうじゃなきゃいけないというのは、おそらくないんですよ。自分のスタンスでこういうことが出来るということが大事で、どうやって結果に結び付けていくか。
例えば、山を登ろうと思ったときに、登り方は何種類もあって、この道しか登っちゃいけないというのはないわけですよ。
持久力があって長距離を歩く方が得意で、急斜面は登りたくないという人は、平坦にずーっと横にグルグル回って登って行ったほうがいい。それには体力が必要だけど、私は体力があるからその方がいいという人もいる。そういう人もいれば、超過密スケジュール、短距離で急速に登るけど、持久力はないという人もいる。
ゴールに着くための手段はいくらでもあるわけですよ。それを実現するための方法は人それぞれ。こうじゃなきゃいけないということはないので、自分のやり方を考えていくといいと思いますね。
以上、Part.1 『技術監督のお仕事とは?編』でした♪
引き続き、小野先生のインタビューをお届けする予定です!
次回も、2.5次元ミュージカルについて、アイディアの出し方など、非常に盛りだくさんな内容になっております!お楽しみに♪