今年もマラルメ!
カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)
こんにちは、制作助手ツカモトです。
先日テント小屋でやっている巡業の芝居を初めて見て、
あまりのパワーに衝撃を受けたツカモトです。
さて、ご報告が遅くなりましたが、
昨年おこなわれました『マラルメ・プロジェクト』の第二弾を
8月14日(日)に開催します!!
題して、マラルメ・プロジェクトII『イジチュール』の夜
マラルメ作品の中でも難解といわれる「イジチュール」に挑みます。
企画、朗読は大学院長・浅田彰、当舞台芸術研究センター所長・渡邊守章、
構成・演出も渡邊守章がおこないます。
前年度と同様に音楽・音響に坂本龍一さんを、
映像・美術に高谷史郎さんをお迎えします!
そして、今回初めてのダンサーの、
白井剛さんと寺田みさこさんが加わります!
実験的でワーク・イン・プログレスなのが特徴であるこの企画。
現在、公演に向けて打ち合わせ&稽古を重ねておりますので、
乞うご期待!
明日14日(火)が友の会先行発売、
あさって15日(水)一般発売開始です!
今年のお盆はマラルメと五山送り火というのはいかがでしょう?
ツカモト
春秋座で“恋”しませんか?
カテゴリー : 過去の公演
突然ですが、皆さんは“恋”してますか??
来い来いと願っても来ないのが“恋”。
“恋”に落ちるような出会いはそうそう転がっているものではありません。
例えば、
クリスマス・イブに寒さに耐えかねて火を借りにきたお針子と詩人が出会うように…
例えば、
気晴らしにと友達と忍びこんだパーティーでその家の一人娘と出会うように…
例えば、
挫折したピアニストがしだいに心惹かれあう声楽家と出会うように…
まるで、ドラマのような…どこかで聞いたような…
そう!
今年の春秋座の夏~秋にかけての社会普及系プログラムは、そんな“恋”をしたくなるような作品が三本も続きます!
普段では考えられないような物語、劇場で美声や美しい肢体から繰り出される技や演技が私たちを非日常のロマンチックな世界に誘ってくれるのでしょう!
どんな出会いにも意味がある。
劇場でお会いしたお客様でそんなことをお話くださった方がいらっしゃいました。
人と人との出会いの縁。
ドラマチックな出会いではなくてもいろんな出会いを大切に思えます。
人と舞台との出会いもまたなにかの縁で結ばれているかのも…
劇場でお待ちしております。
ツチヤ
土蜘蛛の巻
カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)
16日、春秋座では公開講座「日本芸能史」5回目、
壬生大念仏講さんによる壬生狂言が行われました。
「せりふ」を用いない無言劇であることなどが特色とされる壬生狂言ですが、
迫力ある身振り手振りとお囃子によって物語に引き込んでいきます。
今回の演目は『土蜘蛛』。
なんと言っても見せ場は、蜘蛛が吐き出す糸!糸!糸!

とってもキレイで妖艶です。
客席の色んなところから「おぉ~」という歓声が上がっておりました。
この蜘蛛の糸、重石である鉛に薄い紙を巻きつけて、
キレイな放物線を描くように作られているんですが、
なんと全て壬生大念仏講の皆さんによる手作りだそうです。
しかもこの糸を拾ってお財布入れておくとご利益があるんだとか!
演者の方々は普段は自営業をされている方や学生さんで
本職のかたわら練習をし、公演をされています。
慣わしとして、演者の方が表に出てお話をされることや名前を名乗られることは
ほとんどないそうですが、今回は特別に少しお話もしてくださいました。
毎回新しい世界との出会いやサプライズがあるこの「日本芸能史」。
来週は上原まりさんをお迎えして、琵琶の実演を行っていただきます。
どうぞご期待ください。
※受講希望の方はコチラ
さて、本日のブログは私、西村が担当させていただきました。
はじめましてでございます。
それではまた。
西村
歌劇「ラ・ボエーム」始動
カテゴリー : 過去の公演
大嶋です。
数日間の雨の後は、気持ちのいい日が続いております。
こんな気持ちにいい日もあと3週間もすれば梅雨になってしまうんですね…。梅雨前の晴れを有効利用しないと。とりあえず外に出ないともったいないですよね。
さて、HPに掲載が開始しました、歌劇「ラ・ボエーム」の情報をお届けいたします。
先週チラシが出来上がりまして、HPのTOPにもフラッシュが流れております。
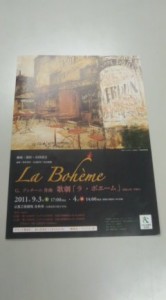
チラシ表面の上の絵は、佐伯祐三「広告“ヴェルダン”」です。茶色を基調とした色彩で、趣があって、華美ではなく、少し憂いがあるけどただ単純に退廃的というわけでなく…。この絵を見るだけで、ラ・ボエームの舞台となった、ボヘミアンたちが集う19世紀パリの雰囲気が思い浮かびます。(実際にこの絵が書かれたのは1927年ごろのようです。)
今回のチラシはなんとA3サイズ2つ折。折った中身はというと…。
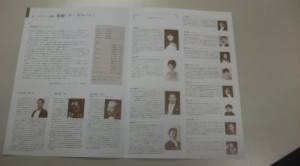
文字と写真がセピア色。
橘プロデューサーのコメントと、構成・演出の岩田氏、指揮の牧村氏、公演監督の松山氏他出演者の皆さんのプロフィールが載っています。
ミミ役(3日)の川越塔子さんは昨年に引き続きのご出演です。また、日本を代表する若手テノール歌手の村上敏明さん(ロドルフォ・3日)や、関西を代表するソリストの方々が続々と出演です。
この公演の演出に関して、岩田さん曰く「劇場の機構を生かして、オーケストラピットもあるけど…花道もある、他で中々出来ないことをやってみたい…」とのこと。これ、要注目ですよ。私も今からワクワクしてます。
岩田さんとは、後日HP等でインタビューの模様をお届けする予定です。
歌劇「ラ・ボエーム」は5月25日劇場友の会先行発売、5月26日一般発売開始です。
大嶋
雪の音
カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)
こんにちは!
先日、こちらで「亀治郎の会」の
レビューを書いた江川です。
今回は、公開連続講座「日本芸能史」、
略して日芸史についてお伝えします!
日芸史は、毎年行われている講座で
今年でなんと9年目。
今年度のテーマは「聖と俗」です。
ひとつひとつの楽器の説明をしているところです。
「鳴り物」とは、日本の伝統打楽器と笛による音楽のことです。
手前にある大太鼓では、「雪の音」を
演奏していただきました。
本来は、雪が降るときに音はしませんが、
ふわふわのボンボンがついたバチで
大太鼓をたたいて
しんしんと降り積もる雪深い風景を
表現されていました。

講師の先生は藤舎呂船(とうしゃ・ろせん)先生です!(画面中央)
先生自らも演奏のご披露をしていただきました!
写真のように、「鳴り物」は
主に三味線音楽と一緒に演奏します。
それから、この授業では、
小皷(こつづみ)が、湿度に大変敏感だということを
実際に聞かせていただきました。
適度な湿度を保っていないときと
息を吹きかけて湿度を調整したときの音が
全く違い、客席から
「おー」という声が漏れました。
おしまいに、
コーディネーターの田口章子先生と
会場の受講生たちと一緒に
「鳴り物」体験として
手拍子で、独特のリズムを教えていただきました。
会場が一体となって
とても感動しました!
今年度の日芸史はあと2回。
1月17日、諏訪春雄先生による「大道芸」
1月24日、丸一仙扇社中による「江戸太神楽」
来年度の日芸史は、いよいよ10周年!
日本の伝統について楽しく学べる日芸史に
ぜひご参加ください!
江川久子



