2014年9月30日
ニュース
10月8日(水)特別講義〜ゲスト:中山博喜(写真家/京都造形芸術大学専任講師)
10月8日開催の特別講義では、前期の最初にも一度ご講義いただいた、本学専任講師の中山博喜先生をゲストに...


2014年9月30日
ニュース
10月8日開催の特別講義では、前期の最初にも一度ご講義いただいた、本学専任講師の中山博喜先生をゲストに...

2014年9月29日
日常風景
4回生の中原光晟くんが、学芸員課程で博物館実習へ行ってきました。 そこでの経験と学びをレポートにまとめ...

2014年9月26日
ニュース
ASP学科の非常勤講師をしていただいている、庭師の山内朋樹先生が、 KYOTO EXPERIMENT 2014のフリンジ企画...
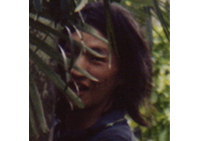
2014年9月25日
ニュース
田中圭子先生のインタビュー記事がwebマガジン『art scape(アートスケープ)』に掲載されています。「アート・ア...

2014年9月22日
ニュース
昨日、本年度の蒼山会 創作・研究補助制度授与式が行われました。 この制度は、本学学生の自主的な創作や研究に対...
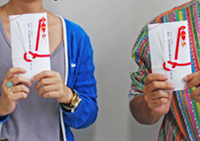
2014年9月20日
ニュース
―あの時の夕日は、 ちょうどミカンのような色をしていた。 弾ける炭酸と共に、あの頃に戻ってみませんか?―...
