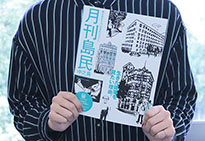2015年10月29日
イベント
12/2 特別講義「表現と仕事」の新しいかたち(ヒビノケイコ)
【講師急病により、日程が変更となりました。11/4(水)→12/2(水)へ変更となります。ご迷惑をおかけしますが、ご...
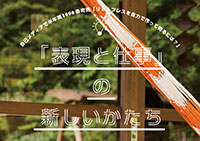

2015年10月29日
イベント
【講師急病により、日程が変更となりました。11/4(水)→12/2(水)へ変更となります。ご迷惑をおかけしますが、ご...
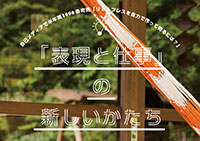
2015年10月27日
イベント
今週末「はならぁと2015」にて 卒業生の山脇益美さん、宿久理花子さんが始めたグループ「月齢会」が 詩のイ...

2015年10月26日
日常風景
10月24日、御所にあるグラウンドで、 学科対抗ソフトボール大会が開催されました。 参加チームは5チーム。...

2015年10月22日
日常風景
10月1日、制作基礎Ⅱの授業で京都市美術館にて行われている「マグリット展」へ行きました。 なんでもこのマ...

2015年10月16日
日常風景
本日は「編集論Ⅲ」の授業をレポートします。 「編集論Ⅲ」は京阪神エルマガジン社で書籍や別冊ムックの編集...

2015年10月13日
ニュース
文芸表現学科3回生・山内優花さんが 9月初めに2週間ほど編集集団「140B」へインターンシップに行ってきまし...