2013年4月29日
イベント
春のオープンキャンパス
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、4月28日(日)、29日(月/祝)の2日間、本学では春のオープンキャン...


2013年4月29日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、4月28日(日)、29日(月/祝)の2日間、本学では春のオープンキャン...

2013年4月29日
日常風景
こんにちは。教員の岡田です。 3回生を対象とする今年度の歴史遺産学演習Ⅰが始まりました。 この授業は学生をA・B...

2013年4月22日
ニュース
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 さて、本日は卒業生が学芸員を務めている資料館から、イベントのお...
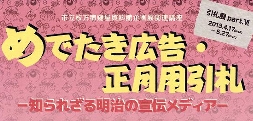
2013年4月18日
ニュース
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今まで学科内でのイベントや授業の内容などをご紹介してきましたが、 今回...
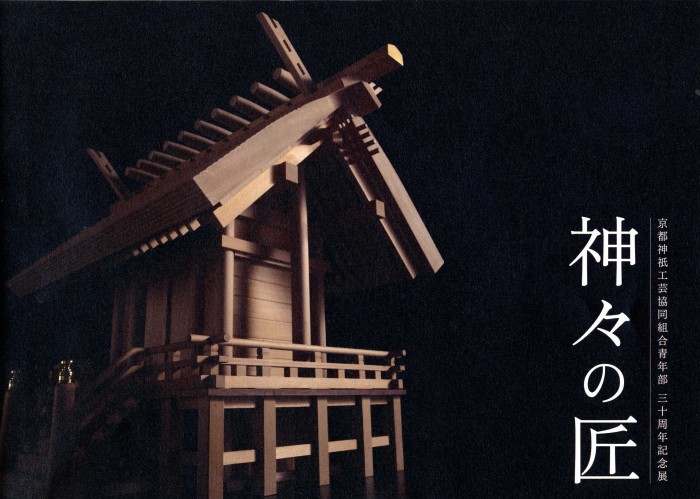
2013年4月16日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今年度最初の授業が早くもスタートし、新入生の皆さんが、学内案内...

2013年4月16日
ニュース
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今年の桜は咲くのが早かったですね。 既に4月1週目の週末に吹き荒れた雨風...
