2014年2月25日
イベント
「舞妓支える職人技紹介」京都新聞に掲載されました!
先日このブログでも紹介した、京都府庁での男衆による着付け実演ワークショップの模様が、 京都新聞に掲載...


2014年2月25日
イベント
先日このブログでも紹介した、京都府庁での男衆による着付け実演ワークショップの模様が、 京都新聞に掲載...

2014年2月24日
イベント
2月22日、23日の2日間、芸術表現・アートプロデュースコースの卒業論文発表会を行いました。 一人あたり15分ほどの...
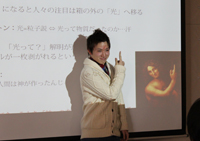
2014年2月22日
イベント
いよいよ本日から卒展が始まります! ASP学科は3月2日まで、人間館4階のNA413教室で展示を行って...

2014年2月19日
日常風景
5月にARTZONEで開催する「舞妓の美 —花街を彩る匠の技—」の調査で、3回生の大西未紗さんと花見堂 直恵さんが...

2014年2月17日
イベント
2月17日から2月28日の間、京都府庁で「舞妓の美―花街を彩る匠の技」2013年度事業報告展が開催されます。 この展覧...

2014年2月13日
日常風景
2回生の金ボンスくんが、淸州国際工芸ビエンナーレを運営する韓国の淸州市文化産業振興財団にインターンにいってき...
