2017年5月29日
日常風景
【学科長短信05】作家・ライター・編集者に学ぶ!
ごぶさたしています。みなさん、お元気ですか? さて、ちょっと日が空いてしまいましたが、今月の...


2017年5月29日
日常風景
ごぶさたしています。みなさん、お元気ですか? さて、ちょっと日が空いてしまいましたが、今月の...

2017年5月19日
日常風景
前期の集中授業として製本について学べる講義が始まっています。 執筆だけじゃなくて、製本まで? と思われるかも...

2017年5月12日
ニュース
先月末に出版された『VEGESUSHI パリが恋した、野菜を使ったケーキのようなお寿司』という、レシピ本とビ...
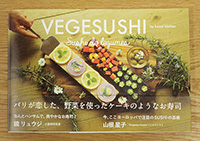
2017年5月10日
ニュース
宿久理花子さん(2011年度卒業)の書き下ろしの詩が、朝日新聞(4月26日夕刊)の〈文芸・批評〉欄に掲載さ...

2017年5月8日
イベント
春のオープンキャンパスにご来場いただいた皆さん、ありがとうございました! こんな風に、教員相談ブース...
