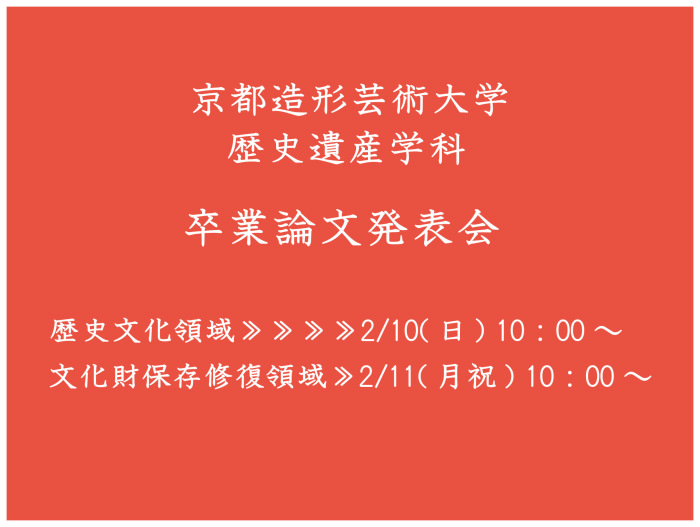2019年2月28日
ニュース
展覧会のご案内 ~小学校が伝える生活資料~
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は、3月2日(土)~と3月4日(月)~開催される2つのパネル展のご案内です...
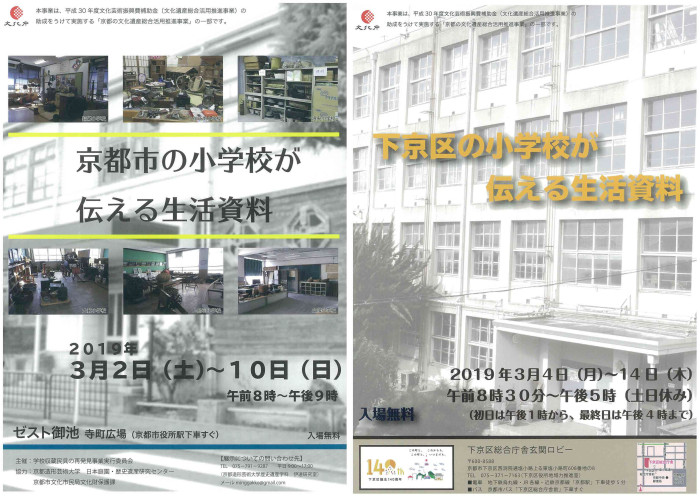

2019年2月28日
ニュース
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は、3月2日(土)~と3月4日(月)~開催される2つのパネル展のご案内です...
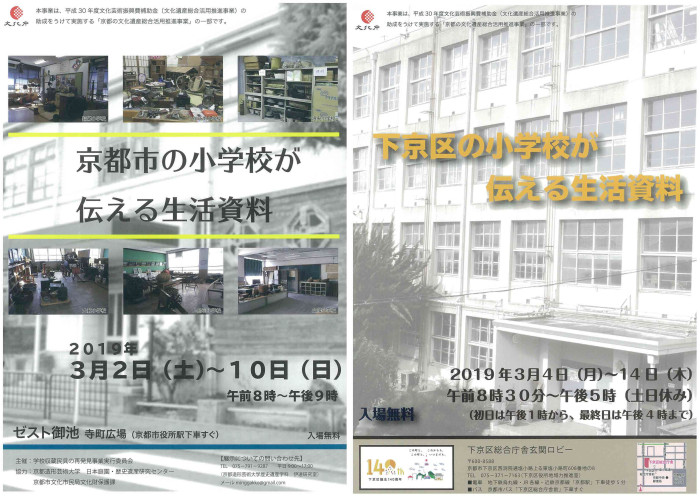
2019年2月26日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 暦の上では春を迎えていますが、まだまだ寒い日が続きますね。 暖かくなる...

2019年2月20日
日常風景
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 1回生「歴史遺産学基礎実習Ⅰ」の授業紹介に引き続き、 今回は2回生「文化...

2019年2月8日
ニュース
みなさん、こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 2月に入り、少しずつ日中の暖かさが感じられる日が増えてきまし...