2019年7月29日
イベント
【歴史遺産】真夏のオープンキャンパス、ご来場ありがとうございました!
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨が明け、いよいよ夏本番ですね!冷たいものがつい欲しくなります。 &nb...


2019年7月29日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨が明け、いよいよ夏本番ですね!冷たいものがつい欲しくなります。 &nb...

2019年7月26日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 今回は7月24日(水)から京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブにて開...
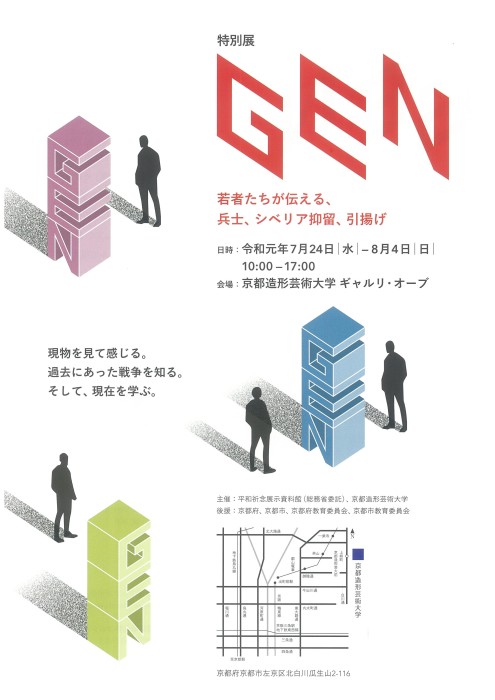
2019年7月12日
イベント
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 7月7日(日)に1日体験入学オープンキャンパスが開催されました! ...
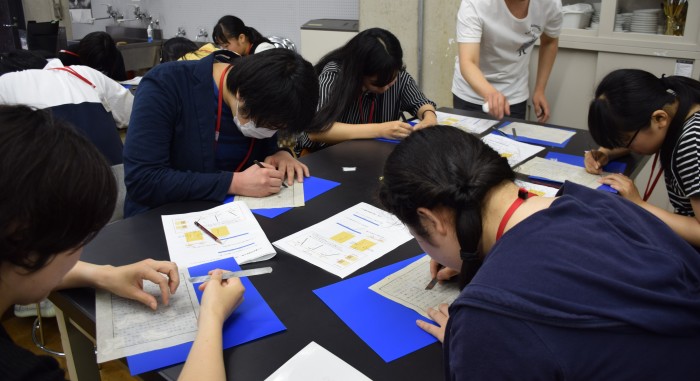
2019年7月3日
日常風景
こんにちは。歴史遺産学科の副手です。 梅雨に入り、曇り空が多い今日この頃ですが、みなさまいかがお過ごしでしょ...
