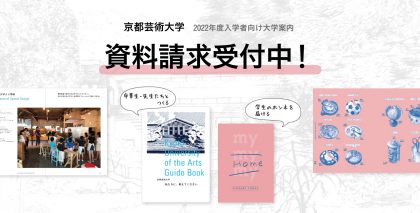- 2021年10月4日
- イベント
多様な染織の在り方を築く 染テキの先生と卒業生が展覧会を開催中【文芸表現 学科学生によるレポート】
違うジャンルを学んでいても、芸術大学でものづくりを楽しむ気持ちは同じ。このシリーズでは、美術工芸学科の授業に文芸表現学科の学生たちが潜入し、その魅力や「つくることのおもしろさ」に触れていきます。
文芸表現学科・2年生の出射優希です。大学の中で行われている染織テキスタイルコースの展覧会に際し、八幡はるみ先生にお話をお聞きしました。
学内でものづくりに対する刺激をたくさん頂き、幸運な環境だな……としみじみ思わずにはいられません! 多様な作品から、卒業生の方が自らの手で掴まれた多様な生き方を感じます。
なお、今回の記事のなかの写真は、京都芸術大学の広報課によって撮影されたものです。
●師の言葉と作品が、会場を包む
現在、人間館1階ギャルリ・オーブにて「Colors 染めの世界・八幡はるみと卒業生」が開催されています。
染織テキスタイルコースの立ち上げから指導されてきた八幡先生が、退職されることを機に企画された今回の展覧会には、壁面の師の作品と言葉に包まれるように、卒業生の作品も並びます。

染織の中でも最新の「デジタルプリント」という技法を用いて作られた掛け軸。
唯一壁面を用いて展示されていますが、実はこれが八幡先生の作品なのです。

●未来型の道具「軸」と最新技術の出会い
布に刷る工程も機械が行うため、「データを作るところまでが私の95%の仕事」と語ります。
ずっと昔からある軸の表現と最新の技術が出会うこととなった背景には、八幡先生のある思いがありました。
戸惑いなく新しい技術を取り入れていく姿勢はただそれだけではなく、昔から既にある柔軟さを丁寧に拾い上げることで成り立っているのです。

既存の価値観を自分の中で理解し消化することの楽しさを、八幡先生の言葉から感じます。
●染織の在り方へ、それぞれの回答
展覧会を彩る八幡先生の言葉のなかに「色には絶対値はなく、むしろ曖昧に捉えることを勧めてきた。」とあります。
物事の捉え方や価値を、自分で考えた上で選択する師の姿を見てこられたからこそ、今回のように多様な作品が並ぶのかもしれません。
展覧会に参加している卒業生は皆共通して、大学院で「考える時間」を持ったことが大きく作品に影響を与えているのだと言います。

↑野村春花さんの作品
八幡先生は、染織というジャンルがアートと工芸の狭間で揺れ動いてきた歴史を肌で感じ、「本当に居心地の良い染織の在り方とは何なのか」を自身に、そして教え子たちに問うのです。

↑塩見友梨奈さんの作品

↑江島佑佳さんの作品
染織というジャンルの良さの一つは、作品が日常の中で人に使われるということ。
何を作るのか、答えは手を動かすなかで見つけていく、というのは、以前工房に訪れた際にも、学生さんから聞かせて頂いた言葉でした。

●人を育て、進んでいく作品
八幡先生は今回の展覧会を振り返り、こう語ります。
染織の未来とものづくりの未来。そして自分自身で考え築いていくエネルギーを見せていただきました。
それらも全て含めて八幡先生の作品として、大切に受け継がれていくのです。
▶関連記事(瓜生通信)
多彩な才能を染め上げた大きな器「Colors -染めの世界・八幡はるみと卒業生-」展
▶京都芸術大学の資料請求はこちらから