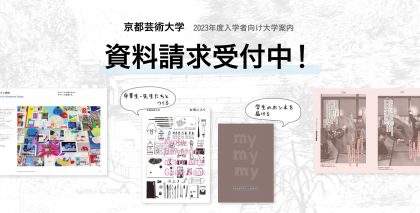- 2022年7月21日
- 日常風景
お茶は「相手のことを思うすべての時間」 時間の流れ自体を大切にする文化を学ぶ【文芸表現 学科学生によるレポート】
違うジャンルを学んでいても、芸術大学でものづくりを楽しむ気持ちは同じ。このシリーズでは、美術工芸学科の取り組みの現場に文芸表現学科の学生たちが潜入し、その魅力や「つくることのおもしろさ」に触れていきます。
文芸表現学科3年生の下平さゆりです。
このごろ、全国で当たり前のように気温30度を超える日が増えましたね。京都では、祇園祭もはじまりました。もう、夏だなあ…。今回は、そうした季節感もふくめた、日常で感じるちいさな変化も大切に扱う、基礎美術コース2年生の茶道の授業に潜入しました。
千秋堂という茶室でおこなわれる、贅沢な授業
学内には、山の上の「千秋堂」という建物に、本格的なお茶室があります。
山の上から京都市内の様子も見渡せるのが、うらやましいなと思うポイントのひとつ。
このお茶室にはもちろん床の間があるのですが、今回の授業では、そこに掛けられた軸や飾られたお花が、実は大切な「お茶」の一部だと知り、ますますお茶という文化の奥深さを感じられました。

「いま」をめいっぱい感じ取るのが、お茶
授業では、お茶にはどんな気持ちで関わるのか、どんなところに楽しみや味わいを感じるのかが丁寧に伝えられていました。
お茶には、その時々の季節の移ろいや、「いま」という瞬間をめいっぱい感じとるということに味わい深さがあります。
季節に合った植物や行事をかたどったお菓子やお花に彩られたお茶室で、畳の香り、空気の香りを感じながら、いま自分が生きているその瞬間に思いを馳せること。その、かけがえのなさ。それは、授業というその場かぎりの人の声を聞くことに慎重になってほしいという、先生のお話からも伝わってきます。その場でしか生まれえないものに、その良さに気づけるようになりたいと思わされました。

↑床の間のお花。「お茶の間で生きているのは花だけ。そこに自分が意味を見つける」と、先生は言います。
お茶はきっと、目の前にいる相手に、その場かぎりの「いま」という空間を相手と共有する、時間に没頭することに意義があるのかもしれません。
「別れがくるとわかっていて、大切に扱う」
そうした心持ちもふまえて、お作法や道具の使い方も実践的に学びます。

お茶室では、言葉を発しません。そこでは、すり足や襖の開け閉めといった動作の音を合図のようにして、お互いがどんな動きをしているか察知することもあります。
「お作法だなんて難しそう」という印象を抱いてしまいそうですが、言葉のない空間で生まれる、人との精神的な距離感には、普段なかなか経験できない心地良さがありました。

↑道具の使い方では、袱紗(ふくさ)の扱い方にそれぞれ苦戦。折ったり包んだりを繰り返すその様子は、まるで手品のようです。
言葉を発しないからこそ、軸にも意義がある
授業で扱う道具は、ひとりに1セット、渡されます。

お茶を点てる際に使う、茶筅(ちゃせん)は消耗品。使える回数に限りがあるからこそ、1回ずつを大切に扱っていきます。
「別れがくるとわかっていて、大切に扱う。人も道具も同じ」。
そんな先生の言葉からも、今回の授業からも、お茶は時間の流れそのものを大切にしてきた文化なのだと思わされました。

↑「松風颯々声」という禅語の軸。言葉を発しないからこそ、軸に意味があります。
お茶は、「相手のことを思ったすべてのこと」。
相手を思うことも、いましかないこの瞬間を味わうことも、特別なようでいて、実は特別ではないかもしれません。
普段から身近にあるものにより深く感じ入って、受けとめようとする時間と心をもつことは、余裕をなくしてしまいがちな今日この瞬間にこそ、わたしたちに必要なものだと、お茶が教えてくれるようでした。
▶京都芸術大学の資料請求はこちらから
▶高校生・受験生向け:近日開催のイベント
👇7/15(金)~8/21(日)|学科独自の体験イベント
👇7/31(日)|ブース型オープンキャンパス
京都芸術大学の全12学科22コースの学びがわかる!体験型ワークショップを開催。
オンライン企画も開催決定!お申込みはこちらから
\大人気!お申込み受付中!/
👇体験入学オープンキャンパス!🛫
8月27日(土)・28日(日)開催!