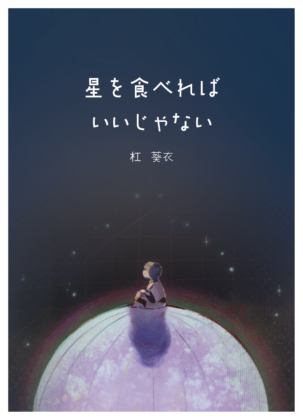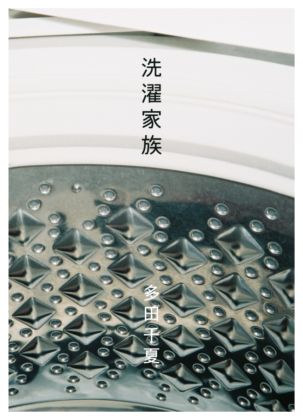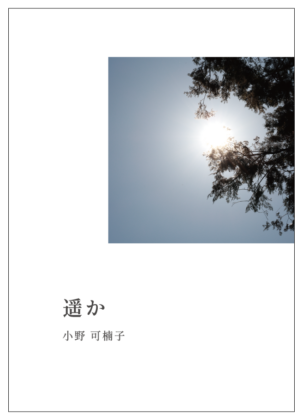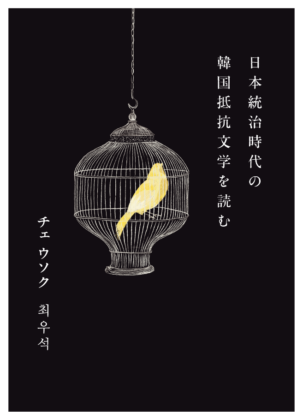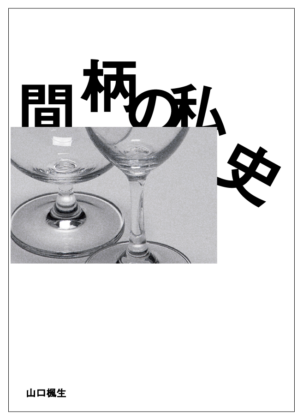- 2025年2月6日
- ニュース
2024年度 卒業制作受賞作品をご紹介します。
こんにちは、文芸表現学科です!
2025年2月8日(土)〜2月16日(日)の9日間にわたり、2024年度「京都芸術大学卒業展/大学院修了展」が開催されます。
文芸表現学科の展示会場では、4年生一人ひとりが、4年間の学習・創作の成果を注ぎ込んで書きあげた小説や映像脚本、エッセイ、ノンフィクション、評論、詩など、さまざまなジャンルの文芸作品を文庫化し、展示・販売を行います。
会期に先駆け、今年度の卒業制作作品・全42作品のなかから、大学および学科が設定している各賞を受賞した8作品をご紹介いたします。
🏆学長賞🏆
映像脚本『星を食べればいいじゃない』
著: 杠葵衣(ゆずりは・あおい)
カヴァーイラスト:山田萌瑛さん(情報デザイン学科3年)
装幀:是松あきほさん(情報デザイン学科2年)
高校三年生の麗は、タカラジェンヌになるための登竜門・宝塚音楽学校合格を目指し、レッスンに励んでいた。ある日麗は、風変わりな転校生・めぐると出会い、スクール講師に「合格には、めぐるの持つ『きらめき』が必要」だと指摘される。
●担当教員講評/山田隆道
超難関の狭き門として知られる、宝塚音楽学校受験合格を目指す少女たちの奮闘を描いた120分劇映画脚本。憧れのタカラジェンヌに必要なのは高い技術よりも強い魅力、すなわち「きらめき」であるという観点で、「きらめき」を持つ者と持たざる者の間で揺れ動く少女の葛藤を、リアルに切実に、残酷に積み上げることで、端正で上品ながらも奥行きと強度のある、これぞ劇文学をかたちづくった。
巧みなシャレードと魅力的なセリフ、丁寧に小箱を積み上げた緻密な三幕構成、そしてチェーホフへのオマージュを感じさせる洗練されたモノローグと示唆に富んだエンディング。これらの「きらめき」にこそ拍手を送りたい。
🎖優秀賞🎖
小説『洗濯家族』
著:多田千夏(ただ・ちなつ)
カヴァー写真・装幀:多田千夏
長女の突然の婚約に湧き立つ平凡な一家、野口家。時を待たず急死した祖母の通夜で、次女のシアキはおかしな家族たちをひとり観察する。退屈さから飼い猫を誘拐し、出会う人すべてに“字幕”をつけて遊ぶが、やがてそれも飽きてしまい……。
●担当教員講評/江南亜美子
野口家の長男である父、母、シナミとシアキの姉妹の暮らしぶりを描く小説ではあるが、読み味はきみょうに愉悦的だ。一人称の「わたし」を担うシアキは、物語世界を遠くから眺めるような客観性と浮遊感を持つ。遺品整理に愚痴をいう父や、姉の婚約者の登場に沸く家族を見る「わたし」の、斜に構えた冷やかさが光る。一人称でありながら三人称のまじるねじれた語りが、シアキを特権的な「主人公」役にとどまらせない。長く連綿とつづく血縁の果てに「わたし」の存在はあるが、それも歴史/時間の一点でしかない生命の不思議、あるいは家族(人間と猫たち)という単位の偶然性を、本作はユーモラスに描く。
🏅同窓会特別賞/奨励賞🏅
ノンフィクション『かんたんでむずかしい「伝える」ということ~ひとつの方法に依拠しないコミュニケーションについて~』
著:工藤鈴音(くどう・りんね)
装幀:大原佳奈乃さん(情報デザイン学科2年)
見ることば、触れる文字、さまざまな方法を用いて、伝えることを決してあきらめない人々の声から、伝えることのむずかしさ、奥深さをあらためて学び、これからのコミュニケーションのかたちについて、著者とともに考えていく。
●担当教員講評/木村俊介
音楽で言えば、ノラ・ジョーンズやジャック・ジョンソンを聴く時のような体温や親密さに安心できる、優しいノンフィクションです。目が見えない、耳が聞こえない、うまく話せないといったやりとりの「クラッシュ」の現場は、人と人とを断絶させるだけでなく、「それがあったからこそ、実は前からそこに存在していた、暗がりや沈黙を通してはじめて触れられる静かな世界」に気づける豊かな接合点・分岐点にもなりうる。そう思えば、うまくいかなさのプロセスをもコミュニケーションの登山の風景を味わうみたいに楽しめる、とわかってくる作中の言葉の積み重ねがいとおしく、ものすごくおもしろいです。
🏅奨励賞🏅(以下、五十音順)
小説『遥か』
著:小野可楠子(おの・かなこ)
カヴァー写真:橋本心音さん(美術工芸学科2年)
装幀:是松あきほさん(情報デザイン学科2年)
美鶴は台所で一人、料理をする。自らの手で食事をこしらえながら静かに物思いにふける。部屋の外では季節がうつろい、食材の旬もうつろい、美鶴の食卓もうつろう。深い水に沈むような回り道の果てにやがて息を吹き返す、再生の物語。
●担当教員講評/仙田学
美鶴の親友だった遥は、ある冬の日に自らの手でこの世を去った。その死を受け入れるために、遥がよく振る舞ってくれていた料理の数々を、美鶴は来る日も来る日も作り続ける。だがどれも、遥の作ってくれたものには遠く及ばない。絶望と希望のあわいで、美鶴は遥を想い続ける。
身近な人の死を、遺された者はどう受け止めていくのか、という問いを静謐な筆致で深めていく秀作。生きることは食べること、食べることは生きること、という事実のどうしようもなさが、ひたひたと迫ってくる。
🏅奨励賞🏅
ノンフィクション『死者をおくる人びと』
著:塩出心愛(しおで・ここあ)
カヴァー写真:太田樹さん(美術工芸学科3年)
装幀:山本小遥さん(情報デザイン学科2年)
インタビュアーである私が納棺師という仕事に興味を持ちアシスタントバイトに応募するところから始まる本作品。
納棺師5名、葬儀社1社への取材を経て書いたノンフィクション。死者をおくる人びとの姿を、あなたに知ってほしい。
●担当教員講評/中村純
自らが納棺師の仕事に携わり、死者、死者に関わる生者への「関与と観察」を通じて、死者と生者のあわいにある縁を結びなおし、みえない尊厳をすくい取ろうとした作品です。
筆者は中学生のときからハンセン病療養所の長島愛生園に通い続け、うち棄てられた人々に向き合い、静かに佇み、話を聴き続けてきました。自身も病の闇の中にいたからこそ、かすかな光を求める人たちの声を聴くことができる。そんな筆者が、声のない死者たちのことを尊厳ある存在としておくりだす納棺師に出会ったことで、おくり人が語り始めます。塩出心愛さんの聴き手としての誠実さ、人間の尊厳への眼差しをリスペクトします。
🏅奨励賞🏅
評論『日本統治時代の韓国抵抗文学を読む』
著:チェ ウソク
装幀:太田茉那さん(情報デザイン学科4年)
日本統治時代の歴史と、暗い時代の中で武器の代わりにペンで戦ってきた3人の詩人を描く。平和と自由を切望し、誰よりも激しい人生を生きてきた彼らの物語と作品を通し、現在の平和な時代がいかに尊いものであることを忘れないでほしい。
●担当教員講評/中村純
日本と韓国の文化を結ぶという志を掲げ、韓国から留学してきた筆者が、尹東柱との出会いを発端として、日本統治時代に詩の尊厳で精神の抵抗をした詩人たちに向き合った評論です。詩人の精神を日本と韓国で探し求め、日本語訳のない文献や詩は自身で翻訳を試みた熱意と胆力、留学生という日韓のマージナルな立場だからこそ可能となりえた藝術立国への試み、意義を大切に考えます。
社会と密接にかかわる韓国文学の同時代性を捉え、現代文学にどのような意味と役割があるか、本質的な問いを呼びかけた筆者の文学的志の高さをリスペクトします。
🏅奨励賞🏅
小説『ant mill』
著:平石峻也(ひらいし・しゅんや)
カヴァー写真:能勢和さん(美術工芸学科4年)
装幀:立石麻子さん(情報デザイン学科2年)
何か目的があるわけでもなく、ただ生きているだけの状態のおじいさん。死ぬ前に何かするべきことを考えた時に、何か忘れてはいけないことを忘れているような気がしてくる。モヤモヤを抱えながら眠りにつくと、夢の世界に落ちていた。
●担当教員講評/江南亜美子
認知症をわずらう老人が家族の団欒のなかにあって、意識の混濁をふりはらうように、遠い過去へと記憶を巡らせるという構造の小説作品だ。だが読み進めるほどに、予想外の場所へと読者はいざなわれる。夢で見る熱帯雨林の森の生活。見知らぬ人々と理解しえない言語での原初的コミュニケーション。そして朝鮮戦争特需にわいた日本の景気。ときに幼児に等しい、ひとりの老人の人生と意識のなかには、なにが沈殿しているのか――。小説でしか描き得ない方法を模索しながら、著者は慎重に掘り起こしている。どこかマジックリアリズム小説に触れたときのような、現実と虚構のすきまに落ちていく読後感がよい。
🏅奨励賞🏅
ノンフィクション『間柄の私史』
著:山口楓生(やまぐち・ふう)
カヴァー写真:渡辺周さん(美術工芸学科3年)
装幀:竹内涼海さん(情報デザイン学科2年)
家族の支えと喪失の間に幸福をみる編集者、居場所を求め自立する元芸舞妓、自分らしさを問い続ける陶芸家——多様な立場で葛藤する三名とともに、多様な間柄や豊かさをみつめる。
なにより普遍的で、なにより個人的な「家族」のインタビュー。
●担当教員講評/木村俊介
どこに行くかわからないボールを投げる。それが、著者が人と会い、「パートナーや親子といった密室的な、人には言いづらい関係のあり方」を聞いて見つけた、愛情のかたちのひとつだと思います。伝わり方がわかりやすく、言う前から受け容れられると知っていることを交換するだけではない「誰にも相談できないまま答えもなく悩み続けてきた歳月や傷や回り道の深さや広さ」を、いわば「どこに行くかわからないボール」として話して大事に渡せることは、どんなに美しいか。今作からは、そんな対話と「あぁ、これがほんとうに考えて書きたいことだったんだな」という実感の喜びがありありと感じられます。
受賞作含む全作品は、会場およびオンラインストアでご購入いただけます。
オンラインストアでは、作品を書いたきっかけなどを語る著者インタビュー記事も公開。
会場に足を運ぶことができない……という方は、ぜひこちらをご活用ください。
▼BUNGEI BOOKSTORE▼
【運営期間】
2025年2月3日(月)10:00〜2月16日(日)17:00
【受注締切】
毎週日曜日正午(12時)※16日のみ17時受注締切
【発送】
発注締切から9日後の翌々週火曜日より随時発送
※商品到着は水曜日以降となります。
※お支払い方法に銀行振込・コンビニ決済をご指定の場合、入金確認の時点で受注完了とさせていただきます。
▼文芸表現学科 卒業展に関する情報ページはこちら▼
https://www.kyoto-art.ac.jp/production/?p=184947
(スタッフ・牧野)