2016年5月26日
イベント
【特別講義レポート】『「瀬戸内国際芸術祭」地方活性化とサポーターネットワーク』甘利彩子さん
5月25日(水)の特別講義は、瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸)ボランティアサポーター「こえび隊」事務局の甘利彩子さん...


2016年5月26日
イベント
5月25日(水)の特別講義は、瀬戸内国際芸術祭(瀬戸芸)ボランティアサポーター「こえび隊」事務局の甘利彩子さん...

2016年5月21日
ニュース
アートプロデュース学科の田中圭子先生が執筆された書籍が出版されました。 ———— 田中圭子 著 『日本髪大全...
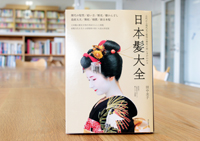
2016年5月18日
ニュース
京に初夏を知らせる葵祭りも終わり、ここから夏まで、アートプロデュース学科では 高校生や受験生の方々に向けたプ...

2016年5月12日
日常風景
5月11日に特別講義『アートを〈編集〉する』を開催しました。ゲスト講師にお越しいただいた櫻井拓さんは、アートの...

2016年5月6日
イベント
みなさんGWはいかがお過ごしでしたか? 今年の京都は運良く天候に恵まれていたので、府外から遊びに来られた方も多...
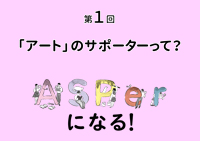
2016年5月2日
イベント
現在ARTZONEにて、展覧会「STRIVE AGAINST FATE」展が開催されています。 本展は、アートプロデュース学科4回生の...
