2018年2月28日
イベント
【在学生の活躍】 きゃらあい個展 『煙に巻く』 開催中
アートプロデュース学科4回生の辻井彩乃さん(きゃらあい)の個展がアトリエ三月(大坂・中崎町)にて開催されてい...


2018年2月28日
イベント
アートプロデュース学科4回生の辻井彩乃さん(きゃらあい)の個展がアトリエ三月(大坂・中崎町)にて開催されてい...

2018年2月23日
ニュース
アートプロデュース学科 2012年卒業生の依田みずきさんが行っている「アーティスト・イン・レジデンス」の取り組み...

2018年2月19日
イベント
2月17日(土)、18日(日)の2日間、卒業論文発表会が開催され、会の最後には授賞者発表と授与式が執り行われまし...

2018年2月12日
イベント
卒展が無事はじまり、本日で2日目!たくさんの方にご来場いただけているようです。ありがとうございます! ...
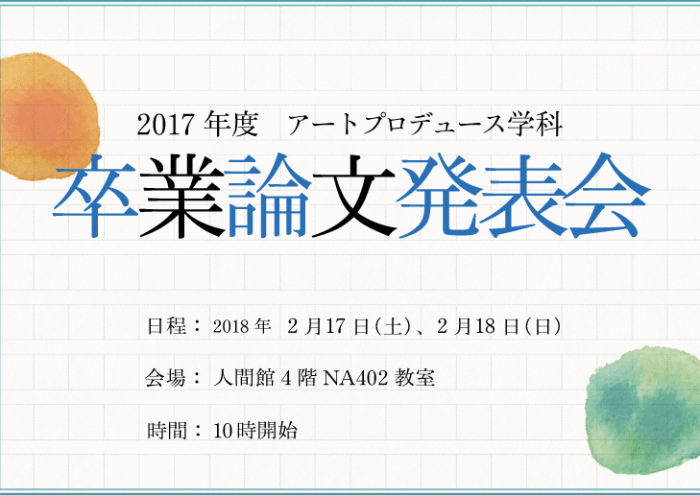
2018年2月10日
イベント
みなさん、こんにちは。 本日10時より、「京都造形芸術大学 卒業展 大学院修了展」がはじまりました! アートプ...

2018年2月7日
日常風景
2018年はじめの特別講義は、甲南大学文学部准教授の服部正さんをお招きし、「包摂あるいは懐柔——アウトサイダ...
