2013年4月29日
日常風景
こどもの時間 × 学生の時間(1)|3・4年次「Czemi」
今年も昨年に引き続き至誠館4階にプレイルームがオープンしました。 Cゼミの3、4年生の授業の一...


2013年4月29日
日常風景
今年も昨年に引き続き至誠館4階にプレイルームがオープンしました。 Cゼミの3、4年生の授業の一...

2013年4月28日
イベント
とてもキレイな青空、そして、もみじもこの季節、新緑がとても美しい今日の京都。 オープンキャンパス初日...

2013年4月27日
ニュース
もうすぐGWですね! これを見ている皆さんは、もう何か計画していますか? ぼくは関東の親戚が京都に遊びに...
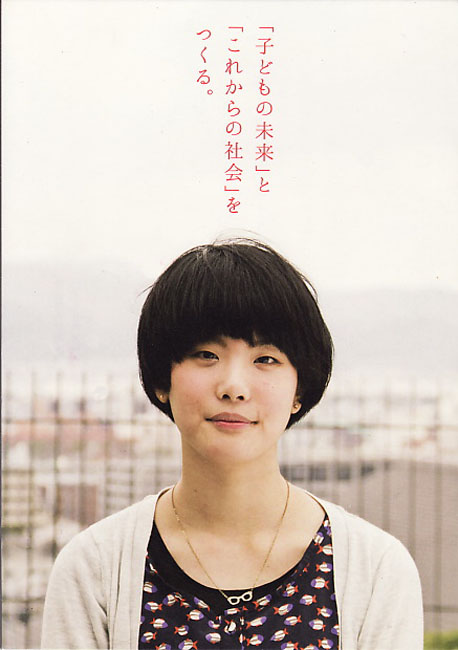
2013年4月24日
日常風景
前期月曜日の2限目3限目のこども芸術研究IVは、こども芸術大学を借りて保育することを学びます。 保育の...

2013年4月22日
日常風景
先週のとある朝、こども芸術学科のある地心館に向かっていると・・・ ほうきを持った女子新入生が二...

2013年4月20日
日常風景
新緑のまぶしい春のうららかな日差しの中、先日15日に知恩寺手作り市がありました。 アクセサリー、...
