2014年12月26日
ニュース
【受賞情報】ゴミ減量コンテストに3名が入賞!
こんにちは!もう今年も残り僅かですね。 2014年最後の情Dブログでは、嬉しいニュースをご紹介します。 京...


2014年12月26日
ニュース
こんにちは!もう今年も残り僅かですね。 2014年最後の情Dブログでは、嬉しいニュースをご紹介します。 京...

2014年12月25日
日常風景
3年生の授業で「大学の半径◯km圏内の問題を解決する」 という課題の発表が行われました。 これは情報デザイン学科...

2014年12月22日
日常風景
2年生の授業で、現在木のおもちゃを制作しています。 「バランス」というテーマで、構想からデザイン、制作まで 全...

2014年12月20日
日常風景
後期集中授業が行われました! 全4回のこの授業では、日本のテレビを中心としたメディアの歴史をふりかえりながら...
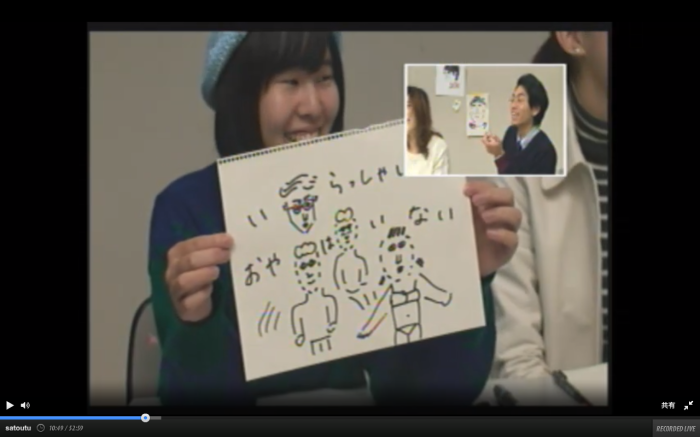
2014年12月17日
ニュース
12月13日(土)は入学前学習プログラム、第二回登学日でした。 入学前学習プログラムとは夏期、秋期コミュニケーショ...
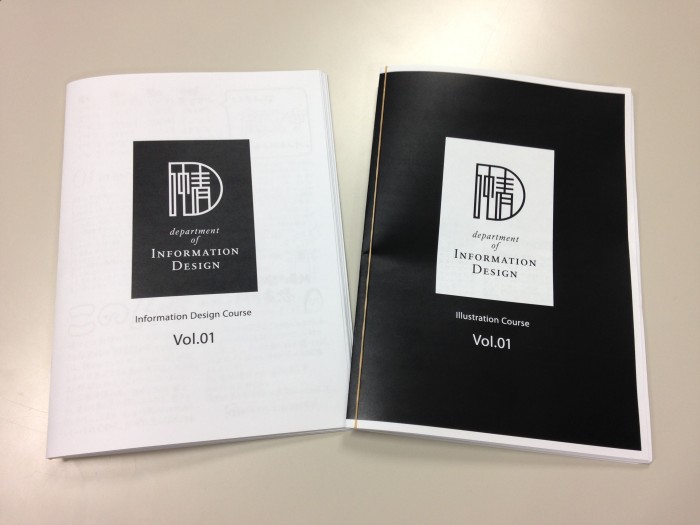
2014年12月12日
ニュース
日本に生まれるさまざまな価値を、クリエイティブの力で海外に発信する映像コンテスト『my Japan Award 2014』で情...
