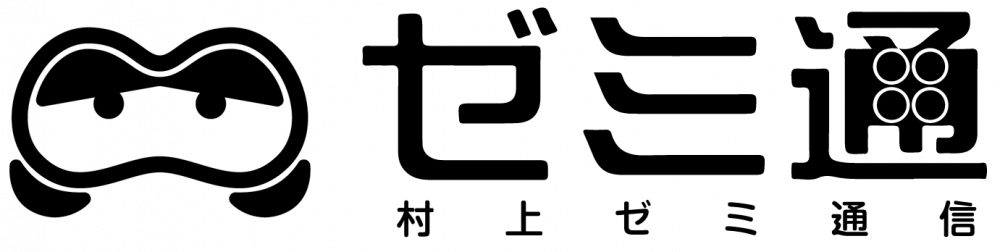- 2022年2月22日
- 日常風景
ゼミ通ヒーローズvol.43「小林鈴果と鈴木うららと卒制作品『Ast1αst』について語るの巻 Part3
※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。
※ゼミ通ヒーローズvol.43「小林鈴果と鈴木うららと卒制作品『Ast1αst』について語るの巻 Part2
の続きから。
村上
では今度はその巨大生物のイメージ作りの話を聞かせてくれる?
鈴木うらら(以下「鈴木」、たまに「うらら」)
最初に考えたのは主人公のラスト君で、その次に世界観、そしてその世界に徘徊する巨大生物っていう順番で考えました。その中で参考にしたのが『スティーブン・ユニバース』っていうカートゥーンネットワークのアニメでした。色遣いが特徴的で、そんなに描き込んでるわけではないのに色彩設計が綺麗で、こんなのを作りたいっていう想いが最初にありました。
全体の雰囲気が見えてきたら、今度は3つの惑星の生態について考えました。砂漠の世界にでっかい木が生えていたら嬉しいとか、電撃地帯には避雷針を模した何かしらの生物がいたらカッコイイなとか考えながらデザインしていきました。
村上
ちゃんと世界観にマッチした生物がデザインされてたし、何よりあの重量感のある演出が良かったよね。キャラクター単体ではなく世界観ありきで総合的に世界が形成されてる点が素晴らしかった。
鈴木
そこは拘ったポイントでしたね。本当にそこに棲んでるように見えることが重要だと思ったので。
卒展会場で販売したビジュアルブックにも設定を掲載してるんですけど、生物の習性なんかも書いてあります。砂漠の世界だと「雲の水分を食べるので体内の水分は豊富で、歩くオアシスみたいな設定になってる」とか、クジラみたいに「死んでも他の生物の栄養になって生態系を回していく」とか、そういう裏設定をまとめています。
ビジュアルブックから抜粋
村上
特に最近の日本のゲームは設定を全部セリフで説明してしまう傾向があるけど、このゲームの場合は説明ではなくちゃんと表現になってるよね。
鈴木
セリフに頼りたくないっていうのは企画当初から話してましたね。オープニングムービーで必要最低限の機会音声みたいなアナウンスが入るだけで、それ以外は全て絵だけを見て世界を感じてもらえるようにしました。
私が物凄く推してる『深世界Into the Depths』っていうゲームがあるんですけど、このゲームにも一切セリフがなくて、UIデザインとか古代のアーティファクトといったデザインで全部表現できているので、じゅうぶんストーリーが伝わってくるんですよ。
村上
やっぱりそういうナラティブを心得たゲームって魅力があるよね。断片的な情報だけを与えておいて、あとはプレイヤーごとに脳内でイメージをつなぎ合わせてくれっていう。
小林鈴果(以下「小林」、たまに「すずまる」)
今回他ゼミの学生もやり込んでくれたんですよ。その子も「最近のゲームは説明ばっかだけど、これはそんなの要らないよね」って言ってくれました。
鈴木
ちょっと難解なくらいがちょうどいいとか、熱く語ってくれましたね。私もオタクなので、狙った通りに伝わってすごく嬉しかったです。
村上
3Dゲームでありながら横スクロールにした意図は?
小林
私の好みでもあり、それ以上にうららの絵って平面的な美しさがあると思うんですよ。それを損ないたくないなって思って。
村上
奥に向かっていく没入感というよりは、レイヤー感を表現したかったと。イラストの世界を旅する感覚というか。
小林
そういうことです。ここは新しい技術に挑戦するよりも元々あるものの美しさを引き出したいというのが大きいですね。このゲームは私たちの好きなものの詰め合わせセットになってます。
鈴木
はい。やりたいことを全部吐き出せたので満足です。
村上
誰が何と言おうと「私たちはこれが作りたかったんだ」って言いきれるところが良いね。
小林
中間合評のときは先生方の反応がイマイチだったので、最終合評のときに私たちの拘りの部分を思う存分プレゼンすることができて「やったったぞ!」ってなりました。
でもまだ優秀賞の実感はなくて、個人的には鈴木うららという人物の世界観を周りが認めてくれたっていう事実が一番嬉しいですね。私が発掘したデザイナーだぜ、どうだ!って(笑)。
鈴木
かっこよ(笑)。
村上
なんか、そのやりとりって一年間続いてたよね。お互いひたすらベタ褒めしまくるっていう(笑)。
小林
私はスケジュールを管理したり仕様書を書いたりデータを整理するのが好きなので、うららには好きなようにやってもらいました。
鈴木
私はビジュアル面で好き勝手にやりたい放題やらせていただいて、足りないところをすずまるに補ってもらって、もう介護まみれの一年間でした。褒められないと伸びないタイプなので。
村上
ビジュアルのところでもう一つ。今回CGモデリング自体も初めてでblenderを勉強しながらの制作になったよね。うららの絵は線画の美しさが特徴的だと思ってるんだけど、それをポリゴンで表現する際に、線画の良さが消えてしまうんじゃないかっていう不安はなかったの?
鈴木
確かに、私の絵は線画を褒められることが多いですけど、まあ何とかなるだろうと(笑)。線だけじゃなくて、配色とかアウトラインも特徴だと自覚してるので、遠目に見ても主人公だと理解できるようにデザインしたし、これだけ守っていれば特に困ることはないだろうと思ってました。
主人公ラスト君の原画とCGモデル
小林
私はワイヤー部分の描画に本当に本当に本当に拘ったので、そこは良くできたと思ってます。
鈴木
ワイヤーの動きを最初見たとき感動しましたもん。ワイヤーを発射する瞬間に手元が光ったり、エフェクト含めて気持ちよさが伝わってきて、職人芸だなって思いました。
村上
エフェクトの「間」の演出も良かったけど、同じくらい効果音も良かったよね。世界観設定的にも孤独感が凄まじくて、広いところに放り出されて、その時の空間内での音の響き方からもキャラクターの心情や世界観がしっかり伝わってきた。
小林
うららの世界観を邪魔しないエフェクトや音響演出を心掛けて、且つ世界を彩るお手伝いをしたいと思ってたので、とにかく綺麗に綺麗に、丁寧に作り込んだつもりです。
村上
そういう気持ちの積み重ねが作品をより良いものにしたってことだね。
ゲーム画面でのエフェクト
村上
ぼちぼちまとめに入ろうかな。4年間を振り返ってどうだった?
鈴木
ゼミのメンバーに恵まれたなって思いましたね。全員仲が良いのに物凄くライバル視していて、常に高いものを求め合う空気感が漂ってたので、そんな関係性が心地良かったです。
そもそも私は怠け者なので、すずまるとチームを組めたのもそうだし、頑張る理由としてはじゅうぶんな環境だったのではないかと思います。
小林
4年間…色んなことがありましたね(笑)。好き放題やって勝手にヘコんで、みたいなドタバタした感じでした。特に2年生のときは毎日「もうどうしたらいいんだー!」って悩みまくってて、何度も村上先生に泣きついた時期もあったり(笑)。
村上
小林の場合、あの辛い時期を乗り越えて、そこからの復活劇が凄かったよね。いきなりVRでゲーム作ったり。
鈴木
私も3年生が一番楽しかったですね。
村上
この世代は2年と3年の間の春休みに一体何が起きたんだ!?って思うくらい劇的に成長した…ていうか全員覚醒したよね。
仕事のスピード感と向上心の高さにビビった記憶がある。
小林
2年生が終わって一安心してたら、その辺りからコロナの関係で大学に行かなくなったじゃないですか。人との適度な距離感があったり一人になる時間が増えて、何をしたらいいのかとじっくり考えるようになったから色々実験してみたっていう感じです。
それ以上に、五十嵐先輩とか門瀬先輩(共にゲームゼミの10期生)とかの卒制作品を見た後だったから、その衝撃が凄すぎて…。
鈴木
そう、それそれ。私たちはこれを越えなきゃいけないのか!?って思って春休みめっちゃ色んなこと考えた。
村上
やっぱり先輩の作品ってのは偉大なんだねぇ。
小林
今度は私たちを踏み台にして、来年の卒展で面白いものが見れたらいいなぁって思います。
村上
ではでは、君らは春からプロのゲームクリエーターになるので、ぜひ世界中を楽しませてくださいね。
では今日はありがとうございました。
小林・鈴木
ありがとうございましたー。