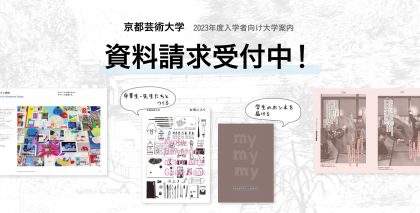- 2022年10月18日
- イベント
「KUA ceramic labo」がギャルリ・オーブにて開催中! コースを超えた実験の場で、作為と無作為の重なりをさぐる 【文芸表現学科学生によるレポート】
違うジャンルを学んでいても、芸術大学でものづくりを楽しむ気持ちは同じ。このシリーズでは、美術工芸学科の取り組みの現場に文芸表現学科の学生たちが潜入し、その魅力や「つくることのおもしろさ」に触れていきます。
文芸表現学科・3年生の出射優希です。昨年もレポートした陶芸展「KUA ceramic labo」が、今年も開催されています。
展覧会開始から数日は気候もよく、吹き抜けから展示場所へ、落ち着いた秋の光が差し込んでいました。
今回は展覧会の様子と、会場での合評(作品の講評会)の風景をお届けします(なお、写真は京都芸術大学職員の作山朋之さんに撮影していただきました)。
陶芸展「KUA ceramic labo」はコースを超えた実験場
人間館1階のギャルリ・オーブにて、展覧会「KUA ceramic labo」が10月19日(水)まで開催中。
「KUA ceramic labo」とは、美術工芸学科の「表現研究」という授業から生まれた取り組みです。写真映像や油画を専門とする美術工芸学科の教員が集い、セラミック(陶磁器)を共通の素材に、学生とともに実験を重ねながら制作を行います。
それぞれの専門領域を超えることで、あらたな考えやものづくりの筋道が生まれてくる場所になっているようです。
今回展覧会に参加するのは「表現研究Ⅰ(神谷徹先生・髙橋耕平先生・福本双紅先生)」「表現研究Ⅲ(清水博文先生・多和田有希先生・福本双紅先生)」の担当教員・受講生、基礎美術コースの2年生、そして総合造形コースで福本双紅先生が指導されている陶芸ゼミのみなさんです。
初日に基礎美術コースの学生が植物を生けたことで、作品や展示風景が大きく変化しているのが印象的でした。
作品として展示され「動き」を止めている焼き物と、日々姿を変える植物。
作品をつくる、表現するという営みだけでなく、つくられたものと生きているものの関係性についても考えさせられます。
作品の搬入後も、ポスターが追加されたり、植物が加わったり、さらにイレギュラーな出来事も迎え入れながら、毎日変化していく展覧会そのものが実験です。
そんな実験の結果や過程を受け止め、次に繋げていくために、福本ゼミのみなさんが作品合評を行っていました。
コントロールできなさを思考し続ける
合評では、作品のそばでコンセプトや制作開始から制作後に感じていたことを話し、ゼミメンバーや福本先生からのフィードバックを受けます。
3年生は外部のギャラリーで行われる展示に向けて、4年生は卒業制作を見据え、普段の会話からさらに踏み込んだ声かけをする場面もあり、みなさん真剣に言葉を交わしていました。
合評のなかで何度も話題にのぼって印象的だったのは、作品に訪れた予測不可能な出来事をどう受け止めていくか、ということ。
陶芸では、窯のなかで起こること、気温や湿度、素材の状態など、人が完全にはコントロールしきれない要素が多く存在しています。
先日、京都高島屋で「なりゆきと思惑」をタイトルに掲げ個展を行った福本先生は、「起こってしまったことは柔軟に受け止める。でもなりゆき任せもあかん」と言います。
「ちょっとでもサボったり単純な判断をしたら、作品から全部ばれる。」そんな福本先生の言葉は、決してネガティブには響きません。
作品が無言で多くを示す不思議さをおもしろがり、心から受け止めてものづくりをしてきたのだろうと想像します。
表現研究に参加する写真・映像コースの髙橋耕平先生も、自身のインスタレーション作品について、作品の全てをコントロールしきることへの疑問と、しかし偶然やラッキーを簡単に持ち込んでしまうことへの違和感がある、と以前別の展覧会でお話ししてくださったことがありました。
陶芸と写真映像。手触りのまったく違うふたつの領域に共通していることは、他の表現にも少なからず通じてくるところがあるのではないでしょうか。
私自身、文芸表現学科で言葉を書いていても、常に言葉のままならなさと格闘する日々です。
工程や素材との向き合い方から生まれる、作品に伴う言葉
さらに、少しずつ角度を変えながら、コンセプトと作品の関係性についても改めて意識させられる場面が何度もありました。
福本先生は「工程や素材との向き合い方から生まれてくるコンセプトもきっとあると思う」と語ります。
そして、コンセプトの役割は作品の「説明」や補助線だけではないのだと、お話しをお聞きしながら感じていました。
手を動かしながら見つけたこと、心の傾くことについて考える。ままならないながらも考えたことを言葉で仮留めしておく。
言葉を、自分が通ってきた道の印として残し、また手を動かしてみる。
それも、コンセプトを文章で置いておくひとつの理由なのだと思います。
「KUA ceramic labo」では、教員と学生がともに陶芸を通して表現方法を深めていく体当たりな取り組みがまだまだ続きます。
会期終了の10月19日まであとわずか。作品によっては販売も行っているようです。
日々変貌する会場に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
▼美術工芸学科の授業「表現研究」関連教員
▶京都芸術大学の資料請求はこちらから
▶高校生・受験生向け:近日開催のイベント
11/6(日)|はじめての学校見学会
京都芸術大学のことが2時間半でよくわかる!
大学説明会やキャンパスツアーなど進路を考え始めた高校生にぴったり👍
お申込みはこちらから