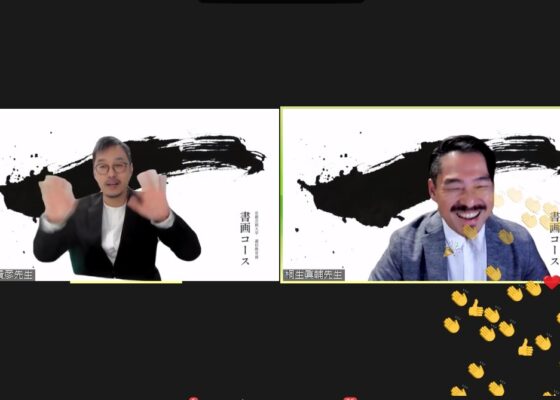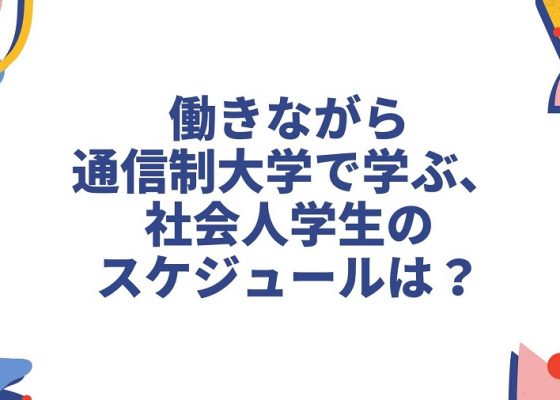通信教育課程 入学課
- 通信教育課程 入学課 記事一覧
- オンライン体験入学のアーカイブ動画を公開します!(2022年11月開催)
2022年12月26日
オンライン体験入学のアーカイブ動画を公開します!(2022年11月開催)
2022年11月に開催した「秋のオンライン一日体験入学」。通信教育部の学科コースごとに模擬授業やミニ講義を通じて芸術大学の学びが体験できる毎年恒例の人気企画です。


今回、当日の様子を期間限定でアーカイブ公開しております。本学に興味がある方や、どんな先生がいるのか知りたい、

学科・コース一覧|京都芸術大学通信教育部
実際に芸術教養学科の授業でも使われている web マガジン「アネモメトリ」の記事をみんなで読みながら、芸術教養の「まなざし」と「方法」、特に「時間のデザイン」「空間のデザイン」「編集」「コミュニティ運営」について考えます。
「アートライティングの視点でみる京都カルチャー散歩」
アートとは何か、アートライティングとは何か、ていねいに説明していきます。同時にミニ講義として、「京都発」のアートライティングをご紹介。大学がある京都は芸術や文化の宝庫です。さまざまな視点や題材によるアートライティングの事例を見ていきましょう。
本コースでは伝統的な書の表現はもちろん従来の書の枠組を超えた書の表現を研究していきます。 体験授業では入学初年度に学ぶ「書と絵画」の授業から、一字書をご紹介。「書と伝統表現」の科目から、行書、楷書の古典としてある王羲之(おうぎし)の「蘭亭序(らんていのじょ)」、欧陽詢(おうようじゅん)の「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」を選び、半紙を用いた臨書の体験学習を行います。
※以下道具を用意いただき動画をみながら一緒に演習いただくとより体験を深めることができます。
①太筆(半紙用、筆管直径1cm程度)②紙(半紙サイズ)③墨液・墨池(固形墨を使用する場合は硯を用意する)④毛氈(下敷き。半紙サイズで可)⑤文鎮(必要な方)⑥エプロン⑦新聞紙(毛氈の下に敷くものがあれば。机の上が墨で汚れる可能性のある制作を行います。)⑧墨で汚れてよい小皿・盆など
水墨画は悠久の歴史と共に発展してきました。筆・墨・紙・硯を[文房四宝]と呼び、それを自由に組み合わせることで多くの名品を生み出しました。授業では墨竹から筆法と造形の基礎を学び水墨画を表現する楽しさを体験してもらいます。筆墨から生まれる心地よいリズムを一緒に体感してみませんか?
※以下道具を用意いただき動画をみながら一緒に演習いただくとより体験を深めることができます。
①筆(穂先4cm程度。兼毫筆や剛毛など少し硬い毛の筆が望ましい)②紙(半紙サイズ)③墨汁(固形墨を使用する場合は硯を用意する)④毛氈(下敷き。新聞紙でもよい)⑤文鎮(必要な方)⑥筆洗(水をためておける容器)⑦白い皿(水分量、墨の濃淡を調整する)⑧雑巾(筆の水分を調整するもの)
パースを理解しなければ背景は描けないと思っていませんか? 本講座では、イラストを描くためにぜひ習得しておきたい背景の描き方について、初心者にも分かりやすく解説します。つい面倒で避けてしまいがちな背景ですが、パースの知識が無くても、ちょっとしたコツさえつかめれば背景は描けるようになります。思わず試してみたくなるようなテクニックの数々を、ぜひ体験してください。
体験授業アーカイブ公開はございません。教員インタビューをご覧ください。
体験授業アーカイブ公開はございません。教員インタビューをご覧ください。
小説を書いてみたいけど難しそう……文章を上手に書きたいけど何から始めればいいかわからない……そんなふうにお悩みの方へ、とびっきりおもしろい「小説の書き方」を学ぶための体験授業を実施します。物語の構造や文章の組み立て方など、基本中の基本を楽しく解説。文芸という表現形態のみならず、出版業界全般や編集者という職業に興味がある人にもオススメ。
伝統文化には、芸能、古典文学、花、茶、書、和歌など多くの分野があります。個々の分野を学んでいくと、知識の点と点が結びついて線になり、さらに線と線が交わって分野どうしの繋がりがみえる、心躍る瞬間に出会うことがあります。授業では、舞台芸能の「能」の詞章を読み、舞台演出を具体的にみていくことで、芸能と古典文学とが織りなす世界を覗いてみます。能は古典文学を題材として取り入れつつも何を独自に表現しようとしているのでしょうか。
私たちは周りにあるものを「あって当然の日常」と感じています。でも本当はあって当然のものなんて何もありません。頭で理解するだけではなく、自分の目と手と心で対象をとらえ直した時に初めて気付く、貴重な素晴らしい宝物があります。日本画は足元の草の一本の語る声に気付かせてくれ、描き続けることで想像もできなかったくらいに日々の輝きを感じさせてくれるでしょう。授業では日本画の作品や素材、また技法もご覧いただきながらその魅力に触れていただきます。
風景画は今日でも多く描かれる対象のひとつです。モネの描いた庭と水蓮、ゴッホの描いた夜景、ダリの描いた不思議な空間も風景に含むことができるかもしれません。風景画はただ美しく心地良いだけでなく、そこに作家の内面性、視点が色濃く現れています。今回の体験授業では複数の風景画作品を紹介し、そこに描かれたものを読み解いていきます。前知識がなくても作品毎に説明があります。ただ描かれただけではない風景画の魅力に一歩踏み込んでみましょう。
皆さんは染めたり織ったりといった作業がご自宅でできるものなのか、と疑問に思っているかもしれませんね。染織はもともと「生活の中の技術」なので、工夫次第で可能です。体験授業では染織コースのカリキュラムご紹介と、実際の授業の様子を動画でお見せします。また小さなスペースでできる織物のデモンストレーションも行います。どんなことを学べるのか、また卒業後の作品制作をどうするのか、といった疑問を解消してください。
入学後にまず自宅で取り組む「写真日記」の課題のレクチャーを通じて、発見や気づきを捉える感覚について学びます。講師は本コース卒業生で、現在は講師として本課題を担当している渡邉真弓先生。写真作家としての活動だけでなく、写真教室や写真関連イベントのオーガナイザー、カメラメーカーとのコラボレーションなど活躍の場を広げる渡邊先生の話を通じて、入学後のご自身の未来像もイメージする時間にしていただければと思います。
グラフィックデザインが扱う専門領域は広く、日常のさまざまな場面で活かされています。今回は入門編として、きっとみなさんも日常的に目にしたことがある企業やサービスの有名ロゴを題材にしながら、そのデザインに隠されたアイデアや秘密を紐解いていきます。近年ではデジタルデバイスに表示させるために、透過するロゴや動くロゴ、多種展開するロゴまで登場しています。そんなロゴデザインを紹介しながら、グラフィックデザインの面白さや奥深さについて触れていきます。
幅広いデザイン領域の中でも建築デザインは、その土地の風土や文化に根ざして設計されています。今回の体験授業では、建築家である講師が旅した世界各地の写真をお見せしながら建築的視点で解説を加えることで、参加されるみなさんにも「建築的に世界を見るまなざし」を体験していただきます。
▼小笹先生が「建築の言葉」による解説をいれているチャット集も併せてご覧ください。
https://vqcb.cdn.msgs.jp/6nvp/vqcb/common/chat_kenchiku.pdf
庭園から公園、自然、環境、観光まで、大きな広がりを持つ本コースの学び。フィールドワークや座学で基礎を学び、デザインや植物、自然環境についての知識・技術を深め、ガーデンデザインや公共空間の設計の応用力を身につけます。今回は、現代の日本庭園に焦点を当て、革新的なデザインの随所に散りばめられた伝統の美意識と技術に迫ります。
空間・モノ・コトという3つの切り口から、デザインを考えます。デザインとは人のよろこびにつながらなければ意味がなく、またそれを考えるには、自ら楽しむという姿勢が大事です。デザインを楽しみながら学ぶこと。この秋の体験入学では「人の集まる場をつくる!」と題して、空間を中心としてさまざまな領域を横断することでつくりあげられる空間演出デザインの展開力をお話ししたいと思います。
詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会
入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。
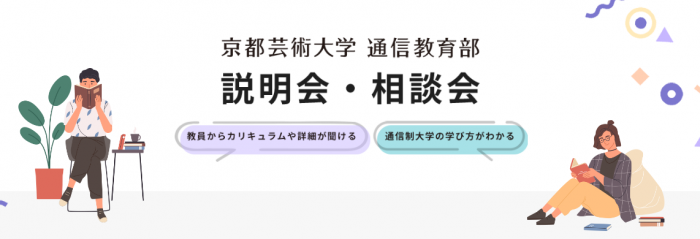


今回、当日の様子を期間限定でアーカイブ公開しております。本学に興味がある方や、どんな先生がいるのか知りたい、

学科・コース一覧|京都芸術大学通信教育部
目次
手のひら芸大
芸術教養学科
「芸術教養のまなざしと方法」
実際に芸術教養学科の授業でも使われている web マガジン「アネモメトリ」の記事をみんなで読みながら、芸術教養の「まなざし」と「方法」、特に「時間のデザイン」「空間のデザイン」「編集」「コミュニティ運営」について考えます。
アートライティングコース
「アートライティングの視点でみる京都カルチャー散歩」担当教員:大辻都、青木由美子
アートとは何か、アートライティングとは何か、ていねいに説明していきます。同時にミニ講義として、「京都発」のアートライティングをご紹介。大学がある京都は芸術や文化の宝庫です。さまざまな視点や題材によるアートライティングの事例を見ていきましょう。
書画コース(書)
「書の芸術、伝統表現と現代表現」担当教員:桐生眞輔
本コースでは伝統的な書の表現はもちろん従来の書の枠組を超えた書の表現を研究していきます。 体験授業では入学初年度に学ぶ「書と絵画」の授業から、一字書をご紹介。「書と伝統表現」の科目から、行書、楷書の古典としてある王羲之(おうぎし)の「蘭亭序(らんていのじょ)」、欧陽詢(おうようじゅん)の「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」を選び、半紙を用いた臨書の体験学習を行います。
※以下道具を用意いただき動画をみながら一緒に演習いただくとより体験を深めることができます。
①太筆(半紙用、筆管直径1cm程度)②紙(半紙サイズ)③墨液・墨池(固形墨を使用する場合は硯を用意する)④毛氈(下敷き。半紙サイズで可)⑤文鎮(必要な方)⑥エプロン⑦新聞紙(毛氈の下に敷くものがあれば。机の上が墨で汚れる可能性のある制作を行います。)⑧墨で汚れてよい小皿・盆など
書画コース(水墨画)
「水墨画を楽しむ心」担当教員:塩見貴彦
水墨画は悠久の歴史と共に発展してきました。筆・墨・紙・硯を[文房四宝]と呼び、それを自由に組み合わせることで多くの名品を生み出しました。授業では墨竹から筆法と造形の基礎を学び水墨画を表現する楽しさを体験してもらいます。筆墨から生まれる心地よいリズムを一緒に体感してみませんか?
※以下道具を用意いただき動画をみながら一緒に演習いただくとより体験を深めることができます。
①筆(穂先4cm程度。兼毫筆や剛毛など少し硬い毛の筆が望ましい)②紙(半紙サイズ)③墨汁(固形墨を使用する場合は硯を用意する)④毛氈(下敷き。新聞紙でもよい)⑤文鎮(必要な方)⑥筆洗(水をためておける容器)⑦白い皿(水分量、墨の濃淡を調整する)⑧雑巾(筆の水分を調整するもの)
イラストレーションコース
「初心者のための背景講座」担当教員:吉田誠治
パースを理解しなければ背景は描けないと思っていませんか? 本講座では、イラストを描くためにぜひ習得しておきたい背景の描き方について、初心者にも分かりやすく解説します。つい面倒で避けてしまいがちな背景ですが、パースの知識が無くても、ちょっとしたコツさえつかめれば背景は描けるようになります。思わず試してみたくなるようなテクニックの数々を、ぜひ体験してください。
週末芸大
芸術学コース
体験授業アーカイブ公開はございません。教員インタビューをご覧ください。
歴史遺産コース
体験授業アーカイブ公開はございません。教員インタビューをご覧ください。
文芸コース
「“シーン”から考える物語のつくり方」担当教員:川﨑昌平、小柏裕俊
小説を書いてみたいけど難しそう……文章を上手に書きたいけど何から始めればいいかわからない……そんなふうにお悩みの方へ、とびっきりおもしろい「小説の書き方」を学ぶための体験授業を実施します。物語の構造や文章の組み立て方など、基本中の基本を楽しく解説。文芸という表現形態のみならず、出版業界全般や編集者という職業に興味がある人にもオススメ。
和の伝統文化コース
「伝統文化の学び ―能と古典文学―」担当教員:森田都紀
伝統文化には、芸能、古典文学、花、茶、書、和歌など多くの分野があります。個々の分野を学んでいくと、知識の点と点が結びついて線になり、さらに線と線が交わって分野どうしの繋がりがみえる、心躍る瞬間に出会うことがあります。授業では、舞台芸能の「能」の詞章を読み、舞台演出を具体的にみていくことで、芸能と古典文学とが織りなす世界を覗いてみます。能は古典文学を題材として取り入れつつも何を独自に表現しようとしているのでしょうか。
日本画コース
「日本画で変わる、ものの見方と日々の輝き」[担当教員]後藤吉晃、松生歩、山田真澄
私たちは周りにあるものを「あって当然の日常」と感じています。でも本当はあって当然のものなんて何もありません。頭で理解するだけではなく、自分の目と手と心で対象をとらえ直した時に初めて気付く、貴重な素晴らしい宝物があります。日本画は足元の草の一本の語る声に気付かせてくれ、描き続けることで想像もできなかったくらいに日々の輝きを感じさせてくれるでしょう。授業では日本画の作品や素材、また技法もご覧いただきながらその魅力に触れていただきます。
洋画コース
「風景画で探索する 創作・表現の視点」[担当教員]藤田つぐみ、奥田輝芳、由井武人
風景画は今日でも多く描かれる対象のひとつです。モネの描いた庭と水蓮、ゴッホの描いた夜景、ダリの描いた不思議な空間も風景に含むことができるかもしれません。風景画はただ美しく心地良いだけでなく、そこに作家の内面性、視点が色濃く現れています。今回の体験授業では複数の風景画作品を紹介し、そこに描かれたものを読み解いていきます。前知識がなくても作品毎に説明があります。ただ描かれただけではない風景画の魅力に一歩踏み込んでみましょう。
陶芸コース
「陶芸とは?器からクレイワークまで技法と作品の解説」[担当教員]西村充、楢木野淑子、田中哲也
陶芸は、毎日の食事に使っている器からクレイワークと呼ばれる立体作品まで実に多様な作品を作ることが出来ます。体験授業ではライブで教員の様々な作品と電動ロクロの水挽きやタタラなどの技法を見ていただき、奥深く幅広い陶芸の世界を感じていただきたいと思います。
染織コース
「染織コースの実際―授業で学べること、卒業後のこと―」担当教員:梅崎由起子、久田多恵、中平美紗子、千葉晃子
皆さんは染めたり織ったりといった作業がご自宅でできるものなのか、と疑問に思っているかもしれませんね。染織はもともと「生活の中の技術」なので、工夫次第で可能です。体験授業では染織コースのカリキュラムご紹介と、実際の授業の様子を動画でお見せします。また小さなスペースでできる織物のデモンストレーションも行います。どんなことを学べるのか、また卒業後の作品制作をどうするのか、といった疑問を解消してください。
写真コース
「『写真日記』で広がる写真の楽しさ」担当教員:勝又公仁彦、渡邉真弓、片岡俊
入学後にまず自宅で取り組む「写真日記」の課題のレクチャーを通じて、発見や気づきを捉える感覚について学びます。講師は本コース卒業生で、現在は講師として本課題を担当している渡邉真弓先生。写真作家としての活動だけでなく、写真教室や写真関連イベントのオーガナイザー、カメラメーカーとのコラボレーションなど活躍の場を広げる渡邊先生の話を通じて、入学後のご自身の未来像もイメージする時間にしていただければと思います。
グラフィックデザインコース
「グラフィックデザインの入口 ロゴデザインを紐解く」担当教員:荒川慎一、上原英司
グラフィックデザインが扱う専門領域は広く、日常のさまざまな場面で活かされています。今回は入門編として、きっとみなさんも日常的に目にしたことがある企業やサービスの有名ロゴを題材にしながら、そのデザインに隠されたアイデアや秘密を紐解いていきます。近年ではデジタルデバイスに表示させるために、透過するロゴや動くロゴ、多種展開するロゴまで登場しています。そんなロゴデザインを紹介しながら、グラフィックデザインの面白さや奥深さについて触れていきます。
建築デザインコース
「建築家の活動から学ぶデザインの視点」担当教員:谷帆奈美、小笹泉
幅広いデザイン領域の中でも建築デザインは、その土地の風土や文化に根ざして設計されています。今回の体験授業では、建築家である講師が旅した世界各地の写真をお見せしながら建築的視点で解説を加えることで、参加されるみなさんにも「建築的に世界を見るまなざし」を体験していただきます。
▼小笹先生が「建築の言葉」による解説をいれているチャット集も併せてご覧ください。
https://vqcb.cdn.msgs.jp/6nvp/vqcb/common/chat_kenchiku.pdf
ランドスケープデザインコース
「ランドスケープデザインとは? 革新と伝統の日本庭園の秘密」担当教員:加藤友規、稲田多喜夫
庭園から公園、自然、環境、観光まで、大きな広がりを持つ本コースの学び。フィールドワークや座学で基礎を学び、デザインや植物、自然環境についての知識・技術を深め、ガーデンデザインや公共空間の設計の応用力を身につけます。今回は、現代の日本庭園に焦点を当て、革新的なデザインの随所に散りばめられた伝統の美意識と技術に迫ります。
空間演出デザインコース
「人の集まる場をつくる!―領域を横断するデザイン―」担当教員:上田篤、岡本正人
空間・モノ・コトという3つの切り口から、デザインを考えます。デザインとは人のよろこびにつながらなければ意味がなく、またそれを考えるには、自ら楽しむという姿勢が大事です。デザインを楽しみながら学ぶこと。この秋の体験入学では「人の集まる場をつくる!」と題して、空間を中心としてさまざまな領域を横断することでつくりあげられる空間演出デザインの展開力をお話ししたいと思います。
詳細・申込|教員から直接話が聞ける!オンライン入学説明会
入学説明会は12月~3月まで毎月開催します。最新情報は上記説明会ページをご確認ください。
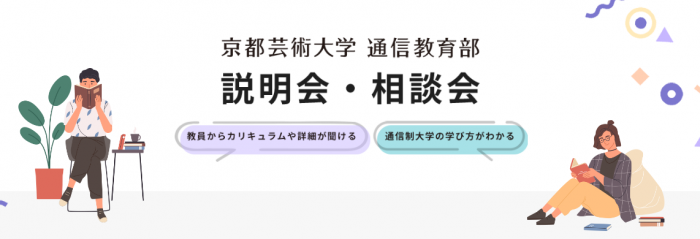
おすすめ記事