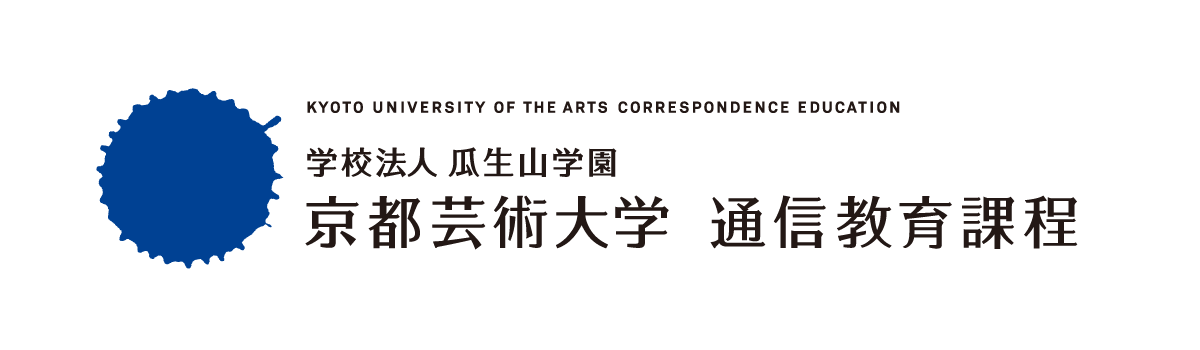アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「社会とはわたしが生きることで作られている。わたしたちが『生きる』ということは、『何かの当事者となる』ことなのではないだろうか」──青山ゆみこ『ほんのちょっと当事者』
2023年03月14日
【アートライティングコース】「社会とはわたしが生きることで作られている。わたしたちが『生きる』ということは、『何かの当事者となる』ことなのではないだろうか」──青山ゆみこ『ほんのちょっと当事者』
 みなさん、こんにちは。アートライティングコース教員の青木由美子です。
みなさん、こんにちは。アートライティングコース教員の青木由美子です。今年の3月は驚くような暖かさで桜の開花もずいぶん早くなりそうです。3月18日の卒業式に向けて、大学の年度末イベントも次々と開催が予定されていて、学生も教員も気分が浮き立っているのを感じます。
さて、上に掲げた言葉は、フリー編集者・ライター青山ゆみこさんの著書『ほんのちょっと当事者』の前書きのなかの一節です。さまざまな時事トピックを自身の実体験に照らし合わせて軽妙に綴ったエッセイですが、2019年発行されてすぐ読んだ時にはあまりに正直にご自分や家族のことを明かされているので驚きました。勇気があるなあ、と。本の帯文にも「ここまで曝すか!」と書いてありました。扱われているテーマは(カードローン)(耳鳴り)(虐待)(性暴力)(介護と看取り)(おねしょ)(障害者差別)(非正規雇用)(遺品整理)。どれも自分事として書くにはデリケートな話題です。青山さんはつねに個人的な体験を冷静かつていねいに紐解くことから問題の実相に迫っています。そして「私の小さな困りごと」を多くの人ひとりひとりの「困りごと」へと開いていくのですが、背景となる社会状況の考察や学問的知見の紹介、行政サービスへのアクセス情報まで目配りした構成で、軽やかで読みやすいだけではないプロの手になる硬質な記事に仕上げています。
「わたしは変わることができるのか」というタイトルの章で、青山さんは小学校5年生の時、聴くこと・話すことに障害があるクラスメイトを班分けのメンバーから排除しようとしたことを告白しています。しかもこのエピソードに7ページを費やし、ことの次第を細やかに描いていて、クラスメイトに彼女が抱いた違和感やかすかな怖れをふくむ微妙な心理が伝わってきました。
大人びた体力のある男子、意思の疎通に手間がかかる相手を、思わず避けようとした少女の振舞いを単純に責めることは難しく、わたしは自分の中に眠る差別意識に向き合わざるをえませんでした。そうなるとこの問題はもう他人事ではなく、胸がざわつき、さまざまな思いが頭を巡ります。『ほんのちょっと当事者』の視点で書かれた青山さんのテキストは、読み手が普段意識しない深部にまで真っすぐ届く推力があることを実感しました。
書籍化される前はウエブ連載されていて、記事がアップされるごとに「実はわたしも~」というメールが多数寄せられ、同じ問題意識を持つ人が世の中にたくさんいることを確信したそうです。かくいう私もこの本を手に取ってから3年余り、看取り、耳鳴りの当事者になりました。
さてそれでは、アートライティングにおける当事者視点とはどんなものでしょうか。
 これは、わたしのことだ。
これは、わたしのことだ。日本では昨年公開されたセリーヌ・シアマ監督の『秘密の森の、その向こう』(2021年、フランス)の鑑賞レビューの中に「おばあちゃんに、さよならを言えなかった少女の物語」というフレーズを見つけ、ハッと胸を衝かれました。「ああ、それはわたしのことだ」と。誰よりも可愛がってくれた、いつでもいちばんの味方でいてくれた大好きな祖母に、わたしはさよならを言えていません。
臨終の時に間に合わなかっただけでなく、なぜか悲しいという感情ももてないまま何十年が過ぎています。当時をふり返ってみれば大学生として独り暮らしを始めたばかりのわたしは、自分のことで頭がいっぱいで故郷や家族にまつわる諸々がすべて煩わしくめったに帰省しなかったのです。もっと会いに行くべきだった。長年胸にしまっておいた悔やむ気持ちがふいに溢れてきました。ああ、なるほど。主人公の少女と母親が森の中で時間を超え、おばあちゃんと触れあったこの作品に、わたしが惹きこまれ、観ている間に心を解きほぐされているような感覚があったのは、そういうことかと腑に落ちたのです。
この個人的な鑑賞体験を軸にして映画評を書くことはもちろん可能ですが、自分事であることがテキストのクオリティを保証するものではもちろんありません。
ただし、自分なりの視点を得る手がかりにはなってくれるように思います。わたしにとって映画『秘密の森の、その向こう』は、第一に大切な人を失った喪失感を乗りこえるための小さな魔法を伴った物語であり、森の中で執り行われる美しい悼みの儀式を描いたフィルムに見えます。ふたりの少女が枝や蔓でつくる小屋の上部が真っ赤に紅葉した葉で飾られた時、魂を天に送る荼毘のイメージが、池に浮かべたゴムボートがふたりを乗せて滑るように進む光景に、水葬のイメージが重なりました。シアマ監督らしい炎と水が散りばめられた色彩豊かな映像から、悲しみでも寂しさでもない詩情があふれてくるという印象が鮮烈に残っています。
うーん、この程度の読み解きではさして新鮮なレビューとは言えませんね。何かもうひとつ補助線が必要な気がします。衣装はどうだろう……。
映画であれ、小説であれ、アートであれ、多くの人にとって魅力的な作品は、鑑賞者が胸の奥にしまっている過去の記憶の蓋を開けてさまざまな感情を噴出させます。それを心が揺さぶられるといい、感動と呼ぶのではないでしょうか。「喪失と回復」はあらゆる分野の創作者が繰り返し取り上げるテーマです。愛する人を失う経験は、誰にとっても避けられない最も痛みを感じる局面だからでしょう。しかも残された者の多くは悔恨に苦しみます。以前は「アートに救われた」「この作品に出会って、楽になった」という発言を聞いても何か得心がいかなかったのですが、年を重ね多くの別れを経験した現在、救われるとまではいかないにしても慰撫される感覚を私も味わうようになりました。
年、ですかね。そうですね。
アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

アートライティングコース
2022年12月21日
【アートライティングコース】アートの基礎体力を鍛えて書く
こんにちは。アートライティングコース担当教員の大辻都です。 2022年もあとわずか。今年一年あったことをふり返るとともに、来年は何をしてどう過ごそ…
-

アートライティングコース
2023年02月27日
【アートライティングコース】アートについて書くことを学ぶとは?
「〈批評〉というものが、その本来の姿において存在し、価値を持ち、〈詩〉に対しては高貴な補完的な操作となりつつほとんどそれに比肩するのは、直接的あるいは崇高なる形…
-

通信教育課程 入学課
2025年10月25日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …