

アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「見慣れた世界を初めて見るかのように見ている」鷲田清一
2023年08月03日
【アートライティングコース】「見慣れた世界を初めて見るかのように見ている」鷲田清一
 こんにちは。アートライティングコース非常勤教員の青木由美子です。夏学期の始まりとともに酷暑と豪雨が続いています。全国各地から受講されている皆さん、大事なくお過ごしでしょうか。どうぞそれぞれ無理のないペースを見いだして学習を進めていただければと思います。
こんにちは。アートライティングコース非常勤教員の青木由美子です。夏学期の始まりとともに酷暑と豪雨が続いています。全国各地から受講されている皆さん、大事なくお過ごしでしょうか。どうぞそれぞれ無理のないペースを見いだして学習を進めていただければと思います。さて、上に掲げた言葉はファッションデザイナー 堀畑裕之さんの著書『言葉の服─おしゃれと気づきの哲学』の帯文として哲学者 鷲田清一さんが寄せたものです。この本の最終章はふたりが京都の町を歩きながら行った対話で構成されていますが、そこで堀畑さんが語ったデザイン理念「いつも見ているものが、見たことのないものになる」に、鷲田さんは「見慣れたものを初めて見るかのように見る」というフレーズで応答したのです。もともとは世界的デザイン会社IDEOの共同創業者 トム・ケリーの言葉だそうです。
この言葉に出会った時、目の前がパッと開けたように感じました。そうか、初めて見るように見ればいいのだと。
ここのところ、私は「見る」ことにナーバスになっています。いや、自分の見る目を疑っている、というほうが近いかもしれません。そう自覚したのは一年ほど前、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』を読んだ時からです。2022年Yahoo|本屋大賞、ノンフィクション本大賞を受賞した作品なので、きっとご存知の方も多いでしょう。全盲の美術鑑賞者 白鳥建二さんとノンフィクションライターの川内有緒さん、友人でアートエデュケーターの佐藤麻衣子さんが全国の美術館を巡るアート鑑賞のレポートで、これを母本にドキュメンタリー映画も制作され本年2月から全国のミニシアターで上映されています。
目の見えない人がどうやって美術作品を見るの? そんな素朴な疑問を抱えてスタートした著者川内さんの試みは、アートについて、障害について、見ること、言葉にすること、共有することについて、気づきと発見に満ちた旅となり、読んでいてほんとうにワクワクしました。なかでもとりわけ面白く感じたのは、アートを鑑賞する場面を再現した以下のような描写部分です。
白鳥、川内、佐藤の3人が初めて一緒に絵画を鑑賞した「フィリップス・コレクション展」(三菱一号館美術館)でパブロ・ピカソの作品《闘牛》(1934年)を前にした会話です。有緒は著者の川内有緒さん、マイティは友人の佐藤麻衣子さんを表します。
─(略)─ちょっとしたカオスだった。わたしたちの描写は見えない的に向かって、あてずっぽうに球を投げるようなものである。
有緒/うーん、馬だね。馬が下を向いているんだ。
マイティ/え、どの馬のこと?馬は二頭いるよね?
有緒/そうだよね、白いのと茶色いの。じゃあ、こっちの右側が闘牛士かな
マイティそう、きっとひとだよね、なんか闘牛士の上にテントみたいのがあるんだけど。
有緒/これ、テントじゃなくて布じゃない?
マイティ/ああ、そうか。これで闘牛してるんだね。でも、闘牛って普通、牛は一頭だよね?
有緒/そうだったかな。
マイティ/スペインで闘牛見なかったの?
有緒/見てない。でもメキシコでは見た気がする。あー、でも全然覚えてない。
話をすればするほどカオスは深まる一方だ。
目の見えない白鳥さんにピカソのキュビズム作品を伝えようと二人の女性が四苦八苦しています。どちらもアートに関する教養も見識も持っていますがそれは横に置いて、目に映るままを口にしているのが子供の会話のようで思わず笑ってしまいました。ここでは引用しやすいようコンパクトにまとまったパートを選びましたが、また別の折、大竹伸朗のコラージュ《8月、荷李活道》(1980年)をもう一人友人を加えた3人で説明した場面では、さらなる混沌へ。大都会のビルを背景にスーツを着た黒人男性がハンカチで顔を拭っている図という説と、アイスクリームショップで白人の子どもがアイスクリームを食べているように見えるという主張がまっこうからぶつかり、それを白鳥さんがニコニコ笑いながら楽しんでいるようすが描かれています。同じものを見ても、人によって見え方が違うことはもちろん承知していますが、ここまで大きな差があるとは! 全盲の人にアートを説明するという特殊なシチュエーションが浮き彫りにした事実に、しばし唖然としました。「見る、言葉にする、共有する」ことの困難さを改めて痛感したのが第一のインパクトですが、同時に、世界の見え方が大きく異なる人たちが、日常的には特に問題なく暮らしているこの社会の在り方がとても不思議に思えてきました。私はそれ以来、「ちゃんと見ているのだろうか?」と折に触れ自問しています。
 是枝裕和監督の最新作『怪物』は、視点を変えると同じ出来事が全く違った様相を現すことを、3章構成で表現した作品です。舞台となるのは大きな湖のある郊外の町。小学校5年生の麦野湊とクラスメートの星野依里、担任の保利先生の間にいったい何があったのか?息子の行動を不審に思った母親早織は教師のモラハラを疑い学校に乗り込んで校長や教頭を問い詰めます。それぞれの言い分がくいちがったまま事態はどんどん深刻な方へ転がり、保利先生の公式な謝罪と辞職へ至ります。この一連の流れを第一章は母親の視点で、第二章は保利先生の視点で描いていますが、母親には見えなかった子供たちや先生の映像が加わるため、第二章になると出来事の輪郭も人物の印象もずいぶん変わります。愛情深い母親が盲目的で身勝手なモンスターペアレントの顔になり、冷淡で無神経な男が子供思いの先生らしく振舞うなど、それぞれ善と悪が入り混じり反転する掴みどころのないキャラクターになってなんとも気味の悪い存在感を発していました。
是枝裕和監督の最新作『怪物』は、視点を変えると同じ出来事が全く違った様相を現すことを、3章構成で表現した作品です。舞台となるのは大きな湖のある郊外の町。小学校5年生の麦野湊とクラスメートの星野依里、担任の保利先生の間にいったい何があったのか?息子の行動を不審に思った母親早織は教師のモラハラを疑い学校に乗り込んで校長や教頭を問い詰めます。それぞれの言い分がくいちがったまま事態はどんどん深刻な方へ転がり、保利先生の公式な謝罪と辞職へ至ります。この一連の流れを第一章は母親の視点で、第二章は保利先生の視点で描いていますが、母親には見えなかった子供たちや先生の映像が加わるため、第二章になると出来事の輪郭も人物の印象もずいぶん変わります。愛情深い母親が盲目的で身勝手なモンスターペアレントの顔になり、冷淡で無神経な男が子供思いの先生らしく振舞うなど、それぞれ善と悪が入り混じり反転する掴みどころのないキャラクターになってなんとも気味の悪い存在感を発していました。第三章で視点は子供たちへ移り、ずっと不穏さを湛えていた映像トーンもナチュラルに変わります。親にも先生にも見せなかった湊と依里の素直な表情や無邪気な行動を目にして、観客はようやくこの映画の真のテーマに気づきます。自分を好きになれない、好きになることを許されない二人の少年が出会い、手を取り、お互いを受け入れていく時間に寄り添うこと。アイデンティティに葛藤する少年をスクリーン上に存在させ、見守ろうとしたのではないでしょうか。終盤、光あふれる草原を二人が走っていく夢の中のようなシーンに重なる坂本龍一氏のピアノの美しい音色が胸に迫りました。
タイトルの『怪物』は一種のパワーワードで、観客の見方をある方向へ誘導しているように感じます。いくつかレビューを読みましたが、乱暴に言えば、その中のかなりの割合が次のような話型になっていました。
─「無意識のうちに怪物は誰だろうと探しながら観始めてしまったが、じきにそういうことではないと気がついた。怪物はみんなの中に潜んでいる」─
シンプルで収まりのよい考察ですし、映画のプロモーションも本編の表現も、そういう読み解きを誘っています。けれど脚本坂本裕二、監督是枝裕和のタッグで今、世に問う作品のテーマとしてはいささか新鮮味に欠けるのではないでしょうか。
脚本を担った坂本裕二さんがパンフレット掲載のインタビューの中で、«視えていない»という視点を出発点として書いた、と語っています。私はむしろこちらに注目します。この作品を最初に鑑賞した時、見えないことについて考えさせるシナリオなのかと思いました。視点が移る構造だからというだけでなく、主要キャストが見えていない状態にあることが小さな間違いを引き起こしストーリーが動いていたからです。怪物という言葉にこだわるなら、それはみんなの内に潜んでいるのではなく、見えない状態でもがいている人のところに現われるのだと思います。
さて、冒頭の言葉に戻りましょう。
「見慣れた世界を、初めて見るかのように見ている」──偏見も予断もなく、まっさらな目で見ることは難しく、そうあれかしと願って、おまじないのように唱えるしかないかもしれません。
自分が見ているものについて、常に疑いの目を用意しておくことは、文章を書くうえで必要かと思います。
青木由美子
アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-
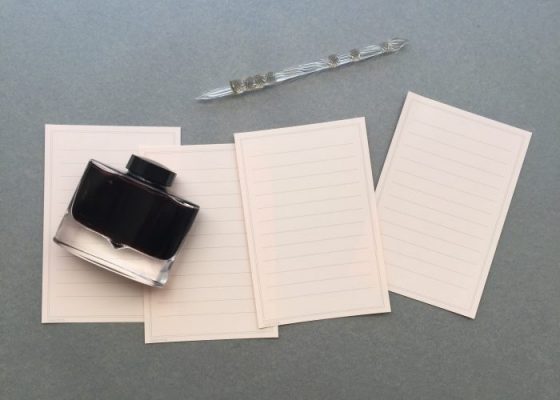
アートライティングコース
2023年02月27日
【アートライティングコース】アートについて書くことを学ぶとは?
「〈批評〉というものが、その本来の姿において存在し、価値を持ち、〈詩〉に対しては高貴な補完的な操作となりつつほとんどそれに比肩するのは、直接的あるいは崇高なる形…
-

アートライティングコース
2023年04月25日
【アートライティングコース】アートは長く、人生は短し Ars longa vita brevis(ヒポクラテス)
こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 花の季節が過ぎ、新緑の季節へ。新入生もすでに授業に参入し、春学期もピークを迎えようとしています。 ことの…
-

通信教育課程 入学課
2025年10月25日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …






























