

芸術教養学科
- 芸術教養学科 記事一覧
- 【芸術教養学科】おおらかなコミュニティをめざして
2024年07月29日
【芸術教養学科】おおらかなコミュニティをめざして
芸術教養学科 早川克美

現代社会において、私たちはSNSやメディアを通じて、多くの人々の意見や行動に触れる機会が増えています。しかし、その一方で、間違いを犯した人に対する批判や炎上が過剰に行われる場面も目立つようになってきました。このような状況を目の当たりにするたびに、私は社会が寛容さを失いつつあるのではないかという懸念を抱いています。
寛容とは、他者の欠点や過ちを受け入れ、理解しようとする姿勢です。それは、他人に対して広い心を持ち、柔軟に対応することを意味します。寛容であることは、必ずしも過ちを許すことではなく、その人がなぜそのような行動をとったのかを理解し、対話を通じて改善を図ろうとする姿勢を持つことです。
昨今のSNSでの過剰な批判や炎上は、寛容さを欠いた行動の典型です。誰もが過ちを犯すものですし、完璧な人間など存在しません。それにも関わらず、他人の過ちを許さず、厳しい言葉で批判する風潮は、社会全体にとって良い影響を与えるものではありません。さらに言えば、関係者以外の部外者が騒ぎ立てることは、問題を全く異なる性質のものへと変容させてしまい、大変よろしくありません。
私たちが必要としているのは、他人の過ちを指摘する際にも寛容さを持ち、建設的な対話を通じて改善を促す姿勢です。妥協して譲歩せよということではありません。寛容さとは、他人の過ちを無条件に許すことではなく、その人がなぜそのような行動をとったのかを理解し、共に解決策を見つけることです。指摘するべき点はしっかりと指摘しつつも、おおらかな心を持って受け止めることが大切です。
例えば、友人が何か失敗をしたとき、その友人を責めるのではなく、その失敗がなぜ起こったのかを一緒に考え、次に同じ失敗をしないための方法を見つけることが重要です。このような態度は、友人との関係をより深めるだけでなく、自分自身も成長させる機会となります。
また、職場や家庭においても同様です。部下がミスをしたとき、そのミスを指摘することは必要ですが、それを単に責め立てるのではなく、そのミスがなぜ起こったのかを理解し、再発防止のための対策を一緒に考える姿勢が求められます。このような寛容な態度は、職場の雰囲気を良くし、チーム全体のパフォーマンスを向上させることにもつながります。
さらに、この寛容の精神は、私たちの大学内SNS「airUコミュニティ」においても大いに必要とされます。「airUコミュニティ」は、学生同士が意見を交換し、学び合う場です。この場においても、他者の過ちや欠点に対して寛容な姿勢を持ち、建設的な対話を通じて互いに成長することが重要です。
例えば、他の学生が不適切な発言をした場合、その発言を即座に非難するのではなく、その背景や意図を理解しようと努めることで、より良いコミュニケーションが生まれます。指摘するべき点はしっかりと指摘しつつも、おおらかな心で受け止めることで、コミュニティ全体の雰囲気が良くなり、より多くの学生が安心して意見を表明できるようになるでしょう。
寛容さを持つことは簡単ではありませんが、私たち一人一人が意識して取り組むことで、社会全体がよりおおらかなものになっていくでしょう。寛容さとは、他人の欠点や過ちを受け入れ、理解しようとする姿勢です。それは、他人に対して広い心を持ち、柔軟に対応することを意味します。寛容であることは、必ずしも過ちを許すことではなく、その人がなぜそのような行動をとったのかを理解し、対話を通じて改善を図ろうとする姿勢を持つことです。
私たちが目指すべきは、指摘するべき点はしっかりと指摘しつつも、おおらかな心を持って受け止める社会だと考えます。寛容さを持ち、他人の過ちを理解しようとする姿勢は、社会全体の調和を促進し、より良い未来を築くための鍵となるでしょう。「airUコミュニティ」においても、寛容さを持った対話が広がり、おおらかで明るく楽しい学びの交流の場となることを期待しています。
芸術教養学科|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

芸術教養学科
2024年05月23日
【芸術教養学科】さらに多様な学びへ!
5月の琵琶湖 みなさん、こんにちは! 今回は芸術教養学科、学科長の下村が担当いたします。 さて5月。爽やかな季節になりました。みなさんはいかがお過ごしでしょうか…
-
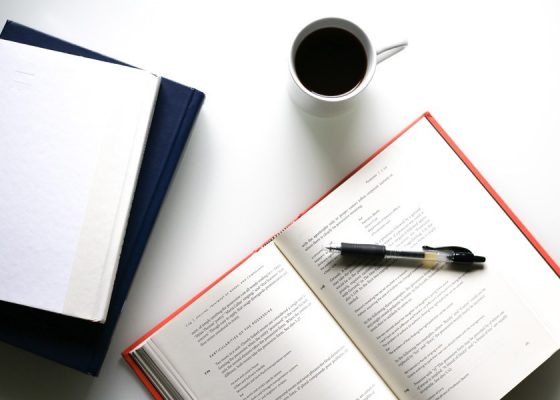
芸術教養学科
2023年07月25日
【芸術教養学科】社会人が学ぶということ〜自負と謙虚
芸術教養学科 早川克美 人生、30年、40年、50年、60年、70年、生きた時間だけ様々な経験を積み、それが生きた証であり、その人の自負となります。自負の「自」…
-

芸術教養学科
2022年08月31日
【芸術教養学科】デザイナーとして大学教育で実現したいこと
芸術教養学科学科長の早川克美先生がWebマガジン「アネモメトリ」へ寄稿されたコラムのまとめをお届けいたします。 日本のデザイン教育や社会人の学び直しについて、ご…






























