

食文化デザインコース
- 食文化デザインコース 記事一覧
- 【食文化デザインコース】1期生に聞きました「食文化デザインコース」での学び
2024年09月26日
【食文化デザインコース】1期生に聞きました「食文化デザインコース」での学び
食文化デザインコース専任教員の宇城安都美です。
食文化デザインコースは2024年4月に開講し、早いもので半年が過ぎました
1期生として400人を超える学生が在籍しており、幅広い年代、お住まい、仕事など、多様なバックグラウンドをもつ方々がそれぞれの目的や思いを持って学んでいます。
そこで、今回は1期生の皆さんが、なぜ食文化デザインコースで学ぶことに興味を持ったのか、どのように食文化デザインの学びを楽しみ、どんな工夫をしながら学びを進めているのかリアルな声を聞いてみました。
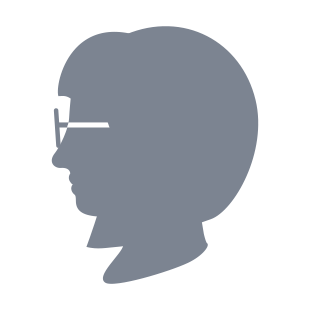
高校を卒業してすぐに入学しました。通学ではなく通信で大学に通いたいと思っていましたが、通信制の大学はIT系の学科が多く、自分が学びたい内容とマッチする学校がなかなか探せませんでした。そんな時に通信で食を学べるコースが新設されるということを知って、これだ!と思い、すぐに入学を決めました。
国内外で活躍するスペシャリストの講師の方々から学べる!ということは魅力的だとは思いましたが、高校を卒業したばかりで、食に関する専門的な知識は無かったので、そんな私でも学びについて行けるかな?と不安でした。しかし講義を見始めるとそんな不安は飛んでいきました。ガイダンスなどで丁寧に学修の進め方も教えてもらえますし、問い合わせフォーム(コンシェルジュ)で大学のスタッフの方や教員の先生方に質問もできるので問題なく学べています。定期的に行われるオンライン学習相談会では、ブレイクアウトルームを作って他の学生の方々と話して交流を持てるのも嬉しいです。
まだ学び始めたばかりですが、特に興味深かった講義は岡根谷実里先生の「世界の食探究」です。日本にいるだけでは、世界のことは遠い別の世界のことだと思ってしまいがちですが、先生の動画教材での講義は、世界のイメージがわかない人たちに寄り添ってくれているような説明で、親しみやすく順序だてて話していただくのでとても面白いです。

料理人として働いていますが、他の分野の知識も学びたいと思って入学しました。調理師専門学校に通って調理技術は学びましたが、食の根本的な部分をあまり知らなかったと思っています。これからの時代はAIが発達したり、世界の食の潮流などの知識と情報を得ているトップにいる人くらいしか活躍できなくなるのではないか、などと不安を感じている私と同じような料理の仕事をしている人はもちろんのこと、今の時代に必要な学びだと思うので様々な方におすすめしたいです。
正直料理人は労働時間も長く、学ぶ時間の確保が難しいです。通勤時間を活用して動画教材を見て、家に帰ってからノートをとる、というような方法で勉強しています。
たくさん面白い講義がありますが、今まで受けた講義の中では、水野考貴先生の「味覚の科学」が料理人としての仕事に役立つなと思っています。また、様々な学びによって、飲食店の厨房で働くという王道の料理人としての仕事以外にも、活躍できる食の仕事がありそうだと思えるようになり、キャリアが広がりそうです。

もともと食に興味があり、料理教室などには通っていましたが、腰を据えて「食」のことを学びたい、日中働きながらでも体系的に「食」を学べる学校に通いたいと思っていたので、こういうコースを待っていました。
3年次編入学で入学したので、最短で2年で卒業できるのですが、じっくり学びたいので3年くらいかけて卒業したいと思っています。学ぶ時間が決められていないので、好きな時間に、深夜でも講義が見られるので自分のペースで学べています。
食に関して領域横断的に広く学べるので、それぞれの職業の人ごとに自分が感じている社会課題に照らし合わせて学びを深められると思います。謎解きをしているようで本当に楽しいです。日頃の食材の選択や料理の場面に色々と生かせる知識があるので日々ワクワクしています。

シンガポール在住 主婦/40代/女性
現在シンガポールに住んでいます。海外在住でも学べるのかはじめは不安でしたが、テキストも電子書籍でも読めますし、海外にいても問題なく課題に取り組めるように配慮されていて大変満足しています。
もともとテーブルコーディネートや料理教室に通うことが好きで、ディプロマやお免状も持っているのですが、もっと広い世界で食を学びたいと思っていました。私は短大卒なのですが、卒業すれば4年生大学卒業資格(学士)が取得できてステップアップにもなるし、まさにこんなコースを待っていました。
ただの習い事ではなく、大学で学んでいるということに自分自身の気持ちも上がります。学生同士のSNSコミュニティもあり、多様な学生さんが学んでいるんだな、ということも知ることができて楽しいです。
提出した課題を一流の先生方に添削・採点してもらえることにも価値を感じます。動画教材も何度も見返せますし、単位取得の講義以外にもコース独自のイベントやミニゼミなどリアルタイムで学べる機会があることも魅力的です。栄養、食文化、など食の専門的なことだけではなく「食の世界観」が学べるというところに魅力を感じている、と友人にもおすすめしています。

食品製造会社経営/40代/男性
食品製造会社を経営していますが、自分の会社が製造している食品以外の知識を広げたいと思って入学しました。自然科学などの理系の学び、社会科学などの文系の学び、また食の具体的な講義もあれば、物事を抽象化して理論でとらえるアプローチの講義もあり、カリキュラムのバランスが良いと思います。
科目に関してはそれぞれの面白さがありすべて興味深く学んでいますが、佐藤洋一郎先生の「日本の食らしさとは」では具体的なトピックスをあげながら講義が進むので面白いです。
食品業界に携わっている人たちにとって、とても学びが深いと感じています。食品の仕事をしていると、どうしても専門分野の情報ばかりが増えていき知識が偏ってしまいます。このコースは体系的に領域横断的に学べるので仕事に役立つと思います。

ウェブデザイナー/50代/女性
食に関わる人を応援するデザインがしたいと思っていました。「芸術大学」で「食」が学べるということを知り、自分にぴったりの学びの場だと思い入学しました。
やはり、働きながら勉強する時間を確保することには苦労しています。動画教材をみて課題に取り組むことは簡単ではないですが、何とか時間を見つけて進めています。イベントなどを通して友人もでき、SNSコミュニティでも新しい気付きがあり充実しています。
食文化に関わること、科学的なことなど、網羅的に講義があるので、今までなんとなくやってきたこと、細切れだった知識が繋がり、どんどん自分の中で色々なことが明らかになってきていることを感じられているので、学びがとても楽しいです。
今回は食文化デザインコースで学ぶ方の中から6名の方の、興味を持ったきっかけや学びの楽しさや学びの工夫などのお話をご紹介しました。それぞれに入学したきっかけや目的は違いますが、同じ講義をそれぞれに咀嚼しご自身の糧にしながら学んでいらっしゃる様子がわかりました。また日常生活やお仕事で時間がない中、それぞれに工夫して学びを進めていらっしゃることもわかりました。食文化デザインコースについて、もっと詳しく知りたい方は、食文化デザインコースの特設サイトもぜひご覧ください。
食文化デザインコース 特設ページ
食文化デザインコース 学生の声
食文化デザインコース Instagram
食文化デザインコース Facebook
食文化デザインコース| 学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから

食文化デザインコースは2024年4月に開講し、早いもので半年が過ぎました
1期生として400人を超える学生が在籍しており、幅広い年代、お住まい、仕事など、多様なバックグラウンドをもつ方々がそれぞれの目的や思いを持って学んでいます。
そこで、今回は1期生の皆さんが、なぜ食文化デザインコースで学ぶことに興味を持ったのか、どのように食文化デザインの学びを楽しみ、どんな工夫をしながら学びを進めているのかリアルな声を聞いてみました。
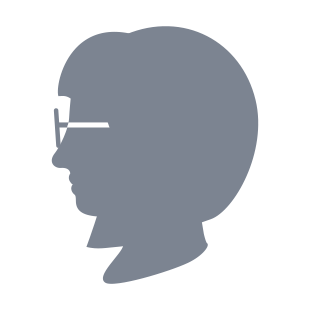
大学生/10代/女性
高校を卒業してすぐに入学しました。通学ではなく通信で大学に通いたいと思っていましたが、通信制の大学はIT系の学科が多く、自分が学びたい内容とマッチする学校がなかなか探せませんでした。そんな時に通信で食を学べるコースが新設されるということを知って、これだ!と思い、すぐに入学を決めました。
国内外で活躍するスペシャリストの講師の方々から学べる!ということは魅力的だとは思いましたが、高校を卒業したばかりで、食に関する専門的な知識は無かったので、そんな私でも学びについて行けるかな?と不安でした。しかし講義を見始めるとそんな不安は飛んでいきました。ガイダンスなどで丁寧に学修の進め方も教えてもらえますし、問い合わせフォーム(コンシェルジュ)で大学のスタッフの方や教員の先生方に質問もできるので問題なく学べています。定期的に行われるオンライン学習相談会では、ブレイクアウトルームを作って他の学生の方々と話して交流を持てるのも嬉しいです。
まだ学び始めたばかりですが、特に興味深かった講義は岡根谷実里先生の「世界の食探究」です。日本にいるだけでは、世界のことは遠い別の世界のことだと思ってしまいがちですが、先生の動画教材での講義は、世界のイメージがわかない人たちに寄り添ってくれているような説明で、親しみやすく順序だてて話していただくのでとても面白いです。

料理人/20代/女性
料理人として働いていますが、他の分野の知識も学びたいと思って入学しました。調理師専門学校に通って調理技術は学びましたが、食の根本的な部分をあまり知らなかったと思っています。これからの時代はAIが発達したり、世界の食の潮流などの知識と情報を得ているトップにいる人くらいしか活躍できなくなるのではないか、などと不安を感じている私と同じような料理の仕事をしている人はもちろんのこと、今の時代に必要な学びだと思うので様々な方におすすめしたいです。
正直料理人は労働時間も長く、学ぶ時間の確保が難しいです。通勤時間を活用して動画教材を見て、家に帰ってからノートをとる、というような方法で勉強しています。
たくさん面白い講義がありますが、今まで受けた講義の中では、水野考貴先生の「味覚の科学」が料理人としての仕事に役立つなと思っています。また、様々な学びによって、飲食店の厨房で働くという王道の料理人としての仕事以外にも、活躍できる食の仕事がありそうだと思えるようになり、キャリアが広がりそうです。

高校教師/30代/男性
もともと食に興味があり、料理教室などには通っていましたが、腰を据えて「食」のことを学びたい、日中働きながらでも体系的に「食」を学べる学校に通いたいと思っていたので、こういうコースを待っていました。
3年次編入学で入学したので、最短で2年で卒業できるのですが、じっくり学びたいので3年くらいかけて卒業したいと思っています。学ぶ時間が決められていないので、好きな時間に、深夜でも講義が見られるので自分のペースで学べています。
食に関して領域横断的に広く学べるので、それぞれの職業の人ごとに自分が感じている社会課題に照らし合わせて学びを深められると思います。謎解きをしているようで本当に楽しいです。日頃の食材の選択や料理の場面に色々と生かせる知識があるので日々ワクワクしています。

シンガポール在住 主婦/40代/女性
現在シンガポールに住んでいます。海外在住でも学べるのかはじめは不安でしたが、テキストも電子書籍でも読めますし、海外にいても問題なく課題に取り組めるように配慮されていて大変満足しています。
もともとテーブルコーディネートや料理教室に通うことが好きで、ディプロマやお免状も持っているのですが、もっと広い世界で食を学びたいと思っていました。私は短大卒なのですが、卒業すれば4年生大学卒業資格(学士)が取得できてステップアップにもなるし、まさにこんなコースを待っていました。
ただの習い事ではなく、大学で学んでいるということに自分自身の気持ちも上がります。学生同士のSNSコミュニティもあり、多様な学生さんが学んでいるんだな、ということも知ることができて楽しいです。
提出した課題を一流の先生方に添削・採点してもらえることにも価値を感じます。動画教材も何度も見返せますし、単位取得の講義以外にもコース独自のイベントやミニゼミなどリアルタイムで学べる機会があることも魅力的です。栄養、食文化、など食の専門的なことだけではなく「食の世界観」が学べるというところに魅力を感じている、と友人にもおすすめしています。

食品製造会社経営/40代/男性
食品製造会社を経営していますが、自分の会社が製造している食品以外の知識を広げたいと思って入学しました。自然科学などの理系の学び、社会科学などの文系の学び、また食の具体的な講義もあれば、物事を抽象化して理論でとらえるアプローチの講義もあり、カリキュラムのバランスが良いと思います。
科目に関してはそれぞれの面白さがありすべて興味深く学んでいますが、佐藤洋一郎先生の「日本の食らしさとは」では具体的なトピックスをあげながら講義が進むので面白いです。
食品業界に携わっている人たちにとって、とても学びが深いと感じています。食品の仕事をしていると、どうしても専門分野の情報ばかりが増えていき知識が偏ってしまいます。このコースは体系的に領域横断的に学べるので仕事に役立つと思います。

ウェブデザイナー/50代/女性
食に関わる人を応援するデザインがしたいと思っていました。「芸術大学」で「食」が学べるということを知り、自分にぴったりの学びの場だと思い入学しました。
やはり、働きながら勉強する時間を確保することには苦労しています。動画教材をみて課題に取り組むことは簡単ではないですが、何とか時間を見つけて進めています。イベントなどを通して友人もでき、SNSコミュニティでも新しい気付きがあり充実しています。
食文化に関わること、科学的なことなど、網羅的に講義があるので、今までなんとなくやってきたこと、細切れだった知識が繋がり、どんどん自分の中で色々なことが明らかになってきていることを感じられているので、学びがとても楽しいです。
今回は食文化デザインコースで学ぶ方の中から6名の方の、興味を持ったきっかけや学びの楽しさや学びの工夫などのお話をご紹介しました。それぞれに入学したきっかけや目的は違いますが、同じ講義をそれぞれに咀嚼しご自身の糧にしながら学んでいらっしゃる様子がわかりました。また日常生活やお仕事で時間がない中、それぞれに工夫して学びを進めていらっしゃることもわかりました。食文化デザインコースについて、もっと詳しく知りたい方は、食文化デザインコースの特設サイトもぜひご覧ください。
食文化デザインコース 特設ページ
食文化デザインコース 学生の声
食文化デザインコース Instagram
食文化デザインコース Facebook
食文化デザインコース| 学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
おすすめ記事
-

食文化デザインコース
2025年02月20日
【食文化デザインコース】初の懇親会が開かれました
こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。 2025年1月10日、食文化デザイン研究室主催の懇親会が開かれました。小山薫堂先生の特別講義の後ということで、…
-

食文化デザインコース
2024年11月26日
【食文化デザインコース】学生主催の「学習会」に参加しました
食文化デザインコースの専任教員 中山晴奈です。 10月、学生が有志で開催した「学習会」が行われ、わたしも少しですが参加してきました。 通信教育部は学習を自分のペ…
-

食文化デザインコース
2024年05月30日
【食文化デザインコース】はじめての入学式と入学ガイダンス
みなさん、はじめまして!食文化デザインコース教員の中山晴奈です。 KUAブログでは、はじめての芸術大学における食文化デザインコースの学生生活や、学習の内容など、…






























