

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「文庫解説400冊への道」(ミステリー評論家 新保博久)
2024年10月30日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「文庫解説400冊への道」(ミステリー評論家 新保博久)
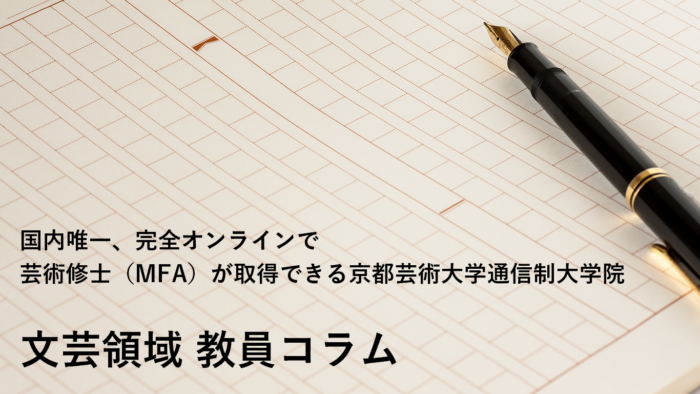
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回はミステリー評論家の新保博久さんのコラムをご紹介します。
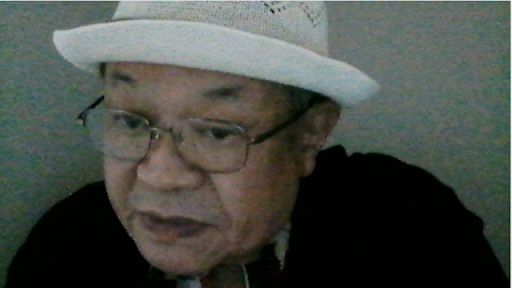
【新保 博久】(しんぽ・ひろひさ)
1953年、京都市生まれ。早大文学部卒。ミステリー評論家。江戸川乱歩賞、横溝正史賞、日本推理作家協会賞などの予選委員・本選委員を歴任。師事する権田萬治氏との共同監修で『日本ミステリー事典』で本格ミステリ大賞を受賞したほか、『横溝正史自伝的随筆集』『シンポ教授の生活とミステリー』など編著書多数。近刊に法月綸太郎氏との往復書簡体エッセイ『死体置場で待ち合わせ』がある(2024年12月刊行予定)。京都芸術大学通信制大学院文芸領域・非常勤講師。
「文庫解説400冊への道」
いつかあなたも、誰かの文庫本の巻末に解説文を書くことがあるかもしれない。
たとえば、あなたが敬愛し目標とも思う作家に、直接ではなくともSNSあるいは自身のブログなどで送りつづけてきたラブコールが、ご本人や編集者の目に留まる。そこで、こんど出る文庫の解説を、と頼まれる場合もあるだろう。はたまた、仲良しの同輩書き手から依頼されるか、これは結婚式のスピーチみたいなものだから断るわけにもいくまい。
小説を書きたい、作家になりたいと夢見る人は多いけれども、文庫解説なるものを頼まれてみたいとは、あまり思わないだろう。それはデビューした結果のオマケであって、そこを目指すのは本末転倒だ。だが一方、そうした文庫解説に生業の多くを負っている種族もあって、彼らを評論家という。私もその一人で、三百冊以上、ひょっとすると四百冊近く文庫解説を書いてきた。そうなると、好きな作家ばかりの解説というわけにもいかないのだが、気に入らない客にも愛想よくしなくてはならないのは、どんな稼業でも同じだ。
しかしまあ、三百数十冊かと溜息も出る。原稿用紙換算で一冊十枚としても約四千枚、一冊丸ごと書く場合の十冊分なので、四十五年間の仕事としては驚くまでもない(解説の原稿料は雑誌に書く二倍以上でも、それだけでは食べてはいけないのだが)。現在の新刊文庫や電子書籍には巻末解説などないものも多いが、私が参入した一九八〇年には文庫本に解説はついていて当たり前であった。エンタテインメント小説が膨大に文庫化されるようになりはじめた時代、解説の書き手が足りなくなり、横溝正史のように専属的な書き手がいるのはむしろ例外だから、多少筆が立つ者にはどしどし仕事の注文が舞い込んだ。
いま、読者は気に入りの作品を見つけて、この作家の著書、あるいは似た傾向の本について情報を得たい、あるいは同じ本を読んだ人の感想を知りたいと思ったら、当該本に添えられた “わかっちゃいねえんだクン” 一人の解説より、インターネットの集合知のほうが頼りになる。解説の役割も変わらなければいけないのだ。
昔は、作品を一読しただけでは分からないレアな知識や情報を盛り込めばいいと思っていた。最近では、解説それ自体を読ませる芸のほうが大事だと考えている。その割に滑ってばかりいるのは内緒だけれども。
このあいだ解説したのは『江戸川乱歩トリック論集』という本だ。三百何十分の一かの仕事にすぎないのだが、実は特別の感慨がある。その本は、乱歩によるミステリー・ガイドブックふうエッセイに大幅増補した新版で、今はなき現代教養文庫から出た元本『探偵小説の「謎」』こそ、中学生のとき出会った私がその後の人生を変えられた一冊ともいえよう一冊なのだから。
「本が誰かの人生を変えるとしたら、それは頭の上に落ちてきたときだけだ」(山田蘭訳『カササギ殺人事件』)と、当代人気随一の推理作家アンソニー・ホロヴィッツは何かの引用なのだか記したことがあるが、一冊の本は足の小指の上に落ちてきても人生を変えうるだろう。『探偵小説の「謎」』は私の体のどのあたりに落ちてきたのか。
いろいろトリックや犯人名が明かされており、今ふうにいうならネタバレ満載の要注意本だが、一冊で翻訳ミステリー数十冊分の知識が得られる、これも今どき語でいうとコスパの良い本でもあった。一読するや中坊が、いっぱしの推理小説通を気取れたものだが、同時に、不用意にネタバレを犯すと顰蹙を買うといった反面教師でもあり、後年ミステリーの文庫解説などをどんなふうに書けばいいのかも、この本から学んでいたような気もする。
江戸川乱歩といえば少年探偵団シリーズをすっ飛ばして、ホームズやルパンの児童向け版から入門し、クリスティーやクイーンの文庫本を読みかけていたころで、書店のそういった棚の文字どおり延長線上に『探偵小説の「謎」』は売られていた。それを買ったのがファースト・コンタクトだが、乱歩についてはちょっとうるさいよと年取ってうそぶくようになるとは知る由もなかった。
二十数冊の江戸川乱歩を含む四百点近い文庫解説は、書こうと思って書いたわけではない。いずれ小説でも物するつもりで、それまでのつなぎにと始めたのが、次から次へと注文があって抜けられなくなった結果だ。ひとまとめにして眺めても、成果物というより、こんなものを書くはずでなかった人間の墓碑銘にも見える。
そういう世界に『探偵小説の「謎」』から入ったともいえる者が、人生の黄昏に入ってその増補版の解説を宛がわれることに、円環を閉じた想いに駆られるのは個人的な感傷で、あなたがたには知ったこっちゃないだろう。今ここまでのおしゃべりが、誰かに何か教訓を与えるとしたら、ひとは望もうが望むまいが結果的に何者かになってしまう、その道への分岐点がどこかにあり、だがその時には分からないって、当たり前すぎて教訓にもならないか。しかし、何か面白そうな翻訳ものを一冊、買うのをあきらめて、さのみ関心のなかった江戸川乱歩の本を書店のレジに持って行った(中学生の小遣いではいちどきに一冊しか買えなかった)――という私の体験の、「翻訳もの」「江戸川乱歩」に違うものを代入すれば、似た決断をする瞬間が絶対あなたにも訪れるはずだ。え、書店で本を買うなんてない、ネットでクリックするだけだと。いや、同じことなんだって。
——————————————————
説明会情報
【2024年11月7日(木)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)
「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」
この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。
しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。
気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。
登壇者一覧)
■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者
*池田雄一(文芸評論家)
*藤野可織(作家)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月20日(水)19:00~20:30】
芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編
「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」
ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。
エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。
登壇者一覧)
■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者
*田中尚史(編集者)
*野上千夏(編集者)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
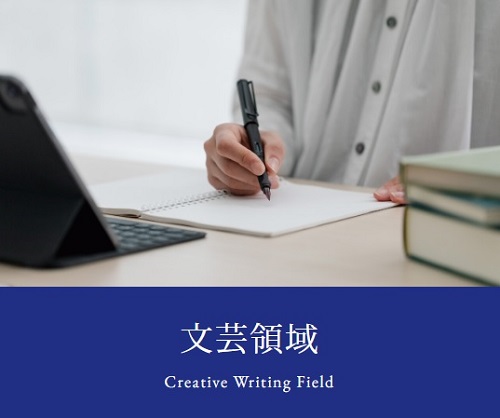
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事
- 記事がありませんでした
-
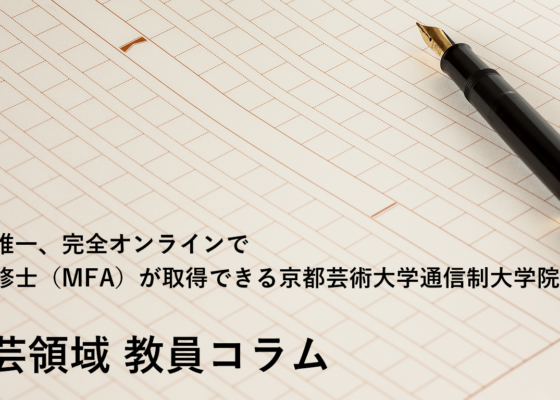
通信制大学院
2024年10月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「私が書いて私を知る」(作家 佐藤 述人)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家佐藤 述人さんのコラムをご紹介します。 【…
-
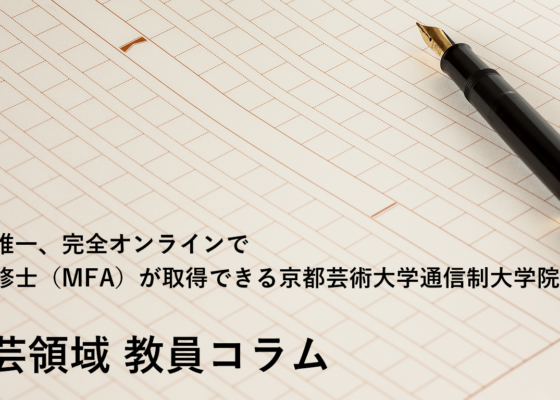
通信制大学院
2024年10月14日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「競馬を予想するように、文章を書いていく」(書評家、ライター あわい ゆき)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は書評家、ライターのあわい・ゆきさんのコラムをご…






























