

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「競馬を予想するように、文章を書いていく」(書評家、ライター あわい ゆき)
2024年10月14日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「競馬を予想するように、文章を書いていく」(書評家、ライター あわい ゆき)
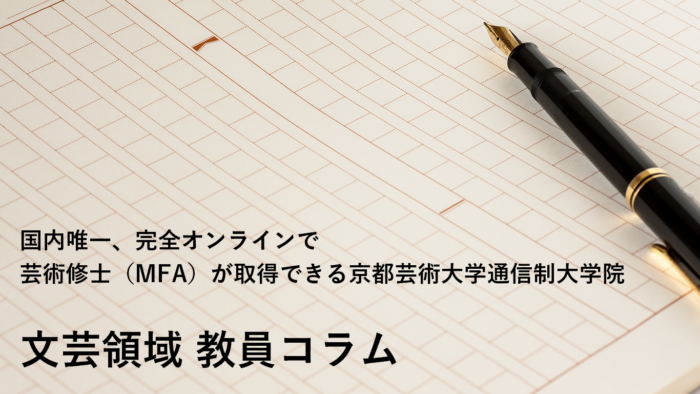
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は書評家、ライターのあわい・ゆきさんのコラムをご紹介します。

【あわい・ゆき】
2000年生まれ。書評家、ライター。
2022年に活動をはじめ、「小説現代」のほか、「文藝」「小説推理」「SFマガジン」「別冊文藝春秋」「産経新聞」「潮」などに寄稿。
主に国内最新の純文学、大衆文学、SF、ミステリ、ライトノベル、児童小説を中心に幅広く読み、noteにも記事を公開している。京都芸術大学通信制大学院文芸領域・非常勤講師。
「競馬を予想するように、文章を書いていく」
なぜ私は文章を書くのか——それを顧みたとき、幼いころから両親の影響でよく競馬場に行き、競馬が身近だったから、というのは、一見飛躍していそうで、最も腑に落ちる結論になります。私にとって文章を書くことと、競馬の予想をすることはとても似ているのです。いまもこうして文章を書きながら、紡がれる文字の真横で競走馬がターフを駆けているような気がします。この文章はどこへ向かうのだろう、ゴールしたときにどんな景色が待ち受けているのだろう——期待と不安をないまぜにしながら。
一般的に競馬は公営ギャンブルのひとつに位置付けられています。一着ないし二着三着までを的中させられれば、賭けた額と配当に応じた払い戻しがある。そして的中させるためには、予想する必要がある。応援している馬を買う、誕生日と同じ馬番号の馬を買う、といったものも立派な予想のひとつでしょう。
しかし、「予想」という行為を追求し、極めようとするためには相応の知識が必要になります。たとえば競走馬のコンディションを知るために馬体や調教を見極め、適性を知るために血統やコース形態、あるいは馬場傾向などを学ぶ。競走馬自体の能力を測るために走破タイムや走破ラップを研究する。そして馬券で最も効率よく勝つためにオッズと照らし合わせて買い方を試行錯誤する……。予想をするための手がかりは尽きません。
一方で、あらゆる手がかりがこうして存在していながら、これらすべてを網羅したうえで信頼し、予想を組み立てていくのは現実的に難しいところ。ポジティブなデータとネガティブなデータは常に衝突し、絶対的に信頼できる要素は存在しません。
そしてもうひとつ。これらすべてを完ぺきに知り尽くしたとして、自分で選んだ答えが正解とは限らないのです。数学やクイズと違い、競馬は百回行えば、百回違う結果になります。
つまり、競馬には「絶対」がない。「正解」がない。だから自分なりに予想をして正解に少しでも近づこうとする——そして、その努力がぴたりと当てはまった瞬間にこそ、私はこれ以上ない高揚感を覚えます。
そして、これと同じ、あるいはそれ以上の高揚感を覚えるのが文章を書いているときです。なぜなら、言葉を組み立てて他者への伝達を試みる「文章」という手段には——特に創作においては——正解など存在しないのですから。
まだ幼く馬券を買えなかった私は、競馬の予想をするかわりに、文章を書くことに夢中になりました。文章を書くときに欠かせない「表現」を追求するときの、無限通りのレパートリーに魅了されたのです。たとえば「うれしい」感情を取り出すだけでも、そのままストレートに伝えたり、凝らしたり、遠回しにしたり。細やかなニュアンスの違いで、意味合いはまったく異なってきます。小説の書き方も人それぞれで、マークシートを正しく記入するのと同程度のルールはあるにせよ、正しさを証明できるような正解はありません。
だからこそ、自分のなかにある感情を探すべく、あらゆる言葉を引き出しているとき、まるで私自身がターフを駆けているように自由な感覚でいっぱいになります。そして心と言葉がはじめて一致したとき、他の何をしていても得られないよろこびが、胸を満たすのは言うまでもありません。
文学の世界も競馬の世界も、いま「執筆」あるいは「予想」を担ってくれるAIが取り沙汰され、それでも人間の手で紡いでいくことの意味を問われていると感じます。そのたびに、私は思い出すのです。存在しない正解を求めてもがく試行錯誤のプロセスと、その果てに得られる高揚の素晴らしさを。そして、正解がないゆえに存在する、これ以上のよろこびを得られる可能性を。この文章もまだまだふさわしい正解があるのかもしれない、考え出したらキリのない可能性を感じつつ、私の文章に対する姿勢を明確に言葉にできた、正解に至れた実感を抱いています。
——————————————————
説明会情報
【2024年10月16日(水)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(1) 小説ゼミ編(第一部)
「普遍的な物語を書くために――物語の「技術」を学ぶ場――」
たとえ紙媒体が衰退し、本が読まれなくなっても、「物語」なるものは人類にとって普遍的な価値をもち、きっといつの時代にも、ひとびとのこころを惹きつける何かであり続けます。
“いつか自分の手で、自分にしか書けない「物語」を書いてみたい。けれど、何をどうすればよいのかわからない”。
こうした思いが、「自分にも書ける」という確信に変わる場が、この大学院文芸領域にはあります。「物語」創作の最前線について、そしてその明るい展望について、以下の登壇者がお伝えします。
登壇者一覧)
■小説ゼミ2(主としてエンタテインメント小説ジャンル)指導担当者
*松岡弘城(編集者)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*藍銅ツバメ(作家)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月7日(木)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)
「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」
この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。
しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。
気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。
登壇者一覧)
■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者
*池田雄一(文芸評論家)
*藤野可織(作家)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月20日(水)19:00~20:30】
芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編
「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」
ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。
エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。
登壇者一覧)
■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者
*田中尚史(編集者)
*野上千夏(編集者)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
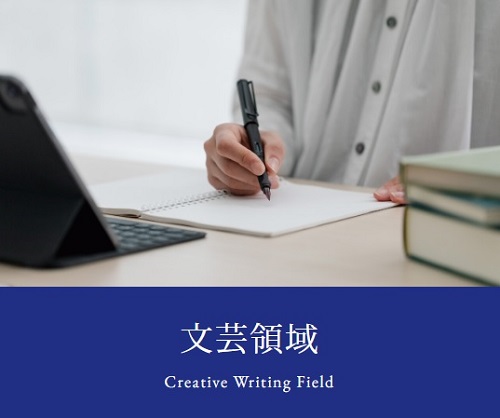
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事
-
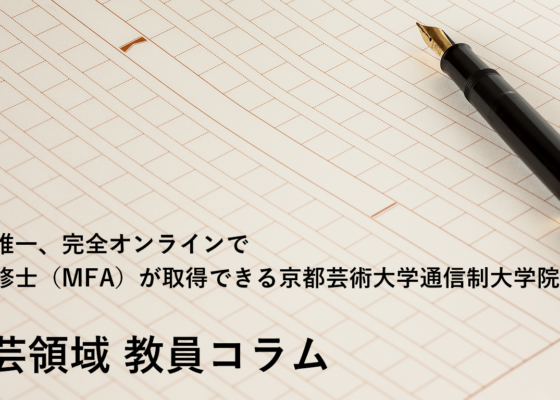
通信制大学院
2024年10月07日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「うそでありうそでなく、苦しくて楽しいほんとうの」(作家・編集者 岡 英里奈)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家、編集者の岡 英里奈さんのコラムをご紹介し…
- 記事がありませんでした
-
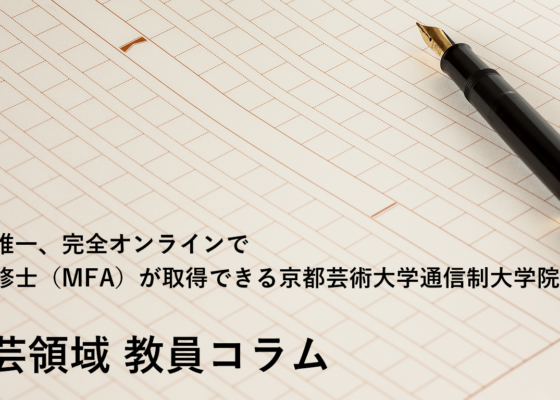
通信制大学院
2024年10月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「私が書いて私を知る」(作家 佐藤 述人)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家佐藤 述人さんのコラムをご紹介します。 【…






























