

芸術教養学科
- 芸術教養学科 記事一覧
- 【芸術教養学科】めがねを作る
2024年11月20日
【芸術教養学科】めがねを作る
 みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。
みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。2024年も残すところあと1ヶ月程となりました。それにしても月日が過ぎるのは早いですね。「光陰矢の如し」とか、「白駒の隙を過ぐるが如し」とか、「月日に関守なし」とか、「歳月人を待たず」とか、「烏兎怱怱」とか、いろいろな言葉がありますが、その一事だけをとってみても、昔の人もいまの我々と同様に「時が経つのは早い」と感じていたことが分かります。
この1年を振り返って、「自分には何ができたのだろうか」と考えてみると、愕然とせずにはいられません。「何もしてないのではないか?」といった焦りにも似た感情が、ふつふつと湧き上がってきます。ちなみに、これって私だけでしょうか。そんなことないですよね。おそらく同じように感じていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
年を重ねるたびに1年は短くなっていきます。19世紀フランスの哲学者ポール・ジャネーは、「主観的に記憶表象される年月の長さは、生活年齢に反比例して、年少者にはより長く、年長者では短く評価される」と主張しました。これを心理学用語で「ジャネーの法則」というそうですが、分母が増えれば、分子の比率はどんどん小さくなっていきますので、体感としての1年が短くなっていくのは、なんら不思議なことではありません。
とはいえ、本来、時間は同じ間隔で、同じように刻まれていきます。年齢によって長くなったり短くなったりすることはありません。それは、あくまでも人が感じている時間の問題ということになるわけですが、これが大問題! では、どうすれば、それをちょっとでも長くすることができるのでしょうか。
脳科学の知見によれば、認知的負荷が高ければ高いほど、人は時間を長く感じるといいます。認知的負荷とは、ある出来事に対して、それを「体験した」という認識を成立させるための認知的努力のことです。つまり、何か新しいことを始めれば、認知的負荷がかかり、人生は長く、そして豊かなものになっていくということです。いささか強引かも知れませんが、そういうことなんです!
ということで、私も何か新しいことを始めてみようと思い、めがねを作ってみました。めがねのビスポークというやつです。これまでもスーツやシャツを仕立ててもらうことはあったものの、めがねをオーダーするのは、はじめての経験でした。
まず、いろいろと話を聞かれます。これまでどういっためがねをかけてきたのか? いまのめがねの気に入っているところは? 今回はどのような目的でめがねを作ろうと思ったのか? などなど。次に、めがねのフレームのデザインを決めていきます。ボストン型やウェリントン型、ラウンド型といった多くの選択肢から1つを選ばなければなりません。しかも、それぞれの型でも多種多様なデザインがあり、どれにしたらよいのか、どの色にしたらよいのか、大いに迷ってしまいます。なんとかフレームが決定したところで、サンプルの作成。これにおよそ1ヶ月から1ヶ月半の時間がかかりました。
その後、仕上がってきたフレームにあわせて、ツル(テンプル)や智(ヨロイ)、丁番(ヒンジ)、ブリッジ、パッド(鼻あて)、クリングスなどの細かいデザインをひとつひとつ選んでいきます。ここでもそれぞれに多彩なオプションがあり、頭を悩ませることになりました。「これもええけどなあ、あれもええなあ」とグズグズしていて、なかなか決まりません。かくかくしかじかで、なんとかパーツを選び、こんどはレンズです(先は長い!)。レンズにもいろいろな種類がありますが、今回、私は動画教材やオンライン会議等で光やライトが反射しないように、ノンリフレクションコートのレンズにしてみました。さらに、ここから顔の大きさや形にあわせて、レンズの幅やレンズの高さ、ブリッジの幅、フロントの全長などを調節。最後に視力検査をして、この日は終了です。
そこからまた1ヶ月半から2ヶ月ほど経ち、ようやくめがねが出来上がったとの連絡がありました。店舗に足を運んでフィッティング、そして先セルやパッドなどを耳や鼻の形にあわせて微調整、そうして、やっとめがねの完成です。ここまでおよそ3ヶ月、待ちに待っためがねを持って、私は家に帰りました。
めがねを選んでいる時間は、とてもゆったりとした贅沢な時間でした。これが、認知的負荷がかかった状態ということでしょうか。しかもそれだけではありません。サンプルや出来上がり品が届くまでの時間も、なんだか心がワクワク、ウキウキして、充実した時間を過ごすことができました。めがねを作ってみるという、ただそれだけの行為ですが(それも実際に作ったのはめがね屋さんで、私は待っていただけなのですが)、そこで感じたのは、やはり新しいことには積極的にチャレンジしてみるべきだ、ということです。
このとりとめもない文章を読んでくださっている、そこのあなた。何か新しいことを始めてみようと思っているのであれば、京都芸術大学通信教育部の芸術教養学科なんて、いかがでしょうか。いささか唐突ですが、新しいことを始めてみたいという方に、これほどうってつけの場所はありません。デザインや芸術、伝統や文化など、さまざまな学問や教養を幅広く、そして深く、それでいて楽しく学ぶことができます。
詩人の辻征夫は、〈私〉とは「雑多で豊富な記憶の総体」であると書いています。その意味では、〈私〉にとって無駄な知識や経験というものは、ひとつもありません(もちろん、めがねを作るという行為も)。さまざまな記憶や体験、それが〈私〉を作り上げていくことになるのです。
あなたも、新しいことに積極的にチャレンジして、〈私〉をさらに拡張していくことで、より充実した時間を過ごしてみませんか。みなさんのその思いを実現すべく、芸術教養学科の門は広く開かれています。
芸術教養学科|学科・コース紹介

おすすめ記事
-
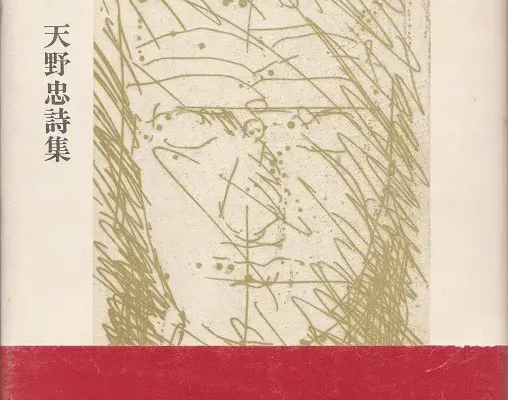
芸術教養学科
2024年06月20日
【芸術教養学科】正身のとこ
みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。 (『大改造‼️ 劇的ビフォーアフター』風に)なんということでしょう。ふと気がつけば、今年も半分が終わろうとしていま…
-

芸術教養学科
2024年02月21日
【芸術教養学科】芸術教養学科で学べること
みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。 突然ですが、みなさんはバナナの皮ですべって転んだことはありますか? 私は……、恥ずかしながら2回ほどあります! あ…
-

芸術教養学科
2023年09月28日
【芸術教養学科】瓜生山懇親会 在学生、卒業生、教職員をつなぎたい!
みなさん、こんにちは。芸術教養学科の宮です。残暑もいくぶん和らぎ、朝夕はしのぎやすい日も増えてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 夏休みを有意義に使われ…






























