

食文化デザインコース
- 食文化デザインコース 記事一覧
- 【食文化デザインコース】料理体験を通じてメッセージを伝える方法とは?
2025年02月19日
【食文化デザインコース】料理体験を通じてメッセージを伝える方法とは?
こんにちは。食文化デザイン研究室の中山晴奈です。
昨年末になりますが、コース専門教育科目「持続可能な食との関係」の担当教員であるニールセン北村朋子先生のミニゼミが団地キッチン「田島」 (埼玉県浦和市)で開催されました。団地キッチン「田島」は「食文化デザイン入門」でも登場する、食の地域コミュニティ施設です。
学生の皆さんに事前にお知らせしていたのは、このミニゼミは料理教室ではない、ということです。出来上がった料理を見ると、すべて盛り付けが違います。さて、どんな体験だったのでしょうか?
 ニールセン先生から当日渡されたのは、すべて英語で書かれた、写真のないレシピです。当日出会った学友で4人1組を作り、今日取り組む料理を伝えられます。
ニールセン先生から当日渡されたのは、すべて英語で書かれた、写真のないレシピです。当日出会った学友で4人1組を作り、今日取り組む料理を伝えられます。
「お渡ししたのはデンマークの一般的な家庭料理のレシピです。今から皆さんにはこの料理を作ってもらいます」
レシピに記されていたのは、以下の3品の工程です。
Jerusalem artichoke Soup
Danish Fish Cake
Danish Soft Apple Cake
どうでしょう、みなさんイメージできるでしょうか?
 戸惑いながら、まず自己紹介から始めたみなさん。
戸惑いながら、まず自己紹介から始めたみなさん。
早いチームは早々にレシピを一読し、材料確保に向かいました。
 慎重なチームは、すべてを翻訳してから進めたいということで、レシピの読み合わせに時間をかけました。
慎重なチームは、すべてを翻訳してから進めたいということで、レシピの読み合わせに時間をかけました。
 すごい熱気です!
すごい熱気です!
20人近くが一斉に料理をするには十分なスペース、調理器具が足りない状況で、グループを超えて道具を貸し借りしないと進められないことがだんだんとわかってきます。そして、2時間で料理を仕上げないといけません。
同じグループだとしても、共通するイメージを頭に描けないまま進みます。この難しさの中で、みなさん様々な困難をアイデアと経験で乗り越えていきました。
無事、出来上がった料理は、いずれもおいしく仕上がりましたが、グループごとに少し様子が違いました。デンマークの材料と日本の材料の違いなどもあり、魚のケーキに使う生地は少しゆるめに仕上がってしまいました。これによって、パンケーキのように焼いたチーム、スペイン風オムレツのように焼いたチームと、最後の盛り付けに差がでました。
また、英語の解読に差が出て、野菜がタルタルのようにカレー風味のソースに入っているチームと、ソテーした野菜とソースが分かれて盛り付けられたチームが出ました。
果たして、どれが正解だったのか…?!
ざわつくキッチンで、最後にニールセン先生がこの料理教室の狙いをお話ししてくださいました。
「このワークショップは、ゴールが見えない中、状況の異なる人たちが一つのものに取り組んでいくワークショップです。私はこれを民主主義を進めていく工程と同じだと考えています。デンマークは民主主義をとても大事にしている国です。多様な人たちが、一つの幸せや豊かさに向かって、一緒に物事を決め、取り組んでいくのは、今日みなさんが取り組んだ料理という作業と一緒です。」
料理を通じて、多様性、合意形成の難しさ、そしておもしろさを学んでいたというのです。食は、様々なメッセージを伝えることができる、というこの授業の意図に、一同驚きながら聞き入っていました。
 最後はおいしくいただき、改めて写真撮影をしました。
最後はおいしくいただき、改めて写真撮影をしました。
食、料理を通じて様々なことが発信できるということで、仕事にも役立ちそうだとおっしゃる方も多かったです。参加してくださった方はしっかりと盛りだくさんのメッセージを受け止めてくださいました。終了後もニールセン先生の周り、そして学生同士でも、話が盛り上がっていました。
ご参加いただいたみなさんありがとうございました。
そして、会場を使わせていただきました団地キッチン「田島」のみなさまもありがとうございました。
食文化デザインコース 特設ページ
食文化デザインコース 学生の声
食文化デザインコース Instagram
食文化デザインコース Facebook
食文化デザインコース| 学科・コース紹介

昨年末になりますが、コース専門教育科目「持続可能な食との関係」の担当教員であるニールセン北村朋子先生のミニゼミが団地キッチン「田島」 (埼玉県浦和市)で開催されました。団地キッチン「田島」は「食文化デザイン入門」でも登場する、食の地域コミュニティ施設です。
学生の皆さんに事前にお知らせしていたのは、このミニゼミは料理教室ではない、ということです。出来上がった料理を見ると、すべて盛り付けが違います。さて、どんな体験だったのでしょうか?
 ニールセン先生から当日渡されたのは、すべて英語で書かれた、写真のないレシピです。当日出会った学友で4人1組を作り、今日取り組む料理を伝えられます。
ニールセン先生から当日渡されたのは、すべて英語で書かれた、写真のないレシピです。当日出会った学友で4人1組を作り、今日取り組む料理を伝えられます。「お渡ししたのはデンマークの一般的な家庭料理のレシピです。今から皆さんにはこの料理を作ってもらいます」
レシピに記されていたのは、以下の3品の工程です。
Jerusalem artichoke Soup
Danish Fish Cake
Danish Soft Apple Cake
どうでしょう、みなさんイメージできるでしょうか?
 戸惑いながら、まず自己紹介から始めたみなさん。
戸惑いながら、まず自己紹介から始めたみなさん。早いチームは早々にレシピを一読し、材料確保に向かいました。
 慎重なチームは、すべてを翻訳してから進めたいということで、レシピの読み合わせに時間をかけました。
慎重なチームは、すべてを翻訳してから進めたいということで、レシピの読み合わせに時間をかけました。 すごい熱気です!
すごい熱気です!20人近くが一斉に料理をするには十分なスペース、調理器具が足りない状況で、グループを超えて道具を貸し借りしないと進められないことがだんだんとわかってきます。そして、2時間で料理を仕上げないといけません。
同じグループだとしても、共通するイメージを頭に描けないまま進みます。この難しさの中で、みなさん様々な困難をアイデアと経験で乗り越えていきました。
無事、出来上がった料理は、いずれもおいしく仕上がりましたが、グループごとに少し様子が違いました。デンマークの材料と日本の材料の違いなどもあり、魚のケーキに使う生地は少しゆるめに仕上がってしまいました。これによって、パンケーキのように焼いたチーム、スペイン風オムレツのように焼いたチームと、最後の盛り付けに差がでました。
また、英語の解読に差が出て、野菜がタルタルのようにカレー風味のソースに入っているチームと、ソテーした野菜とソースが分かれて盛り付けられたチームが出ました。
果たして、どれが正解だったのか…?!
ざわつくキッチンで、最後にニールセン先生がこの料理教室の狙いをお話ししてくださいました。
「このワークショップは、ゴールが見えない中、状況の異なる人たちが一つのものに取り組んでいくワークショップです。私はこれを民主主義を進めていく工程と同じだと考えています。デンマークは民主主義をとても大事にしている国です。多様な人たちが、一つの幸せや豊かさに向かって、一緒に物事を決め、取り組んでいくのは、今日みなさんが取り組んだ料理という作業と一緒です。」
料理を通じて、多様性、合意形成の難しさ、そしておもしろさを学んでいたというのです。食は、様々なメッセージを伝えることができる、というこの授業の意図に、一同驚きながら聞き入っていました。
 最後はおいしくいただき、改めて写真撮影をしました。
最後はおいしくいただき、改めて写真撮影をしました。食、料理を通じて様々なことが発信できるということで、仕事にも役立ちそうだとおっしゃる方も多かったです。参加してくださった方はしっかりと盛りだくさんのメッセージを受け止めてくださいました。終了後もニールセン先生の周り、そして学生同士でも、話が盛り上がっていました。
ご参加いただいたみなさんありがとうございました。
そして、会場を使わせていただきました団地キッチン「田島」のみなさまもありがとうございました。
食文化デザインコース 特設ページ
食文化デザインコース 学生の声
食文化デザインコース Instagram
食文化デザインコース Facebook
食文化デザインコース| 学科・コース紹介

おすすめ記事
-

食文化デザインコース
2024年11月24日
【食文化デザインコース】「南部せんべい」をテーマにしたフィールドワーク開催
食文化デザインコースの専任教員 中山晴奈です。 9月の2日間、藝術学舎(※)の授業として、地域編集講座「フィールドワークと商品開発」と題したフィールドワーク型の…
-

食文化デザインコース
2024年12月22日
【食文化デザインコース】オンライン料理教室も行ったミニゼミ
食文化デザインコース専任教員の宇城安都美です。 食文化デザインコースは完全オンラインの通信制大学ですが、動画による受講や課題提出の他に、ミニゼミや体験型イベント…
-
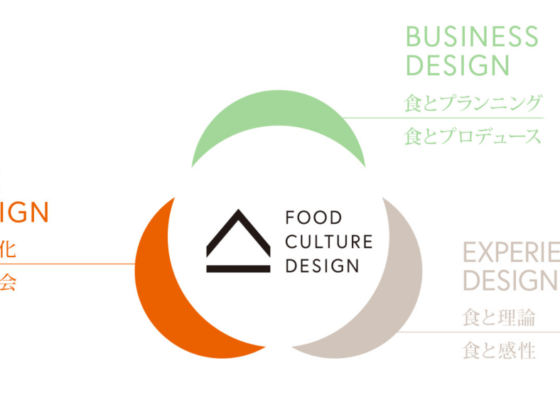
食文化デザインコース
2024年10月31日
【食文化デザインコース】カリキュラム紹介「文化・社会への洞察を磨く”ライフデザイン領域”」
こんにちは、食文化デザイン研究室の麻生桜子です。 食文化デザインコースのカリキュラムは、食を文化と捉え、幅広い知識と感性を磨きながら、人や社会を幸せにする企画力…






























