

グラフィックデザインコース
- グラフィックデザインコース 記事一覧
- 【グラフィックデザインコース】デザインを「体験」に変えるコーディングは奥深い〜品質向上のポイント〜
2025年10月21日
【グラフィックデザインコース】デザインを「体験」に変えるコーディングは奥深い〜品質向上のポイント〜
こんにちは。業務担当非常勤講師の花田です。
日中はまだ暖かいですが、朝晩は少し肌寒くなってきましたね。
前回は新カリキュラムのテキスト作品科目「グラフィックデザイン基礎2(デジタル&Web)」についてご紹介しました。
https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=124061
今回はそこから一歩進んで、実践にもつながる「コーディングの品質向上」をテーマにお話しします。
ウェブデザインでは、視覚的な画面の設計を行います。
それをコーディングすることで、静止していたデザインがブラウザ上で動き、触れて操作できるようになります。
その瞬間、デザインは「見るもの」から「体験するもの」へと変わります。
そのため、コーディングとはデザインを「体験」へと変換するプロセスであると私は考えます。
クリックした時のインタラクティブな動きやアニメーションの心地よさから始まり、支援技術を通じた情報伝達まで、デザインの裏側にあるユーザー体験は、緻密に計算されたコーディングによって支えられています。
だからこそ、コーディングは単にデザインをブラウザ上に再現する作業ではなく、「ユーザー体験をより良く磨く工程」であることを忘れてはいけません。
小さな工夫の積み重ねが、デザインの魅力をより確かに、広げていきます。
ここからは、制作現場でも意識される品質向上のポイントを見ていきましょう。

ウェブサイトを作る上で大切なのは、見た目のデザインだけではありません。
その土台となる文書構造が整っていることも重要な要素の一つです。
「セマンティックなHTML」とは、タグをコンテンツの意味に沿って正しくマークアップすることを指します。
たとえば、段落にはpタグ、ヘッダーにはheaderタグを使うなど、内容の役割に合ったタグを選ぶことがそれに当たります。
文法的に正しくマークアップすることで、検索エンジンやスクリーンリーダーなどにも文章の意味を正しく伝えることができます。
コーディングの際は、構造と意味の両方を意識したマークアップを心がけましょう。
チェックポイント:
・見出しの順序に抜けや飛びがないか
・セクションの区切りは適切か
・タグの閉じ忘れがないか など
便利なチェックツール:The Nu Html Checker
HTMLの仕様に沿って構文エラーを検出できます。練習作品を作ったら、このようなチェックツールで構文エラーがないかを確認してみましょう。

ウェブアクセシビリティとは、利用者の特性や環境に左右されず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できること、またその到達度を意味します。
たとえば、文字の視認性を高めたり、適切なaltを設定する、ボタンをタップしやすいサイズにするといった工夫は、アクセシビリティの向上につながります。
制作現場では、デザイン段階では可視化されていない部分を、コーディングで補い調整することが多くあります。そうした細やかな配慮が、誰にとっても快適なユーザー体験に繋がっていきます。
一般的に、ウェブサイトは表示スピードが遅いほど、離脱率が高まるといわれています。
サイトの表示速度は、ユーザー体験に直結する大切な要素です。
もしサイトが重いと感じるときは、パフォーマンス計測ツールを使って改善点を分析してみましょう。
便利なチェックツール: PageSpeed Insights、Lighthouse
サイトパフォーマンスのチェックツールを使うと、表示速度や最適化の改善ポイントを知ることができます。
作ったサイトはサーバーにアップし、実際の端末で操作してみるのもおすすめです。この段階で、思いがけない発見があるはずです。
たとえば、スマホで開いてみると、文字が小さすぎたり、ボタンが押しづらかったり。
また、ブラウザによって挙動が変わってしまうこともよくあります。
ユーザー視点で実際にサイトに触れながら、操作感を体験してみましょう。
その中で気づいた小さな違和感を調整していくことで、より良い体験に改善することができます。
いかがでしたでしょうか。
テキスト作品科目「グラフィックデザイン基礎2(デジタル&Web)」から少し発展した内容となりましたが、コーディングの奥深さを感じていただけたと思います。
ウェブサイトの仕組みや構造にも目を向け、様々な工夫を積み重ねることで、より多くの人に届くデザインへ飛躍させていきましょう。
グラフィックデザインコースでは、様々な表現方法、ジャンルの課題制作に取り組みます。授業の課題では、幅広い分野で活躍する経験豊富な講師に相談したり、アドバイスを貰う機会もあります。
興味を持たれた方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください!
グラフィックデザインコース|学科・コース紹介
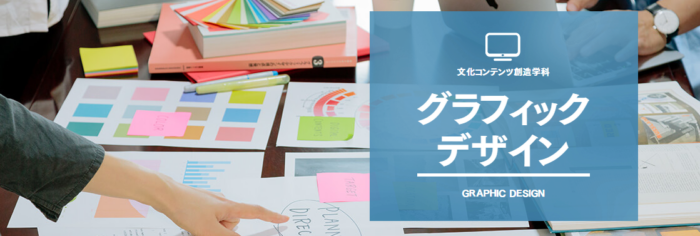 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから

日中はまだ暖かいですが、朝晩は少し肌寒くなってきましたね。
前回は新カリキュラムのテキスト作品科目「グラフィックデザイン基礎2(デジタル&Web)」についてご紹介しました。
https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=124061
今回はそこから一歩進んで、実践にもつながる「コーディングの品質向上」をテーマにお話しします。
コーディングとは、デザインを「体験」へと変換すること
ウェブデザインでは、視覚的な画面の設計を行います。
それをコーディングすることで、静止していたデザインがブラウザ上で動き、触れて操作できるようになります。
その瞬間、デザインは「見るもの」から「体験するもの」へと変わります。
そのため、コーディングとはデザインを「体験」へと変換するプロセスであると私は考えます。
クリックした時のインタラクティブな動きやアニメーションの心地よさから始まり、支援技術を通じた情報伝達まで、デザインの裏側にあるユーザー体験は、緻密に計算されたコーディングによって支えられています。
だからこそ、コーディングは単にデザインをブラウザ上に再現する作業ではなく、「ユーザー体験をより良く磨く工程」であることを忘れてはいけません。
小さな工夫の積み重ねが、デザインの魅力をより確かに、広げていきます。
ここからは、制作現場でも意識される品質向上のポイントを見ていきましょう。

1.セマンティックなHTML構造を意識する
ウェブサイトを作る上で大切なのは、見た目のデザインだけではありません。
その土台となる文書構造が整っていることも重要な要素の一つです。
「セマンティックなHTML」とは、タグをコンテンツの意味に沿って正しくマークアップすることを指します。
たとえば、段落にはpタグ、ヘッダーにはheaderタグを使うなど、内容の役割に合ったタグを選ぶことがそれに当たります。
文法的に正しくマークアップすることで、検索エンジンやスクリーンリーダーなどにも文章の意味を正しく伝えることができます。
コーディングの際は、構造と意味の両方を意識したマークアップを心がけましょう。
チェックポイント:
・見出しの順序に抜けや飛びがないか
・セクションの区切りは適切か
・タグの閉じ忘れがないか など
便利なチェックツール:The Nu Html Checker
HTMLの仕様に沿って構文エラーを検出できます。練習作品を作ったら、このようなチェックツールで構文エラーがないかを確認してみましょう。

2.ウェブアクセシビリティを改善する
ウェブアクセシビリティとは、利用者の特性や環境に左右されず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できること、またその到達度を意味します。
たとえば、文字の視認性を高めたり、適切なaltを設定する、ボタンをタップしやすいサイズにするといった工夫は、アクセシビリティの向上につながります。
制作現場では、デザイン段階では可視化されていない部分を、コーディングで補い調整することが多くあります。そうした細やかな配慮が、誰にとっても快適なユーザー体験に繋がっていきます。
3.サイトパフォーマンスを高める
一般的に、ウェブサイトは表示スピードが遅いほど、離脱率が高まるといわれています。
サイトの表示速度は、ユーザー体験に直結する大切な要素です。
もしサイトが重いと感じるときは、パフォーマンス計測ツールを使って改善点を分析してみましょう。
便利なチェックツール: PageSpeed Insights、Lighthouse
サイトパフォーマンスのチェックツールを使うと、表示速度や最適化の改善ポイントを知ることができます。
4.実機で検証する
作ったサイトはサーバーにアップし、実際の端末で操作してみるのもおすすめです。この段階で、思いがけない発見があるはずです。
たとえば、スマホで開いてみると、文字が小さすぎたり、ボタンが押しづらかったり。
また、ブラウザによって挙動が変わってしまうこともよくあります。
ユーザー視点で実際にサイトに触れながら、操作感を体験してみましょう。
その中で気づいた小さな違和感を調整していくことで、より良い体験に改善することができます。
いかがでしたでしょうか。
テキスト作品科目「グラフィックデザイン基礎2(デジタル&Web)」から少し発展した内容となりましたが、コーディングの奥深さを感じていただけたと思います。
ウェブサイトの仕組みや構造にも目を向け、様々な工夫を積み重ねることで、より多くの人に届くデザインへ飛躍させていきましょう。
グラフィックデザインコースでは、様々な表現方法、ジャンルの課題制作に取り組みます。授業の課題では、幅広い分野で活躍する経験豊富な講師に相談したり、アドバイスを貰う機会もあります。
興味を持たれた方は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください!
グラフィックデザインコース|学科・コース紹介
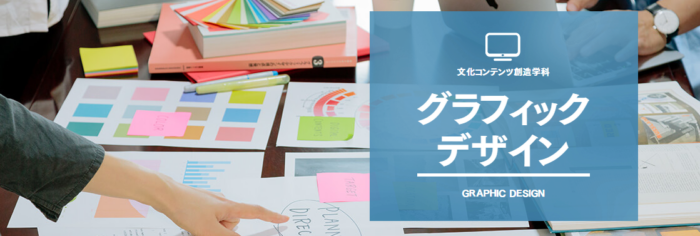 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
おすすめ記事
-

グラフィックデザインコース
2024年09月17日
【グラフィックデザインコース】コーディングの基礎を学び、デザインの質を高めよう。
こんにちは。業務担当非常勤講師の花田です。 まだまだ暑い日が続いていますね。今年の夏は猛暑のため、皆さん、お家で過ごす時間も多かったのではないでしょうか。 さて…
-

グラフィックデザインコース
2025年01月11日
【グラフィックデザインコース】コーディング初心者がつまづきやすいポイントを知っておこう
こんにちは。業務担当非常勤講師の花田です。 グラフィックデザインコースでは、ウェブ制作に関する科目がいくつかあります。 コース紹介ぺージ(大学公式HP) ウェブ…
-

グラフィックデザインコース
2025年06月17日
【グラフィックデザインコース】グラフィックだけじゃない。新カリキュラムで唯一のコーディングを学ぼう!
みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の花田です。 新年度がスタートして、早いものでもう6月。 改めて自己紹介しますと、私は普段、ウェブ制作の仕事をしており、…






























