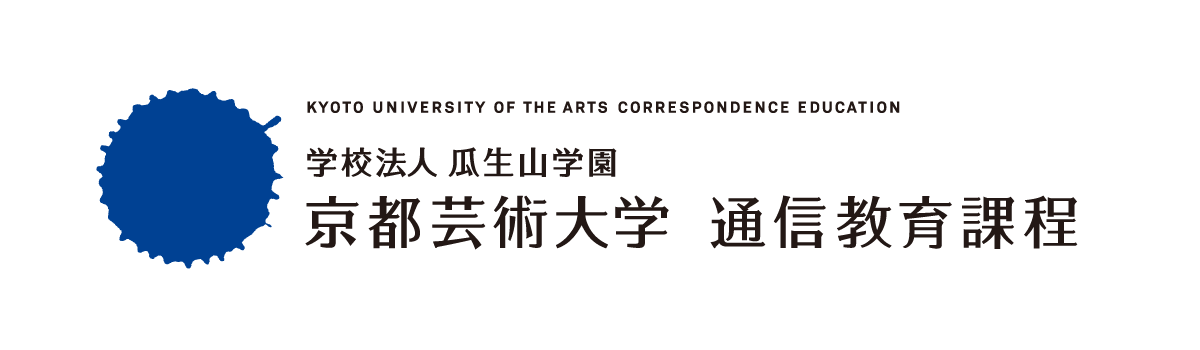芸術学コース
- 芸術学コース 記事一覧
- 【芸術学コース】作品の「価値」
2020年02月14日
【芸術学コース】作品の「価値」
立春も過ぎ、暦のうえではもう春ですね。梅の蕾も綻んできたものの、ここにきて寒さが増してまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
 今回の記事は、芸術学コースの佐藤が担当いたします。私は古代ギリシアの思想を専門としていますが、悲しいかな、この分野はあまり需要がないためか、諸大学から依頼される授業は芸術や文化をテーマに掲げたものがほとんどです。そのような授業の中でしばしば寄せられる質問のひとつに、作品が芸術であると認められたり美術館に展示される基準とはなんですか、というものがあります。つまり、作品の「価値」をめぐる問いです。
今回の記事は、芸術学コースの佐藤が担当いたします。私は古代ギリシアの思想を専門としていますが、悲しいかな、この分野はあまり需要がないためか、諸大学から依頼される授業は芸術や文化をテーマに掲げたものがほとんどです。そのような授業の中でしばしば寄せられる質問のひとつに、作品が芸術であると認められたり美術館に展示される基準とはなんですか、というものがあります。つまり、作品の「価値」をめぐる問いです。
これはなかなか難しい問題で、正直なところ私はいつも答えに窮しつつ、なんとか尤もらしい返答を捻りだしてお茶を濁しております。歴史的・文化的な意義や稀少性、はたまた斬新さや「独創性」、制作者の知名度や権威、来歴等々、作品の価値を判断する要素はもちろん多様で複雑なものであり、その評価も当然のことながら時代や場所によって異なるでしょう。
あるいは、このような公の評価とは別に、ある作品が個人の思い出や思い入れと深く結び付いていたり、何故かは分からないけれども感性に強く訴えかけるなど、特定の個人にとってはかけがえのないものだというケースもあります。
むろん、これら公の評価と私的な評価とを一緒くたにすることはできませんが、いずれの場合も、卓越した技巧や素材の稀少性などといった作品そのものの物理的な価値のみならず(あるいはそれ以上に)、作品の「余白」とでもいうべきものもまた、作品の「価値」を左右する重要な一要素なのではないかと思います。
とまあ、このようなことを意識させられる機会がつい最近もありました。それは、現在公開中の映画『CATS』ならびにこの作品をめぐる一連の批評に接したことです。この作品は私の研究分野とは縁遠いものですし、いわゆる芸術として語られる対象でもないかもしれません。しかしながら、たまたま鑑賞したこの作品自体、ならびにその評価にも、思いのほか興味深い「余白」があるように感じました。そのようなわけで、以下、映画『CATS』の「余白」について、門外漢の立場から少しばかり雑感を述べさせていただきます。
 いうまでもなくこの作品は、ミュージカルの金字塔と称される人気作『CATS』を映画化したものです(いずれも原作はT. S. エリオットの詩)。上の写真は昨年12月のニューヨークの街角ですが、映画会社がその年の一本としてクリスマスシーズンに公開する目玉作品として、ユニバーサル社が当て込んできたのが他でもない『CATS』でした。たしかに、舞台ですでにヒットしている作品を下敷きに、キャスト・スタッフともに一流の陣営を配し、満を持しての映画化。
いうまでもなくこの作品は、ミュージカルの金字塔と称される人気作『CATS』を映画化したものです(いずれも原作はT. S. エリオットの詩)。上の写真は昨年12月のニューヨークの街角ですが、映画会社がその年の一本としてクリスマスシーズンに公開する目玉作品として、ユニバーサル社が当て込んできたのが他でもない『CATS』でした。たしかに、舞台ですでにヒットしている作品を下敷きに、キャスト・スタッフともに一流の陣営を配し、満を持しての映画化。
しかし、じつは昨夏に予告編が流れて以来、この作品に対する酷評が吹き荒れており、結局その印象を払拭できぬまま、米国や英国での年末の公開時には当初の目論見とは裏腹に大赤字を抱える結果となってしまいました。この経緯は、日本でも新聞記事やネットニュースなどで取り上げられていたので、ご存知の方も多いことでしょう。
本邦でも、公開前からそれら激烈に批判的な海外評が取り沙汰され、主にネットを中心に、本編を観てもいないうちから作品を面白おかしく揶揄し、こき下ろすという珍妙な事態が生じました。批判の矛先の多くはまず、ヴィジュアル面に向けられました。予告編を観た人々のあいだで、出演者の猫人間とも人間猫ともつかないヌメっとした容姿が卑猥で不気味だという声が噴出したのです。この映画では、映像に後から編集作業で毛を付け加えるという手法が採られたそうですが、最新の映像技術を駆使したことがかえって仇となったかのような酷評ぶり。
しかし実際に鑑賞してみたところ、個人的には、この体毛の少ない全身タイツ風の容貌にはさして違和感を覚えず、むしろこのような「衣裳」に代わる良策が思いつかないくらいでした。本物の猫を使う、あるいはアニメにするという代案を提唱する声もあるようですが、この作品の要である歌と踊りの魅力を存分に伝えるには、やはり躍動する生身の人間の身体と表情が必要だったでしょう。この「人間のDNAを残す」というこだわりにかんしては、監督のトム・フーパーがインタビューで語っているとおりです。
それでもなお、このヴィジュアルやキャラクター造形に拒否反応を示す人々がかなり存在することは確かです。感性は人それぞれなので正解も不正解もありませんが、ともあれ、この作品に不快感を抱く人が多いという現象そのものが、私にとっては興味深く感じられます。というのも、ここに再現表象をめぐる問題の一端が垣間見えるような気がするからです。
 ©UNIVERSAL STUDIOS
©UNIVERSAL STUDIOS
そのひとつは、類似性の問題です。先述のとおり、映画『CATS』では最先端の技術を用い、動きのある毛や髭、耳や尻尾をCGで加えるなどの意匠が凝らされています。しかしながら、それは必ずしも功を奏しているとは言い難いようです。本物に近づけようとすればするほど、リアリティを追求すればするほど、かえって偽物くさく見えてしまう。すなわち、何かに似せようとすればするほど、皮肉にも差異が目立ってしまうという、類似性をめぐるパラドクスとでも申しましょうか。
この逆説は、程度の差はあれ、再現表象なるものが宿命的に背負っているものかもしれません。たとえば肖像などの似姿が、代替物として機能する一方で/それゆえにモデルの不在を際立たせてしまうという点は、アリストテレスはじめ古来より指摘されているとおりです。
また、卑近な例ではありますが、最近は表情を変える遺影というものが開発されているそうです。一般的に、遺影は写真の形態をとりますが、この新しい遺影では、映像技術を用いて目元や口元を動かすことで、故人がまるで生きているかのように表情を変えるのだとか。以前この遺影がテレビ番組で取り上げられた際、滑稽だ、違和感がある、といった大方の反応が紹介されていました(遺族はまた違った反応を見せてはいましたが)。
少々脱線しましたが、『CATS』に話を戻しましょう。先の類似性のパラドクスとも関連しますが、この作品を「不気味」と感じる別の要素のひとつとして、観者と対象との「近さ」も少なからず関連があるように思われます。つまり、作品中の猫の造形が限りなく人間の姿に近いものであることが、親近感どころかむしろ不気味さを感じさせる遠因となっているのです。反対に、いかに奇妙な容貌であっても自分と縁のないまったくの他者であれば、それを客観的に眼差すことができるのではないでしょうか。この点に関しては、ネット記事などでもすでに『CATS』における「不気味の谷現象」として指摘されており、人間の姿に似せたロボットの不気味さなどが引き合いに出されています。あるいはまた、猫人間/人間猫に対するこの違和感は、「不気味なもの(Das Unheimliche)」とは自らに馴染みのものに起因する、との精神科医フロイトの指摘とも共鳴するかもしれません。
ところで、封切り前からこうした「不気味さ」を強調する批評が蔓延していたにも関わらず、公開を迎えるや日本では先行上映していた英米とは異なる反応が見られたことは注目に値します。相変わらずわが国でも酷評が散見されるものの、外国に比べると明らかに高評価が多いようです。日本での動員数や興行収入も、懸念されていた割には好調な様子。
諸外国ではヒットしなかったものが日本では人気が出るなど(あるいはその逆も)、特異な受容の例は、これまでにも映画や芸術作品のみならず哲学の分野などでもしばしば見受けられましたし、先行する酷評によって予め「免疫」が出来ていた可能性もあり、期待値を下げて、または怖いもの見たさで劇場を訪れた人もいるでしょう。それに判官贔屓めいたものも多少はあったかもしれません。しかしいずれにせよ、新奇なものに接した際の人々の反応が日本では比較的寛容であったことに、私は何か救いのようなものを感じます。
奇しくも、映画『CATS』で描かれていた重要なテーマのひとつは、異質なものをいかに認めるかということです。作中、共同体から排除されてきたアウトローな猫が再びコミュニティに受け入れられる仲介役を担ったのは、よそからやって来た新参者の白猫でした。舞台版では端役に過ぎないこのよそ者の捨て猫を主要な役に据えたのはまさしく今回の映画化の新機軸であり、それだけになおさら、この映画で多様性や寛容さといったメッセージが強く打ち出されているように思われます。
いまだ賛否両論が吹き荒れている映画『CATS』ですが、できるだけ先入観を排して作品と対峙する重要性を再認識するという意味でも、さまざまな「余白」が提示されているという意味でも、傑作とまではいかずともなかなか奥深い作品と言えるのではないでしょうか。なにはともあれ、この作品に限らず、批評を鵜呑みにして作品に接する機会すら逸してしまうというのはあまりに勿体ないことです。翻って、私は、冒頭に述べた作品の「価値」をめぐる問いを考えるサンプルという口実で、専門の研究とは別に趣味として、いましばらくこの作品の評価の推移を観察してみようと目論んでいる次第です。作中の楽曲が頭から離れないのが目下の悩みではありますが…これもまた楽しいものです。
芸術学コース|学科・コース紹介

 今回の記事は、芸術学コースの佐藤が担当いたします。私は古代ギリシアの思想を専門としていますが、悲しいかな、この分野はあまり需要がないためか、諸大学から依頼される授業は芸術や文化をテーマに掲げたものがほとんどです。そのような授業の中でしばしば寄せられる質問のひとつに、作品が芸術であると認められたり美術館に展示される基準とはなんですか、というものがあります。つまり、作品の「価値」をめぐる問いです。
今回の記事は、芸術学コースの佐藤が担当いたします。私は古代ギリシアの思想を専門としていますが、悲しいかな、この分野はあまり需要がないためか、諸大学から依頼される授業は芸術や文化をテーマに掲げたものがほとんどです。そのような授業の中でしばしば寄せられる質問のひとつに、作品が芸術であると認められたり美術館に展示される基準とはなんですか、というものがあります。つまり、作品の「価値」をめぐる問いです。これはなかなか難しい問題で、正直なところ私はいつも答えに窮しつつ、なんとか尤もらしい返答を捻りだしてお茶を濁しております。歴史的・文化的な意義や稀少性、はたまた斬新さや「独創性」、制作者の知名度や権威、来歴等々、作品の価値を判断する要素はもちろん多様で複雑なものであり、その評価も当然のことながら時代や場所によって異なるでしょう。
あるいは、このような公の評価とは別に、ある作品が個人の思い出や思い入れと深く結び付いていたり、何故かは分からないけれども感性に強く訴えかけるなど、特定の個人にとってはかけがえのないものだというケースもあります。
むろん、これら公の評価と私的な評価とを一緒くたにすることはできませんが、いずれの場合も、卓越した技巧や素材の稀少性などといった作品そのものの物理的な価値のみならず(あるいはそれ以上に)、作品の「余白」とでもいうべきものもまた、作品の「価値」を左右する重要な一要素なのではないかと思います。
とまあ、このようなことを意識させられる機会がつい最近もありました。それは、現在公開中の映画『CATS』ならびにこの作品をめぐる一連の批評に接したことです。この作品は私の研究分野とは縁遠いものですし、いわゆる芸術として語られる対象でもないかもしれません。しかしながら、たまたま鑑賞したこの作品自体、ならびにその評価にも、思いのほか興味深い「余白」があるように感じました。そのようなわけで、以下、映画『CATS』の「余白」について、門外漢の立場から少しばかり雑感を述べさせていただきます。
 いうまでもなくこの作品は、ミュージカルの金字塔と称される人気作『CATS』を映画化したものです(いずれも原作はT. S. エリオットの詩)。上の写真は昨年12月のニューヨークの街角ですが、映画会社がその年の一本としてクリスマスシーズンに公開する目玉作品として、ユニバーサル社が当て込んできたのが他でもない『CATS』でした。たしかに、舞台ですでにヒットしている作品を下敷きに、キャスト・スタッフともに一流の陣営を配し、満を持しての映画化。
いうまでもなくこの作品は、ミュージカルの金字塔と称される人気作『CATS』を映画化したものです(いずれも原作はT. S. エリオットの詩)。上の写真は昨年12月のニューヨークの街角ですが、映画会社がその年の一本としてクリスマスシーズンに公開する目玉作品として、ユニバーサル社が当て込んできたのが他でもない『CATS』でした。たしかに、舞台ですでにヒットしている作品を下敷きに、キャスト・スタッフともに一流の陣営を配し、満を持しての映画化。しかし、じつは昨夏に予告編が流れて以来、この作品に対する酷評が吹き荒れており、結局その印象を払拭できぬまま、米国や英国での年末の公開時には当初の目論見とは裏腹に大赤字を抱える結果となってしまいました。この経緯は、日本でも新聞記事やネットニュースなどで取り上げられていたので、ご存知の方も多いことでしょう。
本邦でも、公開前からそれら激烈に批判的な海外評が取り沙汰され、主にネットを中心に、本編を観てもいないうちから作品を面白おかしく揶揄し、こき下ろすという珍妙な事態が生じました。批判の矛先の多くはまず、ヴィジュアル面に向けられました。予告編を観た人々のあいだで、出演者の猫人間とも人間猫ともつかないヌメっとした容姿が卑猥で不気味だという声が噴出したのです。この映画では、映像に後から編集作業で毛を付け加えるという手法が採られたそうですが、最新の映像技術を駆使したことがかえって仇となったかのような酷評ぶり。
しかし実際に鑑賞してみたところ、個人的には、この体毛の少ない全身タイツ風の容貌にはさして違和感を覚えず、むしろこのような「衣裳」に代わる良策が思いつかないくらいでした。本物の猫を使う、あるいはアニメにするという代案を提唱する声もあるようですが、この作品の要である歌と踊りの魅力を存分に伝えるには、やはり躍動する生身の人間の身体と表情が必要だったでしょう。この「人間のDNAを残す」というこだわりにかんしては、監督のトム・フーパーがインタビューで語っているとおりです。
それでもなお、このヴィジュアルやキャラクター造形に拒否反応を示す人々がかなり存在することは確かです。感性は人それぞれなので正解も不正解もありませんが、ともあれ、この作品に不快感を抱く人が多いという現象そのものが、私にとっては興味深く感じられます。というのも、ここに再現表象をめぐる問題の一端が垣間見えるような気がするからです。
 ©UNIVERSAL STUDIOS
©UNIVERSAL STUDIOSそのひとつは、類似性の問題です。先述のとおり、映画『CATS』では最先端の技術を用い、動きのある毛や髭、耳や尻尾をCGで加えるなどの意匠が凝らされています。しかしながら、それは必ずしも功を奏しているとは言い難いようです。本物に近づけようとすればするほど、リアリティを追求すればするほど、かえって偽物くさく見えてしまう。すなわち、何かに似せようとすればするほど、皮肉にも差異が目立ってしまうという、類似性をめぐるパラドクスとでも申しましょうか。
この逆説は、程度の差はあれ、再現表象なるものが宿命的に背負っているものかもしれません。たとえば肖像などの似姿が、代替物として機能する一方で/それゆえにモデルの不在を際立たせてしまうという点は、アリストテレスはじめ古来より指摘されているとおりです。
また、卑近な例ではありますが、最近は表情を変える遺影というものが開発されているそうです。一般的に、遺影は写真の形態をとりますが、この新しい遺影では、映像技術を用いて目元や口元を動かすことで、故人がまるで生きているかのように表情を変えるのだとか。以前この遺影がテレビ番組で取り上げられた際、滑稽だ、違和感がある、といった大方の反応が紹介されていました(遺族はまた違った反応を見せてはいましたが)。
少々脱線しましたが、『CATS』に話を戻しましょう。先の類似性のパラドクスとも関連しますが、この作品を「不気味」と感じる別の要素のひとつとして、観者と対象との「近さ」も少なからず関連があるように思われます。つまり、作品中の猫の造形が限りなく人間の姿に近いものであることが、親近感どころかむしろ不気味さを感じさせる遠因となっているのです。反対に、いかに奇妙な容貌であっても自分と縁のないまったくの他者であれば、それを客観的に眼差すことができるのではないでしょうか。この点に関しては、ネット記事などでもすでに『CATS』における「不気味の谷現象」として指摘されており、人間の姿に似せたロボットの不気味さなどが引き合いに出されています。あるいはまた、猫人間/人間猫に対するこの違和感は、「不気味なもの(Das Unheimliche)」とは自らに馴染みのものに起因する、との精神科医フロイトの指摘とも共鳴するかもしれません。
ところで、封切り前からこうした「不気味さ」を強調する批評が蔓延していたにも関わらず、公開を迎えるや日本では先行上映していた英米とは異なる反応が見られたことは注目に値します。相変わらずわが国でも酷評が散見されるものの、外国に比べると明らかに高評価が多いようです。日本での動員数や興行収入も、懸念されていた割には好調な様子。
諸外国ではヒットしなかったものが日本では人気が出るなど(あるいはその逆も)、特異な受容の例は、これまでにも映画や芸術作品のみならず哲学の分野などでもしばしば見受けられましたし、先行する酷評によって予め「免疫」が出来ていた可能性もあり、期待値を下げて、または怖いもの見たさで劇場を訪れた人もいるでしょう。それに判官贔屓めいたものも多少はあったかもしれません。しかしいずれにせよ、新奇なものに接した際の人々の反応が日本では比較的寛容であったことに、私は何か救いのようなものを感じます。
奇しくも、映画『CATS』で描かれていた重要なテーマのひとつは、異質なものをいかに認めるかということです。作中、共同体から排除されてきたアウトローな猫が再びコミュニティに受け入れられる仲介役を担ったのは、よそからやって来た新参者の白猫でした。舞台版では端役に過ぎないこのよそ者の捨て猫を主要な役に据えたのはまさしく今回の映画化の新機軸であり、それだけになおさら、この映画で多様性や寛容さといったメッセージが強く打ち出されているように思われます。
いまだ賛否両論が吹き荒れている映画『CATS』ですが、できるだけ先入観を排して作品と対峙する重要性を再認識するという意味でも、さまざまな「余白」が提示されているという意味でも、傑作とまではいかずともなかなか奥深い作品と言えるのではないでしょうか。なにはともあれ、この作品に限らず、批評を鵜呑みにして作品に接する機会すら逸してしまうというのはあまりに勿体ないことです。翻って、私は、冒頭に述べた作品の「価値」をめぐる問いを考えるサンプルという口実で、専門の研究とは別に趣味として、いましばらくこの作品の評価の推移を観察してみようと目論んでいる次第です。作中の楽曲が頭から離れないのが目下の悩みではありますが…これもまた楽しいものです。
芸術学コース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

芸術学コース
2018年05月31日
【芸術学コース】作品の制作年と作品解釈について―横山大観筆《柳蔭》をめぐって
みなさん、こんにちは。芸術学コースの三上です。今回は横山大観作《柳蔭》(図1)を例に、作品の制作年と作品解釈の関係について考えてみたいと思います。 今年は日本画…
-

芸術学コース
2022年11月13日
【芸術学コース】「技」と「芸術」――近代以前の作品を考えるにあたって
皆様、ごきげんよう。芸術学コースの佐藤です。早いもので今年も残すところあとひと月。京都の紅葉も徐々に色づき始めています。この時期、以前私が留学していたイタリア…
-

芸術学コース
2023年11月06日
【芸術学コース】芸術学 vs コスパ/タイパ——芸術学は「役に立つ」?
こんにちは。芸術学コース教員の江本です。 突然ですが、みなさんは複数の選択肢の中から1つを選ぶ際、どのような基準で選択されますか?じっくり考えた上で決定…