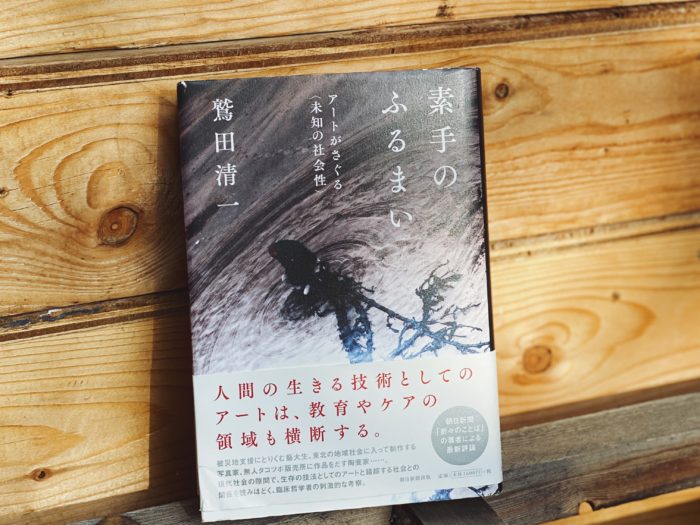写真コース
- 写真コース 記事一覧
- 【写真コース】アザーズポートレイトについて
2020年07月20日
【写真コース】アザーズポートレイトについて
こんにちは。写真コース教員の堀井ヒロツグです。
本当に長い梅雨が続いている中、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
Zoomによる遠隔授業も定着してきましたが、新しい形式に応じたコミュニケーションの作法に慣れようとする一方で、休み時間のような余剰の時間の中から生まれる会話の「よさ」を思い出したりもしています。
さて、今回の記事では、いつものスクーリング紹介とは別に、テキスト課題についてのお話をしようと思います。
通信教育部には、大学に赴いて受講するスクーリング(現在は遠隔スクーリング)の他に、自宅で取り組む作品課題があります。「写真日記」「フォトコラージュ」「テーマ制作」などたくさんの科目があるのですが、その中でも私が添削を担当している「アザーズポートレイト」についてです。
「アザーズポートレート」は、その名の通り他者のポートレートによる作品制作に取り組んでいただくものです。ところが今般の事情により、外出そのものを控えたいというご相談を受けることが多くなりました。その上、被写体となる方のご協力が必要なため、簡単には事が進まないかもしれません。そんな状況でそもそも撮影などできるのでしょうか。確かにその気持ちには同意できますし、そして無理にご自身の行動半径を広げる必要はないと思っています。
ただ、そういった「制約」は制作においてむしろ「条件」という捉え方の変化ができるものでもありますし、日常で見過ごしていた違和感に気づくきっかけになることもあります。他者が撮れないのなら、毎日「連続しているかのような」自分を他者に見立て撮影することもできるでしょう。あるいは、人間でないものに他者性を見出す眼差しがあってもいいと思います。また、日常的に着用することが暗黙の了解となったマスクを外す場面の線引きからは、無意識に分け隔てている境界が見えてもきます。実は、写真家は必ずしも動き続けなくても、作品を提示しそこから思考することはできるのです。
その際、一方的に入ってきた情報に立ち止まり、自分自身の中で整理・最適化していくことも必要かと思います。言葉には大きく2種類あって、ひとつは政治やメディアの世界から「降って」くる言葉。そしてもうひとつは日常の身体から「湧いて」くる言葉です。前者は誰かの意図をいつのまにか内面化し引き継いでしまうことがありますが、後者は自分で選択したものを使うことができます。
社会を循環するそれらの言葉は、やがて構造や風潮を作り出してしまうからこそ、まずは自分自身に聞き耳を立てるようなところから顕れる湧水のような言葉に価値を思います。ここ数ヶ月のあいだ、降ってきた言葉が溢れ、それに飲み込まれるような生活があったからこそ、みなさんの個人的な眼差しからやってくる作品について、楽しみにしています。
少し長くなってしまいましたが、くれぐれも無理はせず、しかしもし足踏みをされているようなことがあれば視点を変えて、状況がもたらした再考の機会をうまく利用されてみてください。教員は、そこから次の一歩に繋がり作品の芽が育っていくための、みなさん自身を映す「鏡の役割」ができればと思っています。また添削やスクーリングでお目にかかれることを楽しみにしています。
写真コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら
本当に長い梅雨が続いている中、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
Zoomによる遠隔授業も定着してきましたが、新しい形式に応じたコミュニケーションの作法に慣れようとする一方で、休み時間のような余剰の時間の中から生まれる会話の「よさ」を思い出したりもしています。
さて、今回の記事では、いつものスクーリング紹介とは別に、テキスト課題についてのお話をしようと思います。
通信教育部には、大学に赴いて受講するスクーリング(現在は遠隔スクーリング)の他に、自宅で取り組む作品課題があります。「写真日記」「フォトコラージュ」「テーマ制作」などたくさんの科目があるのですが、その中でも私が添削を担当している「アザーズポートレイト」についてです。
「アザーズポートレート」は、その名の通り他者のポートレートによる作品制作に取り組んでいただくものです。ところが今般の事情により、外出そのものを控えたいというご相談を受けることが多くなりました。その上、被写体となる方のご協力が必要なため、簡単には事が進まないかもしれません。そんな状況でそもそも撮影などできるのでしょうか。確かにその気持ちには同意できますし、そして無理にご自身の行動半径を広げる必要はないと思っています。
ただ、そういった「制約」は制作においてむしろ「条件」という捉え方の変化ができるものでもありますし、日常で見過ごしていた違和感に気づくきっかけになることもあります。他者が撮れないのなら、毎日「連続しているかのような」自分を他者に見立て撮影することもできるでしょう。あるいは、人間でないものに他者性を見出す眼差しがあってもいいと思います。また、日常的に着用することが暗黙の了解となったマスクを外す場面の線引きからは、無意識に分け隔てている境界が見えてもきます。実は、写真家は必ずしも動き続けなくても、作品を提示しそこから思考することはできるのです。
その際、一方的に入ってきた情報に立ち止まり、自分自身の中で整理・最適化していくことも必要かと思います。言葉には大きく2種類あって、ひとつは政治やメディアの世界から「降って」くる言葉。そしてもうひとつは日常の身体から「湧いて」くる言葉です。前者は誰かの意図をいつのまにか内面化し引き継いでしまうことがありますが、後者は自分で選択したものを使うことができます。
社会を循環するそれらの言葉は、やがて構造や風潮を作り出してしまうからこそ、まずは自分自身に聞き耳を立てるようなところから顕れる湧水のような言葉に価値を思います。ここ数ヶ月のあいだ、降ってきた言葉が溢れ、それに飲み込まれるような生活があったからこそ、みなさんの個人的な眼差しからやってくる作品について、楽しみにしています。
少し長くなってしまいましたが、くれぐれも無理はせず、しかしもし足踏みをされているようなことがあれば視点を変えて、状況がもたらした再考の機会をうまく利用されてみてください。教員は、そこから次の一歩に繋がり作品の芽が育っていくための、みなさん自身を映す「鏡の役割」ができればと思っています。また添削やスクーリングでお目にかかれることを楽しみにしています。
写真コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら
おすすめ記事
-

写真コース
2024年06月03日
【写真コース】風景写真について学べる講座のご紹介
みなさん、こんにちは。写真コース専任教員の河田憲政です。 気づけば初夏となり、汗ばむ日々が続きますがいかがお過ごしでしょうか。 今回は一般公開講座「藝術学舎」で…
-

写真コース
2021年12月02日
【写真コース】入学時に必要な機材について、簡単に解説します。
こんにちは。通信教育部 写真コース 非常勤講師の大河原です。 今回のブログでは、入学時に必要となる撮影機材について簡単に解説したいと思います。 入学説明会でも多…
-

写真コース
2022年12月20日
【写真コース】通信写真コースの教員紹介 ー片岡 俊先生ー
こんにちは。今年度10月より通信教育部 写真コースにて非常勤講師となりました片岡俊です。これからどうぞよろしくお願いいたします。 12月になり卒業制作の準備も隆…