

和の伝統文化コース
- 和の伝統文化コース 記事一覧
- 【和の伝統文化コース】スクーリング「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」のご紹介
2022年02月07日
【和の伝統文化コース】スクーリング「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」のご紹介
こんにちは。
和の伝統文化コースの教員の森田都紀です。
今回は、本学通信教育課程「和の伝統文化コース」の「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」という授業を紹介したいと思います。
★★★本ブログの末尾に、2021年度の受講生からのアンケートの声を掲載しています★★★
本コースでは、
花・茶・書・香・能・歌舞伎・日本舞踊・着物などの伝統文化に幅広く触れ、
日本の伝統文化を理解することを目指しています。
この「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」は、江戸時代初期に大坂で成立した
人形浄瑠璃(文楽)を講義とワークショップを通じて学ぶことを目的としており、
Zoomを用いたオンラインで行われました。
初日には、人形浄瑠璃の歴史や舞台構造に関する講義と、
「義太夫節(ぎだゆうぶし)」の語りのワークショップがありました。

語りのワークショップでは、竹本綾之助先生の迫力あふれる義太夫節にあわせ、皆でお腹から声を出しました。
題材は《仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)》の「裏門の段」。
赤穂浪士の討ち入り事件に取材した名作です。
Zoomを通して学生の皆さんの積極的な語りを聴くことができました。
二日目には鶴澤寛也先生にお越しいただきました。
最初に「太棹」といわれる義太夫三味線の楽器の構造と
人形の役柄別による弾き分けを実演付きで解説いただきました。
その後、《仮名手本忠臣蔵》の「裏門の段」を演奏いただきました。

義太夫三味線の音色は重厚なのにとても繊細です。
鶴澤寛也先生より、
「義太夫三味線は伴奏楽器ではありません。物語の情景を音で描くのです。」
とお聞きしました。
太夫の語りを増幅させ、観客をその場面に引き込んでいきます。
「ベン」と響く一つの音だけで、涙することもありますね。
「義太夫三味線の難しさを知るには時間がかかります。」というお話も伺い、
難しいということすら容易に知ることができない という、
この道の奥深さを学びました。
★★★2021年度の受講生の皆様からの声★★★
「初めて義太夫節と三味線を聴いて、特に三味線の音に鳥肌が立ちました。
浄瑠璃、文楽の歴史よりも義太夫節の声と三味線の音に魅了されました。」
「語り実習が初めての経験であり、イントネーションも複雑でとても難しかった。
しかし、自ら声を出して練習できたので、とても良い講義だったと思う。」
「文楽に全く縁がなかったので学習を進められるか心配したが、
こんなに楽しいものなのだと実感させてもらえました。
環境が整ったら、観劇に出掛けたいと思いました。」
もちろん、対面でぜひ受講したかった、という声も寄せられておりました。
みなさまがご入学される際には、ぜひ対面での実施ができるよう、
社会情勢を見守りつつ、実施に向けて準備をしております!(事務局より)
★★★
和の伝統文化コースでは、伝統文化を広く学び、伝統文化の今ある姿を動的に見つめ、
これからの文化のあり方を考えていきます。
他にも魅力的な授業がたくさんあります。
次回の報告もどうぞお楽しみに。
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

和の伝統文化コースの教員の森田都紀です。
今回は、本学通信教育課程「和の伝統文化コース」の「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」という授業を紹介したいと思います。
★★★本ブログの末尾に、2021年度の受講生からのアンケートの声を掲載しています★★★
本コースでは、
花・茶・書・香・能・歌舞伎・日本舞踊・着物などの伝統文化に幅広く触れ、
日本の伝統文化を理解することを目指しています。
この「伝統文化実践Ⅱ‐1(伝統邦楽)」は、江戸時代初期に大坂で成立した
人形浄瑠璃(文楽)を講義とワークショップを通じて学ぶことを目的としており、
Zoomを用いたオンラインで行われました。
初日には、人形浄瑠璃の歴史や舞台構造に関する講義と、
「義太夫節(ぎだゆうぶし)」の語りのワークショップがありました。

語りのワークショップでは、竹本綾之助先生の迫力あふれる義太夫節にあわせ、皆でお腹から声を出しました。
題材は《仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)》の「裏門の段」。
赤穂浪士の討ち入り事件に取材した名作です。
Zoomを通して学生の皆さんの積極的な語りを聴くことができました。
二日目には鶴澤寛也先生にお越しいただきました。
最初に「太棹」といわれる義太夫三味線の楽器の構造と
人形の役柄別による弾き分けを実演付きで解説いただきました。
その後、《仮名手本忠臣蔵》の「裏門の段」を演奏いただきました。

義太夫三味線の音色は重厚なのにとても繊細です。
鶴澤寛也先生より、
「義太夫三味線は伴奏楽器ではありません。物語の情景を音で描くのです。」
とお聞きしました。
太夫の語りを増幅させ、観客をその場面に引き込んでいきます。
「ベン」と響く一つの音だけで、涙することもありますね。
「義太夫三味線の難しさを知るには時間がかかります。」というお話も伺い、
難しいということすら容易に知ることができない という、
この道の奥深さを学びました。
★★★2021年度の受講生の皆様からの声★★★
「初めて義太夫節と三味線を聴いて、特に三味線の音に鳥肌が立ちました。
浄瑠璃、文楽の歴史よりも義太夫節の声と三味線の音に魅了されました。」
「語り実習が初めての経験であり、イントネーションも複雑でとても難しかった。
しかし、自ら声を出して練習できたので、とても良い講義だったと思う。」
「文楽に全く縁がなかったので学習を進められるか心配したが、
こんなに楽しいものなのだと実感させてもらえました。
環境が整ったら、観劇に出掛けたいと思いました。」
もちろん、対面でぜひ受講したかった、という声も寄せられておりました。
みなさまがご入学される際には、ぜひ対面での実施ができるよう、
社会情勢を見守りつつ、実施に向けて準備をしております!(事務局より)
★★★
和の伝統文化コースでは、伝統文化を広く学び、伝統文化の今ある姿を動的に見つめ、
これからの文化のあり方を考えていきます。
他にも魅力的な授業がたくさんあります。
次回の報告もどうぞお楽しみに。
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-
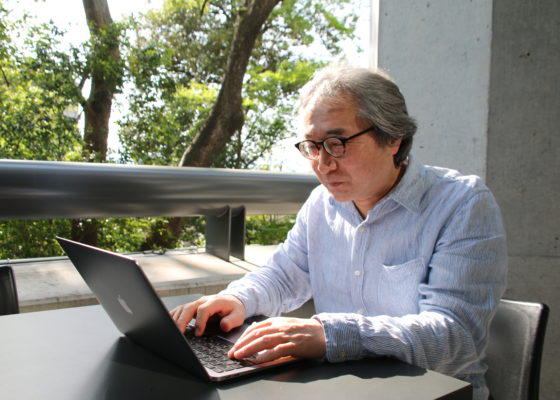
通信教育課程 入学課
2021年05月28日
「オンライン学習」のサポート体制-パソコン操作の基本編-
こんにちは。京都芸術大学 通信教育部 教務部長の野村です。普段は芸術教養学科の教員をしていますが、教務委員会では通信教育部の学修サポートにもあたっています。 今…
-

和の伝統文化コース
2021年04月23日
【和の伝統文化コース】入学後の「はじめの一歩」を紹介します
皆さん、こんにちは。和の伝統文化コース教員の井上治です。 新年度が始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今年度はこれまでで最多の100名以上の方々が本コー…
-

和の伝統文化コース
2021年09月30日
【和の伝統文化コース】「一座」と「独座」と「オンライン」で深める和の学び
みなさん、こんにちは。和の伝統文化コースの中村幸です。 さて、このブログをご覧の方の中には、奥座敷で相伝の印象もある日本の芸能・芸道などの文化を、大学の通信教育…






























