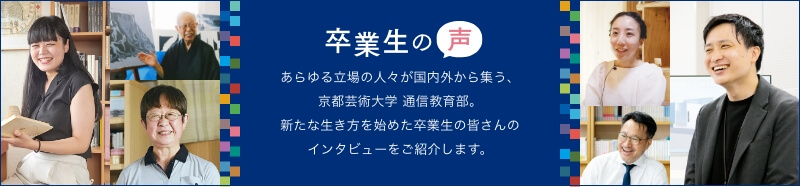| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 4年間 = 924,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(4年間) |
|
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 2年間 = 462,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(2年間) |
|
芸術学科
JAPANESE CLASSICALAND TRADITIONAL ARTS
日本の伝統的な文化や芸術について、カタチや技ではなく、その内面にある存在価値を深く考察。
それを通して、いまある私たちの文化のあり方を見つめ直します。
茶道や花道など、実際に体験できるワークショップ型の科目を数多く用意。心と体を活性化する「知恵」としての伝統文化を、生活や仕事に活かすことをめざします。
能楽、歌舞伎、茶の湯、生け花など、幅広いジャンルの伝統文化を学習。「実技」と「心」の両方を学び、さまざまな伝統文化が、根底ではつながっていること、それらの心や技を現代にどう活かすかについて、実践的に学んでいきます。
京都という地の利を生かし、流派家元や狂言師、作庭師など、その道の達人をスクーリング講師に招聘。現役の役者に指導を受ける貴重な体験など、実践を通して、伝統文化を体感的に学べます。
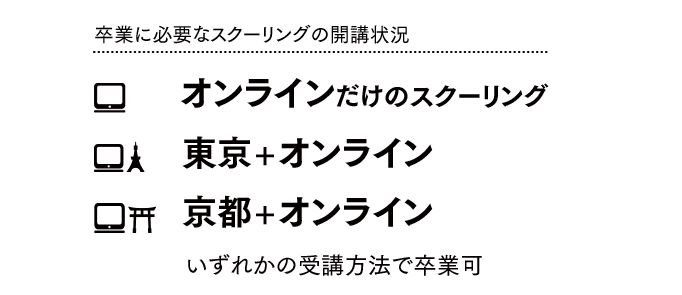
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ◆ 伝統芸能の諸相 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 詩歌と日本文化 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 室礼ともてなし | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 京都学研修 1 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 京都学入門 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 日本文化の源流 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 日本文化と東アジア | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 伝統文化基礎講義 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 伝統文化論Ⅰ-1 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 伝統文化研修 | 2日間 | |||||||||||
| ★ 伝統文化入門 | 1日間 | |||||||||||
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ◆ 伝統芸能の諸相 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 伝統芸能と工芸 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 詩歌と日本文化 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 花道文化の展開 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 伝統文化の空間 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 室礼ともてなし | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 論文研究特論 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 日本文化の源流 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 論文研究Ⅰ-1、2 | 2日間 | レポート | ||||||||||
| ◆ 論文研究Ⅱ-1、2 | 2日間 | レポート | ||||||||||
| ★ 伝統文化入門 | 2日間 | |||||||||||
| ★ 伝統文化研修 | 1日間 | |||||||||||
| ★ 伝統文化実践Ⅰ-1、4 | 2日間 | 2日間 | ||||||||||
| ★ 伝統文化実践Ⅱ-4 | 2日間 | |||||||||||
| ★ 伝統文化基礎講義 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 伝統文化論Ⅰ-1、2、3 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||
| ★ 伝統文化論Ⅱ-2 | レポート | 試験 | ||||||||||
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 4年間 = 924,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(4年間) |
|
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 2年間 = 462,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(2年間) |
|
大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)和の伝統文化コースに3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。
また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。
書類審査
(大学等の卒業証明書など)
最短2年
3年次編入学の出願資格に
該当しない方は最短4年(1年次入学)
通信教育部
和の伝統文化コース
書類審査
(指定提出物など)
最短2年
大学院
芸術学・文化遺産領域

「ここなら、自分の本当に好きなことを見つけられる」。高校を出たばかりの齋藤さんが、迷うことなく次の進路に選んだのは、和の伝統文化コース。「一般の大学だったら、どうしてもひとつの分野を選ぶことになるでしょう。でも、正直なところ、そこまで突きつめたいものがなかったので」。進学の必要性を感じられなかったところに、家族が本コースの存在を教えてくれたという。「説明会を受けて、茶道や能楽の学びに参加。たちまち、その幅広さに引き込まれました」。
入学後は、ますますスクーリングの面白さにはまり、歌舞伎、浄瑠璃、小唄、声明など、あらゆる伝統芸能を10代にして人生初体験。「たとえば声明の授業なら、教壇に立つのは本物の僧侶。その道を極めた先生方が、実践をまじえて歴史や思想まで教えてくださるので、どの授業も印象深くて」。”伝統文化“という言葉の響きだけで”厳しくて恐そう“と思っていたのが、「授業を通して、魅力ある出会いができたおかげで、ひとつひとつの文化を身近に感じられました」と、イメージが一変。授業をきっかけに、地元で三味線や着物を学び直すなど、興味が広がるにつれ、自分の世界も広がったという。
こうして、さまざまな学びを吸収していった齋藤さん。それらを練りあげ、レポートや論文で発信することでも、これまでにない感動を味わえた。「大好きな”昭和歌謡“を取りあげた卒業研究で、思いがけず賞をいただいて」。一般的な伝統文化とはかけ離れているし、きっとだれも興味を持ってくれない。そんな迷いを抱えながらも、情熱を注いだ論文が評価され、「自分が思ったとおりにすすんで、いいんだ」という大切な自信をもらえた。「いまは、地元の古書店に勤めながら、子育て支援施設をお手伝い。子どもたちに、いろんな文化を体験する面白さを伝えられたら」と話す齋藤さん。未知の伝統文化を学んで見つけたのは、これからの新しい自分自身でもあった。

「そういえば、私、なんにもわかっていない」と、入学を決意した梅田さん。長年、花道を習ってきて、生け花の作家や指導者としてのキャリアもありながら、本学の和の伝統文化コースへ。「あるとき外国人学生の方々に、生け花を教える機会があったんです。すると、こちらの答えに詰まるような質問がつぎつぎと飛び出してきて」。なぜ、花道は型どおりに生けるのか?なんのために花道があるのか? 自分が何十年も当たり前だと思ってきたことを、なにひとつ説明できないという事実に気づかされ、少なからずショックを受けた。「日本人として知っておきたいこと、伝えていきたいことを、あらためて学んでおこうと思ったんです」。
入学して出会ったのは、他流派の花道をはじめ、茶道、和歌など、さまざまな日本文化の”素顔“。どれも、うわべだけで知ったつもりになっていたけれど、本当の奥深さを体感できたという。なかには、現代ドラマと同じようなストーリーにワクワクするものも。「ある平安時代の歌謡に、女どうしの壮絶なバトルが描かれていて。昔の女性もたくましい!と痛快でした」。
思い込みを捨てて、まっさらな気持ちで向き合えば、色あせてみえた伝統もいきいきと輝いてくる。その豊かさにふれて、自身の意識が変わったことが、梅田さんの生ける花そのものを変えたという。「自分ではよくわからないのですが、長年の師匠や身近な方から、”別人の作品かと思った“とお褒めいただきました」。
一方で、伝統文化のすばらしさを知れば知るほど、強く気にかかることもあった。それは、次の世代に受け継がれているのか、という危機感。「自然を尊び、万物を愛でる。そんな日本の心を伝えられたら」と、お花の展覧会などの活動にいっそう力を入れるようになった梅田さん。自分らしいかたちで、かけがえのない学びのリレーを、つぎの時代へつなげていく。


卒業後は大学院の「文化遺産・伝統芸術分野」に進学。「珈琲文化普及」の研究論文をさらに練りあげて完成度を高めることを、何よりの目標としている。
「和物っていいな、と、年を重ねるほど思うようになりました」と入学のきっかけを語るM.Sさん。華やかな西洋文化に憧れた娘時代を過ぎ、家庭に入ってからは家族の世話に追われ、ようやく自分の時間を持てるというタイミングで、本学の広告を見つけた。「これから趣味を増やし、人生を豊かにする手がかりになれば」。そんな期待をはるかに上回る、幅広く本格的な学びの数々。さほど詳しくなかった伝統文化の世界に、すっかりひきこまれていった。「これまでテレビで見かけるだけだった〝能〞も、テキスト課題やスクーリングで学ぶと、別モノのように舞台が面白く感じられて」。茶道や花道など、ひとつひとつの授業を受け持つ先生が、その道の達人や専門家であるだけでなく、熱意ある指導に感銘を受けたという。
「最初は、通信教育のスタイルを〝気軽でいい〞と受けとめていたんです。でも初提出のレポートで、先生が細部まで自分の意図をくみ取ってくださったのがうれしくて。楽しくがんばって取り組むほど、評価や結果で返ってくると実感しました」。通信の距離をこえた心のやりとりに、学ぶ意欲が一気に開花。「卒業論文の題材も、調べられる資料が残る時代の、あまり前例がないものにしよう」と、〝大正・明治期の珈琲普及〞という異色のテーマに挑戦。「調べるほど、興味をそそられる発見があって。もう一歩研究を深いものにしたくて、卒業後は大学院へ」。入学時には想像もしなかった、自身の変化である。
そんなM.Sさんが、本コースで得た一番の成果とは。「伝統文化という形で受け継がれてきた昔の人々の想いが、今の自分でもひしひしと身に迫るように、共感できることが多くて。私も日本人の一員なんだ、と、地に足がつく安心感を得られました」。人生の節目に、伝統文化を通して、自身のなかにある日本の心を見つめ直せたというM.Sさん。新しい知見をひらく学びは、思いがけず、自分の奥深くへとつながっていた。


夫の喪から休んでいた茶道教室も、卒業を機に再開。「大学で、いろいろな方が伝統文化を守り伝えようとしているのを間近に感じて。私も、できることをしたいですね」。
「そろそろリタイア後の生活を考えようかという時に、夫が倒れて。朝までは元気そのものだったのに」。心痛む入学のきっかけを、気丈な笑顔で語ってくれた石井さん。突然すぎる別れにぽっかり開いた心の穴を、少しでも埋めたくて本学へと飛び込んだ。「いい歳だし、卒業しなくてもいいから、なんて息子に言われて。じゃあ卒業してみせるわよ、と逆に奮起しました」。いろいろな想いを振り払うように、和の学びに没頭していった。
数多くある学びから本コースを選んだのは、取り組みやすく、体力的にも安心できそうだったから。そして何より、昔から和の文化が大好きだったから。「お茶は長年つづけていますが、他はそれほど詳しくないんですよ」と笑む石井さん。モノや表現にはたくさんふれてきたけれど、その歴史や裏の心まで深く考える機会はなかった。「このコースで学ぶほど、それぞれの奥深さや互いのつながりを知り、さらに素晴らしさを感じられるようになりました」。
もともと東京で学べる便利さもあって本学を選んだはずが、気がつくと京都でのスクーリングに通いづめ。「お寺めぐりや京繍など、この地でしかできない経験がたくさんあったので、つい」。「2年で卒業するつもりが3年かかったけれど、本当は最長7年もありだな、と思ったくらいです」と微笑む。けれど初心を貫くためにも、卒業論文は仕上げておきたかった。「テーマ選びも執筆も大変で、さすが大学、と実感させられましたね」。
分厚い専門書を何冊も読み、資料を作り直し、努力の末に完成させた論文は、近代の茶人をテーマにしたもの。「お茶席には、空間から道具まで、その人だけの世界観があふれているんです」。じつは何十年もお茶を習い、自身の教え子もいる石井さん。「ここで学んだことを活かして、私だけの茶事をつくりだしたいですね」。そう語るかたわらには、夫が趣味で手がけた陶の器があった。失う悲しみから、新たに学ぶよろこびを知り、おわりのない茶の道、和の道を見つめていく。