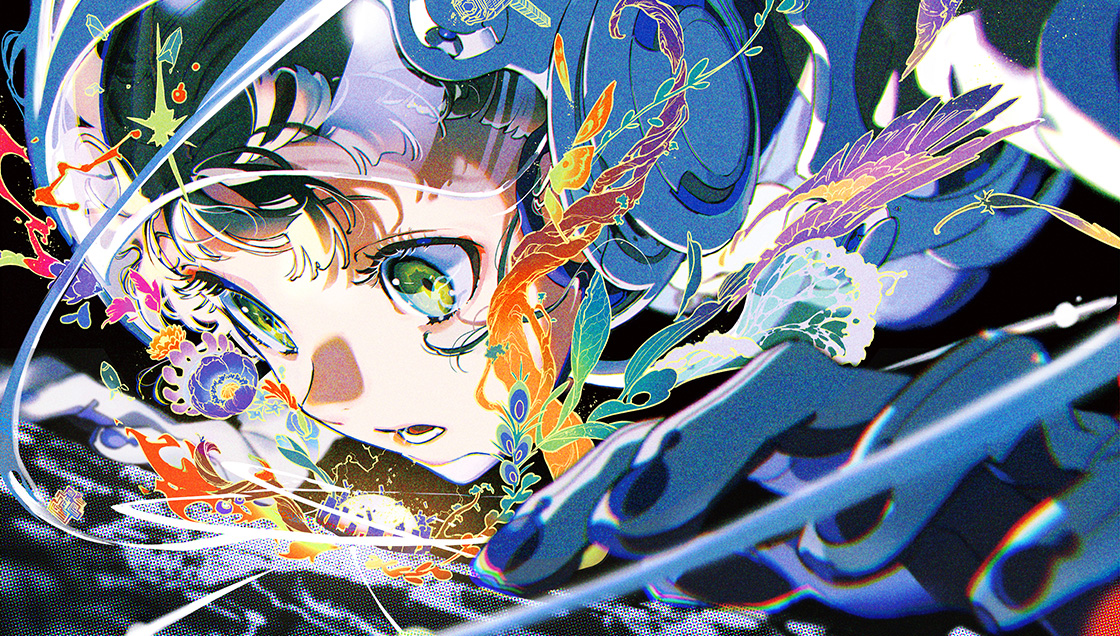

イラストレーションコース
- イラストレーションコース 記事一覧
- 【イラストレーションコース】参考書籍の選び方・活用のコツ
2022年03月17日
【イラストレーションコース】参考書籍の選び方・活用のコツ
こんにちは。イラストレーションコース研究室の虎硬です。
皆さんはイラストを勉強する時に書籍を参考にするでしょうか。近年はイラストに関しても動画教材が増えていますが、依然として書籍から得る情報は重要です。今日はそんなイラスト参考書籍の選び方や使い方についてお伝えします。

イラスト参考書籍は大きくわけて2種類あると考えています。一つ目は資料集、二つ目はノウハウ本です。もちろん双方の情報が入ったハイブリッドなものもあるでしょう。
資料集は図鑑などに代表されるように、あるモチーフについて図で表現されているものが多いです。動物のイラストを描きたい時は図鑑を参考にすると良いですし、人物を描くときは解剖学の本も参考になります。人物のポーズ写真集なんかもこちらにあたります。
資料集は描き方についてのアプローチは少なく、あくまでも図で対象モチーフの描画を理解することが主な使い方です。模写などの練習をするときにも役に立ちます。
良い資料集とは、画図の掲載点数が十分であり、クオリティが高いことが条件です。購入する際は、写真やイラストなどが自分にとって良いと思えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
ノウハウ本には、絵の描き方が掲載されている、いわば教科書のような役割があります。例えば色についてのノウハウ本であれば、色を感じる仕組み、色相、明度、彩度などといった基礎知識についても解説が載っています。つまり絵を作るための原理について解説したものとなっています。
資料集とは大きくアプローチが異なるもので、著者の解説力やノウハウの再現性が読み手にとっては重要なものとなります。つまり、ノウハウ本は著者が想定しているレベルと読み手のレベルが一致していなければ理解することが難しいものです。
イラストのノウハウ本は「初心者向け」という文言はあっても、中級者、上級者向けについて言及されているものはほとんどないので、これも事前に内容を確認した上で、自身のレベルにマッチしているかを考えてみると良いでしょう。
また、それぞれの書籍を読む時にもインプットの仕方が異なります。まず資料集はどの絵を描く時にも必ず使うものではありません。購入したらまず内容をパラパラとめくって何が掲載しているかをざっくりと把握しましょう。把握したら本棚にしまっておいて、必要になったら使います。イラストを描いて資料が必要になった時に「あの資料集に載っていたな」とあとから思い出せることが大切です。
ノウハウ本も資料集と同じような使い方もできますが、できるだけ実践すべきです。一般的なイラストノウハウ本には制作手順や描き方のコツ、調色方法などが掲載されています。それらを流して読むのでなく、しっかりと自分の手で絵を描き、感覚的に身につけることが大切です。なぜなら表現は、目で見るのと体験するのでは大きく異なるからです。「できそう」と思っても、実践したらできなかったり、その逆もあります。
そういった自身のイメージとノウハウの差がどこにあるのか、そういった齟齬を埋めていくことがイラスト学習では非常に大切になります。
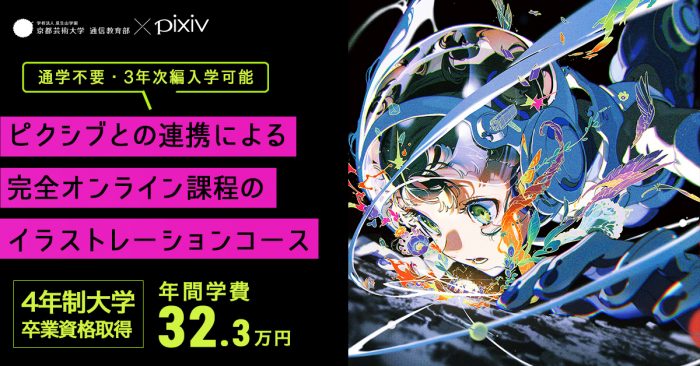
イラストレーションコース|学科・コース紹介
皆さんはイラストを勉強する時に書籍を参考にするでしょうか。近年はイラストに関しても動画教材が増えていますが、依然として書籍から得る情報は重要です。今日はそんなイラスト参考書籍の選び方や使い方についてお伝えします。

イラスト参考書籍は大きくわけて2種類あると考えています。一つ目は資料集、二つ目はノウハウ本です。もちろん双方の情報が入ったハイブリッドなものもあるでしょう。
資料集
資料集は図鑑などに代表されるように、あるモチーフについて図で表現されているものが多いです。動物のイラストを描きたい時は図鑑を参考にすると良いですし、人物を描くときは解剖学の本も参考になります。人物のポーズ写真集なんかもこちらにあたります。
資料集は描き方についてのアプローチは少なく、あくまでも図で対象モチーフの描画を理解することが主な使い方です。模写などの練習をするときにも役に立ちます。
良い資料集とは、画図の掲載点数が十分であり、クオリティが高いことが条件です。購入する際は、写真やイラストなどが自分にとって良いと思えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。
ノウハウ本
ノウハウ本には、絵の描き方が掲載されている、いわば教科書のような役割があります。例えば色についてのノウハウ本であれば、色を感じる仕組み、色相、明度、彩度などといった基礎知識についても解説が載っています。つまり絵を作るための原理について解説したものとなっています。
資料集とは大きくアプローチが異なるもので、著者の解説力やノウハウの再現性が読み手にとっては重要なものとなります。つまり、ノウハウ本は著者が想定しているレベルと読み手のレベルが一致していなければ理解することが難しいものです。
イラストのノウハウ本は「初心者向け」という文言はあっても、中級者、上級者向けについて言及されているものはほとんどないので、これも事前に内容を確認した上で、自身のレベルにマッチしているかを考えてみると良いでしょう。
書籍の活用のコツ
また、それぞれの書籍を読む時にもインプットの仕方が異なります。まず資料集はどの絵を描く時にも必ず使うものではありません。購入したらまず内容をパラパラとめくって何が掲載しているかをざっくりと把握しましょう。把握したら本棚にしまっておいて、必要になったら使います。イラストを描いて資料が必要になった時に「あの資料集に載っていたな」とあとから思い出せることが大切です。
ノウハウ本も資料集と同じような使い方もできますが、できるだけ実践すべきです。一般的なイラストノウハウ本には制作手順や描き方のコツ、調色方法などが掲載されています。それらを流して読むのでなく、しっかりと自分の手で絵を描き、感覚的に身につけることが大切です。なぜなら表現は、目で見るのと体験するのでは大きく異なるからです。「できそう」と思っても、実践したらできなかったり、その逆もあります。
そういった自身のイメージとノウハウの差がどこにあるのか、そういった齟齬を埋めていくことがイラスト学習では非常に大切になります。
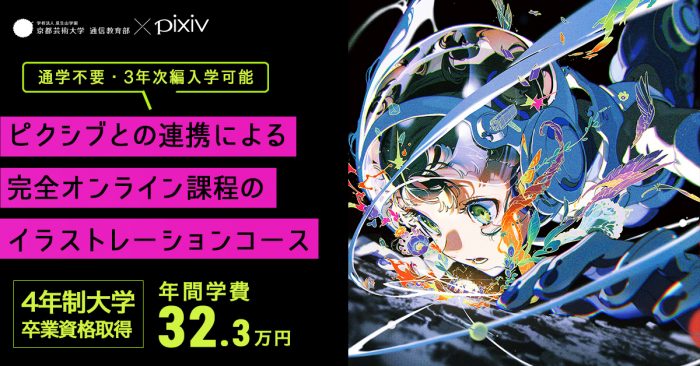
イラストレーションコース|学科・コース紹介
おすすめ記事
-
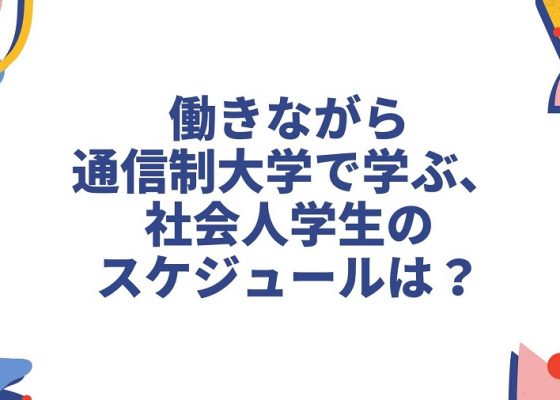
通信教育課程 入学課
2022年04月25日
働きながら通信制大学で学ぶ、社会人学生のスケジュールは?
通信制大学に入学した場合の学習ペースや、働きながら学習・卒業できるのかを知りたい方のために、「社会人大学生の一日」について本学通信教育部卒業生4名の具体例を紹介…
-
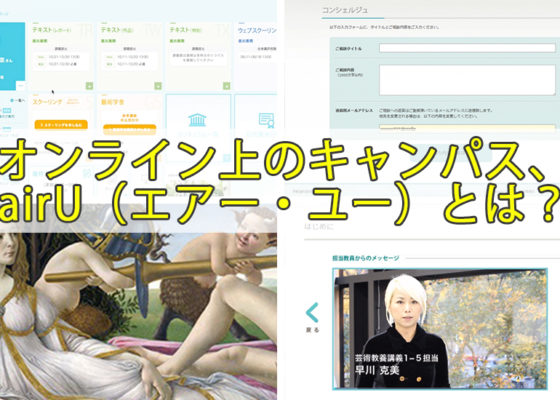
通信教育課程 入学課
2021年08月05日
通信教育課程のオンラインキャンパス「airU(エアー・ユー)」とは?
こんにちは。京都芸術大学通信教育課程 入学課です。 本学通信教育部では、「airU(エアー・ユー)マイページ」という学習用Webサイトを活用して学習を進めます。…
-

イラストレーションコース
2021年05月25日
【イラストレーションコース】1期生の学修がスタート!―テキスト科目のご紹介―
はじめまして。イラストレーションコース研究室の虎硬(とらこ)と申します。今回はブログを書く機会をいただくにあたり、イラストレーションコースカリキュラムについてお…






























