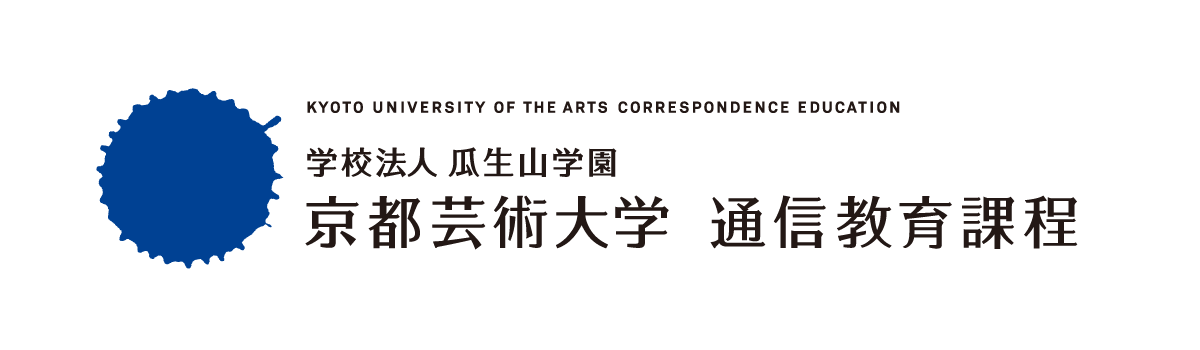文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】「キャラクター名」にはコンセプトが必要⁉
2022年05月27日
【文芸コース】「キャラクター名」にはコンセプトが必要⁉
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。
さて、今回は小説を書く上で考えなくてはならない「キャラクター名」について、ちょっと書いてみたいと思います。
小説をこれから書きたいと思っている、あるいは既に書いている皆さんは、おそらく作中に登場させる人物の名前について、一度ならず頭を悩ませた経験があるでしょう……とはじめると、「いや、キャラクターの名前なんてどうでもいいよ。小説で大事なのはストーリーでしょ?」と感じる方も中にはいらっしゃるかもしれません。ですが、読者にとってキャラクター名とは、作品へ没入する上での最初の入口。キャラクターを愛でるにせよ嫌うにせよ、読者が作品を読み進める上での、取っ掛かりとしての名前は、(とりわけ登場人物が多いような作品であれば)必要不可欠な要素ではないでしょうか。
通信教育部 文芸コース紹介ページ(大学HP)

では、実際に作家はどのように作品におけるキャラクター名を決めているのでしょうか? まずは大文豪の事例から学んでみましょう。
なるほど、あの『罪と罰』に登場する人物の名前には、こんな由来があったわけですね。何気なく(?)読んでいたドストエフスキーですが、キャラクター名のコンセプトが判明すると、それぞれの役割やセリフの意味、物語の構造まで違って読めてくるから不思議です。
知りませんでした。カラマーゾフはつまりミスター「Paint It Black」、あの重厚すぎるほどに重厚な物語にピッタリくる姓だったんですね。ちなみに引用文中のポリフォニックとは、ここでは多層的、重層的といった意味合いで使われていると私は考えます。ドストエフスキーの作品における登場人物の名前が、非常に複雑な、何重もの意味や文脈を背負った上で決定されているということなのでしょう(ちなみに引用した『謎解き『罪と罰』』の著者であるロシア文学者江川卓(1927〜2001年)氏の著書はどれもロシア文学、とりわけドストエフスキーをより深く学びたい人にとってはとても勉強になるものばかりです。今調べてみたところ、新潮選書のラインナップではまだ新刊として購入が可能なようですから、興味を持った方はぜひとも読んでみてください)。ドストエフスキーほどの大文豪ともなると、キャラクター名ひとつとっても徒や疎かにしていないというか、かくも深甚な、絶大な意図と思想を込めて決定されているということがわかるかと思います。
しかしながら、一方で「それは海外文学の話だろ? 日本語で書く小説に登場する日本人のキャラクター名をポリフォニックにしたら……野比のび太とか出来杉英才とか、そんな感じになっちゃうじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。確かにあまりに読み取りやすい多義性をキャラクター名に込めてしまうと、作風が固定化されてしまうというか、読者からすると物語の展開そのものも透けて見えてしまうような、そうしたデメリットも考えられます。仮に「私の名前は骨川痩夫(ほねかわやせお)。今日は意を決して駅前にあるトレーニングジムの門を敲くことにした。」みたいな書き出しの小説があったら、ちょっと読む気がしませんよね。もうキャラクターの名前でオチまで見えてしまう気すらします。
となると、ポリフォニックでありながら幾重にも日本語のヴェールを被せた固有名詞が望まれるのかもしれません。一例を挙げるなら、やはり三島由紀夫でしょうか。『鏡子の家』の鏡子は、戦後の一時代を映す鏡であり、交わらない個々人という現代を予言する鏡でもあり……とやりたいところですが、あいにくと私は専門家ではないため恥を晒す前にこのあたりでよしておきましょう。『金閣寺』の溝口や『潮騒』の新治や初江あたりも、いかにも作品のコンセプトを託された名前という感じがするのですが……興味がある方はぜひ論文や研究書を紐解いてみてください。あるいは、もう少し薄めのヴェールがご希望なら、ライトノベルなどの作品群にも参考になるものはありそうです。手元にある作品ですと、例えば『りゅうおうのおしごと!』(白鳥士郎、GA文庫)の主人公、九頭竜八一はいかにも将棋が強そうなキャラクター名ですよね。作中では「八月一日生まれだから八一」ということにされていますが、この名から将棋盤を連想しないわけにはいきませんし、姓もまた棋界最高位とされる竜王を想起させます。他には、西尾維新の作品に登場するキャラクター名などにも(私は西尾維新の作品をすべて読んだわけではないので断定的には語れないのですが)丁寧に吟味されたポリフォニックな意味性が付与されていそうです。
もちろん、上記の私の主張への反論もあるでしょう。「えー、九頭竜も戦場ヶ原も……なんかリアリティがないよ。そんな姓をキャラクター名に使ったら、途端にリアルな小説じゃなくなっちゃう」とする意見があれば、私は否定しません。ただし、だからといってリアルに寄せようとするあまり、ありそうな姓名を現実の存在から適当に借りてくるだけというのは、ダメです。なぜって……読者が作品を読み解く楽しみがひとつ、減ってしまうじゃないですか。後年の研究者から作品を分析する喜びを奪ってしまう危険性もあります。どのような姓名をキャラクターに冠するのも、作者の自由ではありますが、そこにコンセプトを持たせないと作品の厚みが目減りしてしまうと、私は考えています。
さて、長々書いてしまいましたが、もし仮に「もう、うるさいなあ。いろいろ言われたらかえって思いつかないよ!」と憤慨する方がいらっしゃったら……いっそのこと、キャラクター名をあえてつけない、というスタイルはどうでしょうか? 「名前のない主人公」は文芸表現においては一種のスタンダードでもあり、カフカの「K」しかり、安部公房の「S」しかり、夏目漱石の「吾輩」しかり……おっと、漱石なら『坊っちゃん』の「おれ」がいましたね。「主人公の匿名性」というテーマにおける文学史上の最大の成功例である「おれ」は、とりわけ近現代の日本文学に絶大な影響を及ぼしていると私は思います。谷川流の『涼宮ハルヒ』シリーズの主人公は作中でこそ「キョン」と呼ばれていますが、地の文では徹頭徹尾「俺」を貫いています。それは、未成熟な個人主義が延々と繰り返される日本の文化を象徴する一種のアイコンとして……いやはや、そろそろ紙面が尽きてきました。より詳細な話は、また別の機会にするとしましょう。ではまた。
文芸コース| 学科・コース紹介

さて、今回は小説を書く上で考えなくてはならない「キャラクター名」について、ちょっと書いてみたいと思います。
小説をこれから書きたいと思っている、あるいは既に書いている皆さんは、おそらく作中に登場させる人物の名前について、一度ならず頭を悩ませた経験があるでしょう……とはじめると、「いや、キャラクターの名前なんてどうでもいいよ。小説で大事なのはストーリーでしょ?」と感じる方も中にはいらっしゃるかもしれません。ですが、読者にとってキャラクター名とは、作品へ没入する上での最初の入口。キャラクターを愛でるにせよ嫌うにせよ、読者が作品を読み進める上での、取っ掛かりとしての名前は、(とりわけ登場人物が多いような作品であれば)必要不可欠な要素ではないでしょうか。
通信教育部 文芸コース紹介ページ(大学HP)

では、実際に作家はどのように作品におけるキャラクター名を決めているのでしょうか? まずは大文豪の事例から学んでみましょう。
『罪と罰』の作中人物たちは、そのほとんどが「意味のある」名前を持っている。日本名としていくぶん据わりの悪いことを我慢すれば、おおかたが「翻訳」可能でさえある。たとえば、愛すべき酔いどれの九等官マルメラードフは、フランス語の「マルメラード」、つまり果物の砂糖煮、ママレードがもとであり、創作ノートを見れば「お砂糖のような姓」という書きこみもあるので、「佐藤聞太」ないし「甘井聞太」と翻訳できる。いかにも拵えものじみた滑稽な名前だが、原作そのものにそういう味わいがある。(中略)断っておくが、名を「聞太」としたのは、ためにする訳者のいたずらではなく、彼の洗礼名のセミョーン(シメオン)がヘブライ語の「聞く」に由来するからである。
(江川卓『謎解き『罪と罰』』、新潮社、1986年、31〜32頁より引用)
なるほど、あの『罪と罰』に登場する人物の名前には、こんな由来があったわけですね。何気なく(?)読んでいたドストエフスキーですが、キャラクター名のコンセプトが判明すると、それぞれの役割やセリフの意味、物語の構造まで違って読めてくるから不思議です。
『悪霊』のスタヴローギンの姓は、「十字架」とも「角立て」(悪魔)とも読める。カラマーゾフにいたっては、直訳すれば「黒塗」だが、これは、民衆に「塗炭」の苦しみを与える存在とも、「黒いキリスト」とも解釈できる。キリストの原義は「油を塗られたもの」だが、カラマーゾフは油の代りに「カラ」(チュルク語で「黒」)を塗られるわけである(「まーゾフ」はロシア語の動詞「塗る(マザーチ)」から派生)。ここまでくれば、これはもうたんなる多義性ではなく、名前そのものがポリフォニックな構造をもつと考えなければなるまい。
(江川卓『謎解き『罪と罰』』、新潮社、1986年、38頁より引用)
知りませんでした。カラマーゾフはつまりミスター「Paint It Black」、あの重厚すぎるほどに重厚な物語にピッタリくる姓だったんですね。ちなみに引用文中のポリフォニックとは、ここでは多層的、重層的といった意味合いで使われていると私は考えます。ドストエフスキーの作品における登場人物の名前が、非常に複雑な、何重もの意味や文脈を背負った上で決定されているということなのでしょう(ちなみに引用した『謎解き『罪と罰』』の著者であるロシア文学者江川卓(1927〜2001年)氏の著書はどれもロシア文学、とりわけドストエフスキーをより深く学びたい人にとってはとても勉強になるものばかりです。今調べてみたところ、新潮選書のラインナップではまだ新刊として購入が可能なようですから、興味を持った方はぜひとも読んでみてください)。ドストエフスキーほどの大文豪ともなると、キャラクター名ひとつとっても徒や疎かにしていないというか、かくも深甚な、絶大な意図と思想を込めて決定されているということがわかるかと思います。
しかしながら、一方で「それは海外文学の話だろ? 日本語で書く小説に登場する日本人のキャラクター名をポリフォニックにしたら……野比のび太とか出来杉英才とか、そんな感じになっちゃうじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。確かにあまりに読み取りやすい多義性をキャラクター名に込めてしまうと、作風が固定化されてしまうというか、読者からすると物語の展開そのものも透けて見えてしまうような、そうしたデメリットも考えられます。仮に「私の名前は骨川痩夫(ほねかわやせお)。今日は意を決して駅前にあるトレーニングジムの門を敲くことにした。」みたいな書き出しの小説があったら、ちょっと読む気がしませんよね。もうキャラクターの名前でオチまで見えてしまう気すらします。
となると、ポリフォニックでありながら幾重にも日本語のヴェールを被せた固有名詞が望まれるのかもしれません。一例を挙げるなら、やはり三島由紀夫でしょうか。『鏡子の家』の鏡子は、戦後の一時代を映す鏡であり、交わらない個々人という現代を予言する鏡でもあり……とやりたいところですが、あいにくと私は専門家ではないため恥を晒す前にこのあたりでよしておきましょう。『金閣寺』の溝口や『潮騒』の新治や初江あたりも、いかにも作品のコンセプトを託された名前という感じがするのですが……興味がある方はぜひ論文や研究書を紐解いてみてください。あるいは、もう少し薄めのヴェールがご希望なら、ライトノベルなどの作品群にも参考になるものはありそうです。手元にある作品ですと、例えば『りゅうおうのおしごと!』(白鳥士郎、GA文庫)の主人公、九頭竜八一はいかにも将棋が強そうなキャラクター名ですよね。作中では「八月一日生まれだから八一」ということにされていますが、この名から将棋盤を連想しないわけにはいきませんし、姓もまた棋界最高位とされる竜王を想起させます。他には、西尾維新の作品に登場するキャラクター名などにも(私は西尾維新の作品をすべて読んだわけではないので断定的には語れないのですが)丁寧に吟味されたポリフォニックな意味性が付与されていそうです。
もちろん、上記の私の主張への反論もあるでしょう。「えー、九頭竜も戦場ヶ原も……なんかリアリティがないよ。そんな姓をキャラクター名に使ったら、途端にリアルな小説じゃなくなっちゃう」とする意見があれば、私は否定しません。ただし、だからといってリアルに寄せようとするあまり、ありそうな姓名を現実の存在から適当に借りてくるだけというのは、ダメです。なぜって……読者が作品を読み解く楽しみがひとつ、減ってしまうじゃないですか。後年の研究者から作品を分析する喜びを奪ってしまう危険性もあります。どのような姓名をキャラクターに冠するのも、作者の自由ではありますが、そこにコンセプトを持たせないと作品の厚みが目減りしてしまうと、私は考えています。
さて、長々書いてしまいましたが、もし仮に「もう、うるさいなあ。いろいろ言われたらかえって思いつかないよ!」と憤慨する方がいらっしゃったら……いっそのこと、キャラクター名をあえてつけない、というスタイルはどうでしょうか? 「名前のない主人公」は文芸表現においては一種のスタンダードでもあり、カフカの「K」しかり、安部公房の「S」しかり、夏目漱石の「吾輩」しかり……おっと、漱石なら『坊っちゃん』の「おれ」がいましたね。「主人公の匿名性」というテーマにおける文学史上の最大の成功例である「おれ」は、とりわけ近現代の日本文学に絶大な影響を及ぼしていると私は思います。谷川流の『涼宮ハルヒ』シリーズの主人公は作中でこそ「キョン」と呼ばれていますが、地の文では徹頭徹尾「俺」を貫いています。それは、未成熟な個人主義が延々と繰り返される日本の文化を象徴する一種のアイコンとして……いやはや、そろそろ紙面が尽きてきました。より詳細な話は、また別の機会にするとしましょう。ではまた。
文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事
-

文芸コース
2021年01月17日
【文芸コース】卒業生紹介「文芸のある風景」
通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸…
-

通信教育課程 入学課
2022年02月06日
【卒業生が語る!通信教育部の日々②】~芸術学科 芸術学コース・文芸コース・アートライティングコース編~
前回1月のオンライン入学説明会では本学通信教育部の学科・コースの卒業生たちに在学中の学習や思い出、体験談を語っていただきました。一部を抜粋してご紹介いたします。…
-

文芸コース
2021年08月18日
【文芸コース】必見!「レポートのお供」〜映像配信開始します!!
皆さん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。文芸コース教員の安藤です。 コロナ禍でしかも酷暑……。 文芸コース研究室では少しでも学習のお役にたてればと新企画…