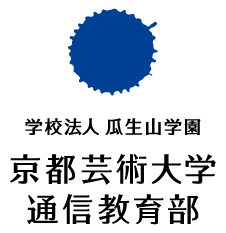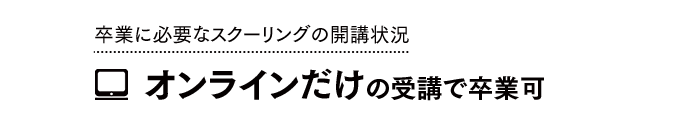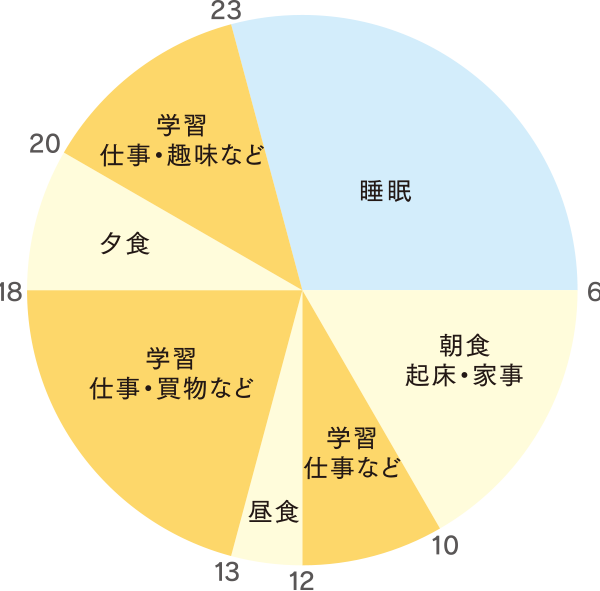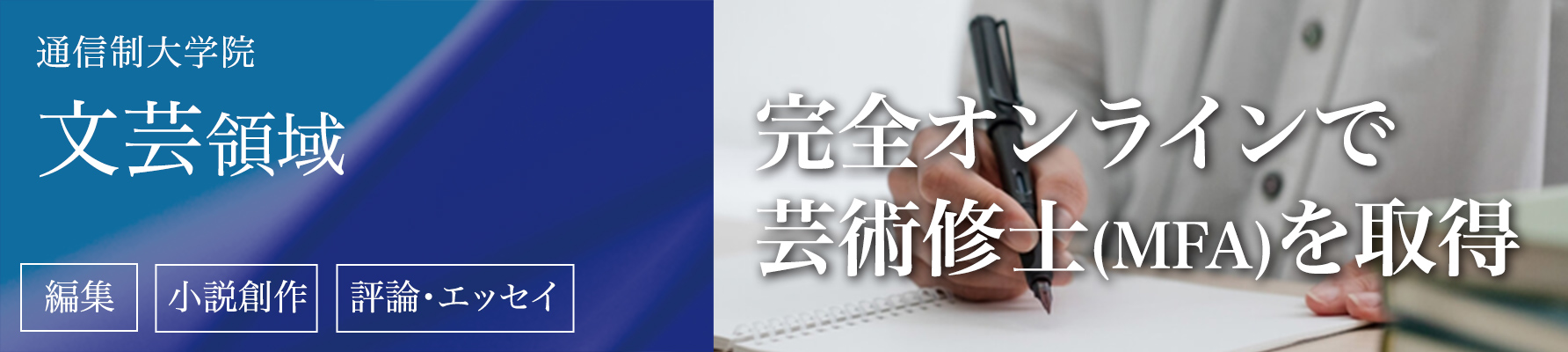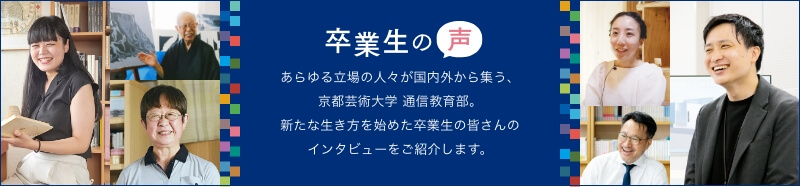私から生まれる物語
1年間の休学をはさみ、コース開設時から学んできた中村さん。もしかすると先生より、本コースで得るものを知っているかもしれない。40歳を前にして「定年を待つより、今の自分にしか書けないものを書いてみたい」と入学。テキスト科目で理論を学び、文章との向き合い方がまるで変わったという。「何より大きかったのは、文学を論じるための言葉を手に入れたこと」。たとえば《語り手》《視点》《ストーリーとプロット》など。小説を組み立てている要素を言葉で理解することで、単に〝面白い〞だけでなく、〝なぜ面白いのか〞を読み解けるようになった。中村さんいわく、それは「文芸を考えるための補助線、ツールのようなもの」。本を読むだけでなく、書いて思いを言葉にするときにも使えるという。「もちろんツールなので、どう使うかは本人次第ですが」。中村さんの場合は、卒業研究のテーマにまでつながった。
一方、スクーリングで得たのは、文章を書き、読んでもらう楽しさ。あるエッセイの授業で「彼女のブラジャーを洗う」話を発表したところ、予想以上の好反応。休学の後でも「あ、ブラジャーの人」と声をかけられ、心に残る文を書くよろこびを知った。「自分の中から物語が出てくる、という初めての感覚も課題で味わえました」。深く読み、書くたびに、知らない世界が開かれる。そこで得た思考は、現実世界にもつながっていく。「より柔軟にものごとを考えられ、生き方が豊かになったと感じます」。
やがて迎えた卒業研究では、《時間》をテーマに小説を創作。「テーマを課すことで、本来なら到達できなかった所まで、物語を運んでいけたと思います」。まずは自分の言葉で書き、読んでもらう。すべてはそこからはじまるから。その環境を与えてくれた本コースに感謝している、という中村さん。これからどう書き、どこまで届くかは分からないけれど、補助線の先にある、自らの物語を追いつづける。