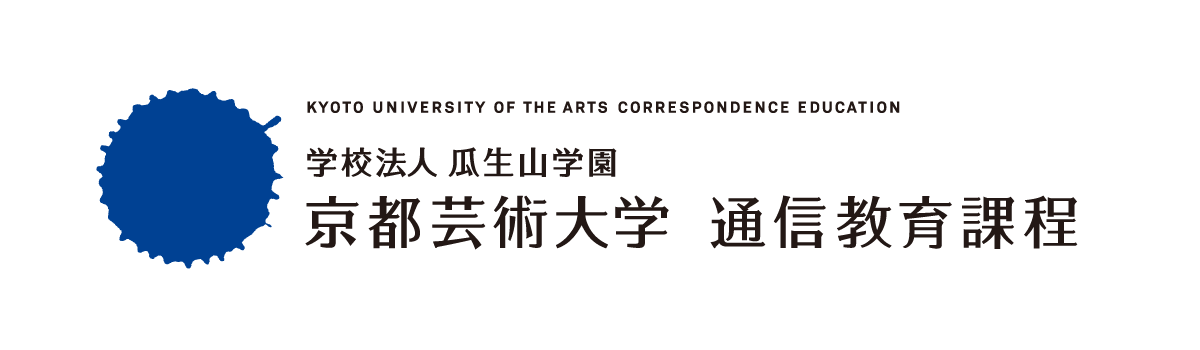アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「一体どうしたら「いい声」を聞くことができるのか。そこでたどり着いた僕らの仮説はまさに、自分たちが「聞く」ことによってそれは成せるのではないか、ということだった。」(濱口竜介『カメラの前で演じること』)
2022年07月22日
【アートライティングコース】「一体どうしたら「いい声」を聞くことができるのか。そこでたどり着いた僕らの仮説はまさに、自分たちが「聞く」ことによってそれは成せるのではないか、ということだった。」(濱口竜介『カメラの前で演じること』)
こんにちは。アートライティングコース非常勤教員の青木由美子です。
早いもので夏学期が始まってもう一カ月が過ぎようとしています。私がオブザーバーを務めているアートライティングコース専門教育科目の「アートライティング演習2(クリティカル・エッセイ)」にも、すでに多くの方々が履修をエントリーしています。それぞれどんな個性的なレポートを発表されるのか今からとても楽しみです。
私は13年前、あるNPOが主宰する「聞き書き」プロジェクトの立ち上げに協力し、準備作業のひとつとして高齢女性の語りを文章にまとめ、手作りの小冊子に仕上げています。そのことはすっかり忘れていたのですが、つい最近、事務局から再度協力の打診があり当時のことをにわかに思い出しました。この企画はシニア対象の会員制コミュニティが運営するもので、聞き書きの「書き手」を養成し、自分史を残したいと望む「語り手」とマッチングさせるという構想でした。この時点で想定した「書き手」は定年退職世代、「語り手」はその親世代、つまりかなりの高年齢になります。そのためプロジェクト準備チームは通常のインタビュー取材とは異なる「聞き方書き方」のルールを作りました。語り手に寄り添い耳を傾けること、語られる内容はそのまま受け入れること。事実誤認や記憶違いがあっても、その場で指摘しないと決めました。介護施設や病院で実施される「傾聴」のノウハウに倣ったのです。インタビュー取材を数多く経験してきた私ですが、こんなやり方は初めてで少し緊張しながら取り組んだと記憶しています。
今回はインタビューおける「聞き手」のふるまいについて考えてみました。
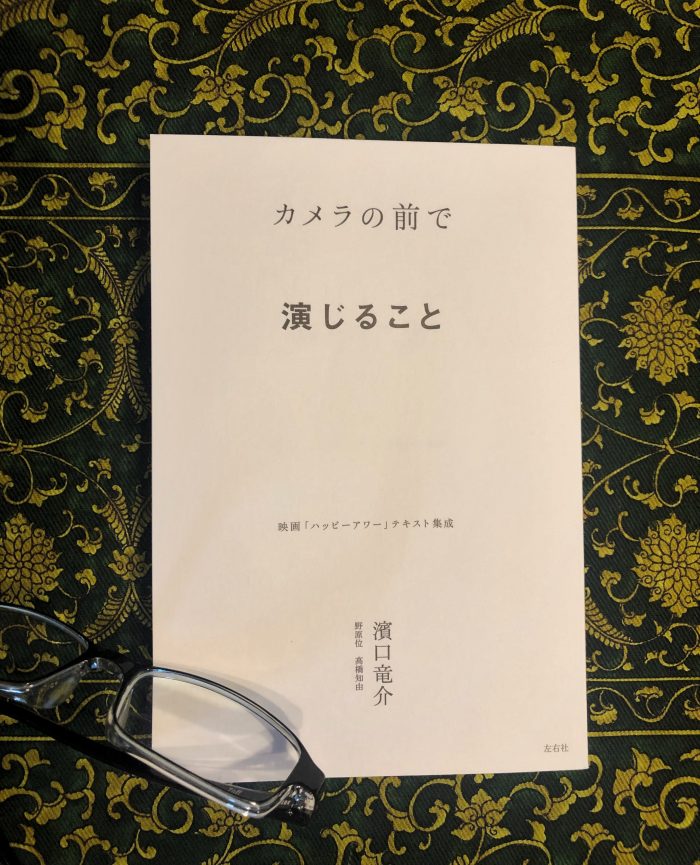
冒頭に挙げた言葉は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー国際長編映画賞を獲得した濱口竜介監督の著書『カメラの前で演じること』の中の一節です。この本は映画『ハッピーアワー』の制作ノートといえるものですが、引用したのは酒井耕と共同監督した東北記録映画三部作について述べている部分です。東北大震災で被災した人の語りを記録した『なみのおと』『なみのこえ』で濱口監督が採用したインタビュー形式は、夫婦・友人・親子・仕事仲間などもともと親密な間柄の二人に向かい合ってお互いの体験を語り合ってもらうというものでした。語り合うとはつまり聞き合うことでもあります。その結果、二人の監督には「いい声」が聞こえ始めたといいます。また、震災/日常を切り分けることなく同時に生きる「一個人」が立ち現れたと感じたとも。どちらも被災者にカメラを向けた時、めったにおきることではないそうです。ではより確実にこの状態をつくるには?
冒頭の言葉はこれに続きます。
──一体どうしたら「いい声」を聞くことができるのか。そこでたどり着いた僕らの仮説はまさに、自分たちが「聞く」ことによってそれは成せるのではないか、ということだった。──
──「被災体験に限らず、あなたの話すことなら何でも聞きたい」という態度は「いい声」の生まれる、つまりは人が率直に自分自身を表現することの基盤となる。──
東北での経験を通じて「聞くことの力」に確信を得た濱口監督は、それをフィクションの世界へ展開し、3分の2が演技経験のない受講生とともに5カ月にわたるワークショップをへて5時間超の映画『ハッピーアワー』に結実させました。ワークショップは一貫して「聞く力を伸ばす」プログラムだったそうです。
聞かれているという実感が、その人に自分自身を表現する力を与えるというのは実に大きな発見です。

聞きだす力、といえば琉球大学教授・上間陽子さんのそれは、畏敬の念を抱くほどです。本屋大賞ノンフィクション本大賞を獲得した「海をあげる」の中に収められている痛みを抱えて生きる沖縄の少女や少年のインタビューは、その内容の痛ましさとともに彼らから素直な言葉を引き出す上間さんの繊細かつ力強いコミュニケーションの取り方に圧倒されます。もちろん長年にわたり若年女性の調査・支援をしてきたからこそとは充分承知していますが、次のような言葉は皆さんが聞き手を担う時の参考になるかもしれません。
──生きていることが面倒くさい日々が私にあったことは、若い女の子の調査の仕事をしていると、どこかで役に立っている。──
──悲しみのようなものはたぶん、いきているかぎり消えない。それでもだいぶ小さな傷になって私になじみ、私はひとの言葉を聞くことを仕事にした。──
他者の痛みへの想像力──言うのは簡単ですが想像力は自分自身も傷つけます。インタビューの帰り道、ときどき泣いた、ときどき吐いた、と上間さんは著書のなかで明かしています。人と人が向き合うには覚悟が必要だと思いいたります。
さて、最初に紹介した13年前の聞き書き作品をあらためて読んでみました。語り手の高齢女性はその口ぶりから過去を回想するのを楽しんでいるのが伝わってきます。時代は日本が戦争につきすすむ昭和初期から戦中・戦後の復興期までですが、彼女が口にするのは映画、歌舞伎、宝塚で観た演目、看護師として働いていた病院近くで見る士官学校生の噂、食事に出かけるうれしさなど、華やかで明るい話題ばかりです。戦争体験記としては、あまり例がない奇妙にハッピーな内容でした。聞き書きをした当時、戦争の被害は人によってずいぶん濃淡があってほとんど何事もなくくぐりぬけることもあるのだ、と少し驚きつつも納得したことを思い出しました。個人史というのはそういうミニマムな歴史の一面を拾い上げることもあって興味深く感じました。さて、この時の私はよい聞き手だったのでしょうか。ありふれた苦労話に回収しようとしなかったことは、よしとしましょう。
アートライティングコース|学科・コース紹介

早いもので夏学期が始まってもう一カ月が過ぎようとしています。私がオブザーバーを務めているアートライティングコース専門教育科目の「アートライティング演習2(クリティカル・エッセイ)」にも、すでに多くの方々が履修をエントリーしています。それぞれどんな個性的なレポートを発表されるのか今からとても楽しみです。
私は13年前、あるNPOが主宰する「聞き書き」プロジェクトの立ち上げに協力し、準備作業のひとつとして高齢女性の語りを文章にまとめ、手作りの小冊子に仕上げています。そのことはすっかり忘れていたのですが、つい最近、事務局から再度協力の打診があり当時のことをにわかに思い出しました。この企画はシニア対象の会員制コミュニティが運営するもので、聞き書きの「書き手」を養成し、自分史を残したいと望む「語り手」とマッチングさせるという構想でした。この時点で想定した「書き手」は定年退職世代、「語り手」はその親世代、つまりかなりの高年齢になります。そのためプロジェクト準備チームは通常のインタビュー取材とは異なる「聞き方書き方」のルールを作りました。語り手に寄り添い耳を傾けること、語られる内容はそのまま受け入れること。事実誤認や記憶違いがあっても、その場で指摘しないと決めました。介護施設や病院で実施される「傾聴」のノウハウに倣ったのです。インタビュー取材を数多く経験してきた私ですが、こんなやり方は初めてで少し緊張しながら取り組んだと記憶しています。
今回はインタビューおける「聞き手」のふるまいについて考えてみました。
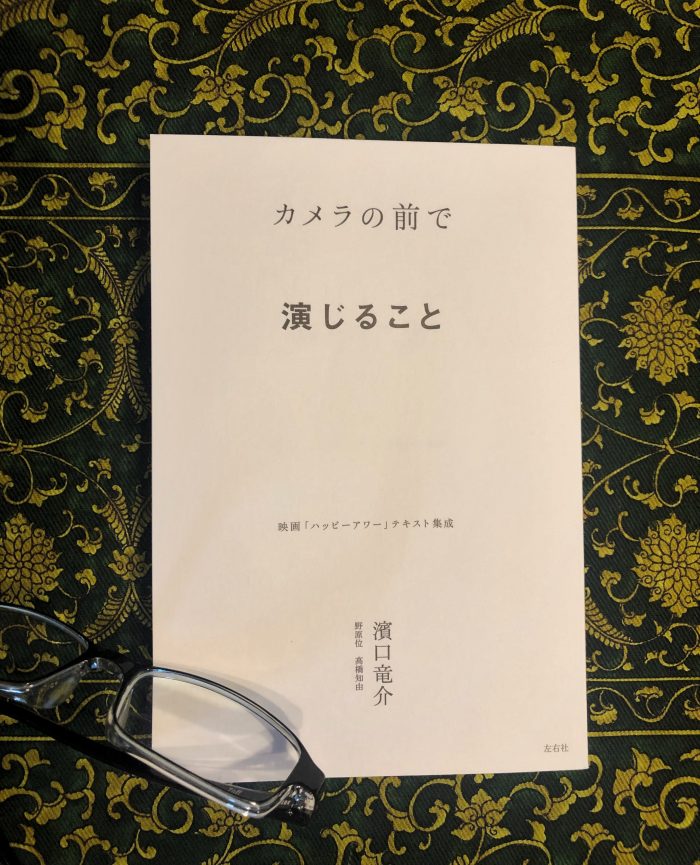
冒頭に挙げた言葉は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー国際長編映画賞を獲得した濱口竜介監督の著書『カメラの前で演じること』の中の一節です。この本は映画『ハッピーアワー』の制作ノートといえるものですが、引用したのは酒井耕と共同監督した東北記録映画三部作について述べている部分です。東北大震災で被災した人の語りを記録した『なみのおと』『なみのこえ』で濱口監督が採用したインタビュー形式は、夫婦・友人・親子・仕事仲間などもともと親密な間柄の二人に向かい合ってお互いの体験を語り合ってもらうというものでした。語り合うとはつまり聞き合うことでもあります。その結果、二人の監督には「いい声」が聞こえ始めたといいます。また、震災/日常を切り分けることなく同時に生きる「一個人」が立ち現れたと感じたとも。どちらも被災者にカメラを向けた時、めったにおきることではないそうです。ではより確実にこの状態をつくるには?
冒頭の言葉はこれに続きます。
──一体どうしたら「いい声」を聞くことができるのか。そこでたどり着いた僕らの仮説はまさに、自分たちが「聞く」ことによってそれは成せるのではないか、ということだった。──
──「被災体験に限らず、あなたの話すことなら何でも聞きたい」という態度は「いい声」の生まれる、つまりは人が率直に自分自身を表現することの基盤となる。──
東北での経験を通じて「聞くことの力」に確信を得た濱口監督は、それをフィクションの世界へ展開し、3分の2が演技経験のない受講生とともに5カ月にわたるワークショップをへて5時間超の映画『ハッピーアワー』に結実させました。ワークショップは一貫して「聞く力を伸ばす」プログラムだったそうです。
聞かれているという実感が、その人に自分自身を表現する力を与えるというのは実に大きな発見です。

聞きだす力、といえば琉球大学教授・上間陽子さんのそれは、畏敬の念を抱くほどです。本屋大賞ノンフィクション本大賞を獲得した「海をあげる」の中に収められている痛みを抱えて生きる沖縄の少女や少年のインタビューは、その内容の痛ましさとともに彼らから素直な言葉を引き出す上間さんの繊細かつ力強いコミュニケーションの取り方に圧倒されます。もちろん長年にわたり若年女性の調査・支援をしてきたからこそとは充分承知していますが、次のような言葉は皆さんが聞き手を担う時の参考になるかもしれません。
──生きていることが面倒くさい日々が私にあったことは、若い女の子の調査の仕事をしていると、どこかで役に立っている。──
──悲しみのようなものはたぶん、いきているかぎり消えない。それでもだいぶ小さな傷になって私になじみ、私はひとの言葉を聞くことを仕事にした。──
他者の痛みへの想像力──言うのは簡単ですが想像力は自分自身も傷つけます。インタビューの帰り道、ときどき泣いた、ときどき吐いた、と上間さんは著書のなかで明かしています。人と人が向き合うには覚悟が必要だと思いいたります。
さて、最初に紹介した13年前の聞き書き作品をあらためて読んでみました。語り手の高齢女性はその口ぶりから過去を回想するのを楽しんでいるのが伝わってきます。時代は日本が戦争につきすすむ昭和初期から戦中・戦後の復興期までですが、彼女が口にするのは映画、歌舞伎、宝塚で観た演目、看護師として働いていた病院近くで見る士官学校生の噂、食事に出かけるうれしさなど、華やかで明るい話題ばかりです。戦争体験記としては、あまり例がない奇妙にハッピーな内容でした。聞き書きをした当時、戦争の被害は人によってずいぶん濃淡があってほとんど何事もなくくぐりぬけることもあるのだ、と少し驚きつつも納得したことを思い出しました。個人史というのはそういうミニマムな歴史の一面を拾い上げることもあって興味深く感じました。さて、この時の私はよい聞き手だったのでしょうか。ありふれた苦労話に回収しようとしなかったことは、よしとしましょう。
アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

アートライティングコース
2022年05月23日
【アートライティングコース】「書く技術とは、自分の両腕を差し伸ばす技術にほかなりません。」D. ディドロ(日付不詳の手紙 1769年頃)
みなさま、こんにちは。アートライティングコースの教員、上村です。 この春、アートライティングコースは開設から4年目を迎え、今年も大勢の新しい学生のみなさんを迎え…
-

通信教育課程 入学課
2022年02月06日
【卒業生が語る!通信教育部の日々②】~芸術学科 芸術学コース・文芸コース・アートライティングコース編~
前回1月のオンライン入学説明会では本学通信教育部の学科・コースの卒業生たちに在学中の学習や思い出、体験談を語っていただきました。一部を抜粋してご紹介いたします。…
-

通信教育課程 入学課
2022年12月15日
コースの垣根を越えて広く芸術全般を学べる!共通科目のご紹介
本学に興味をもっている方のなかで、「大学で学ぶ」こと自体や「通信教育で学ぶ」こと、どちらもはじめて。という方はとても多いと思いますので、まずは本学のカリキュラム…