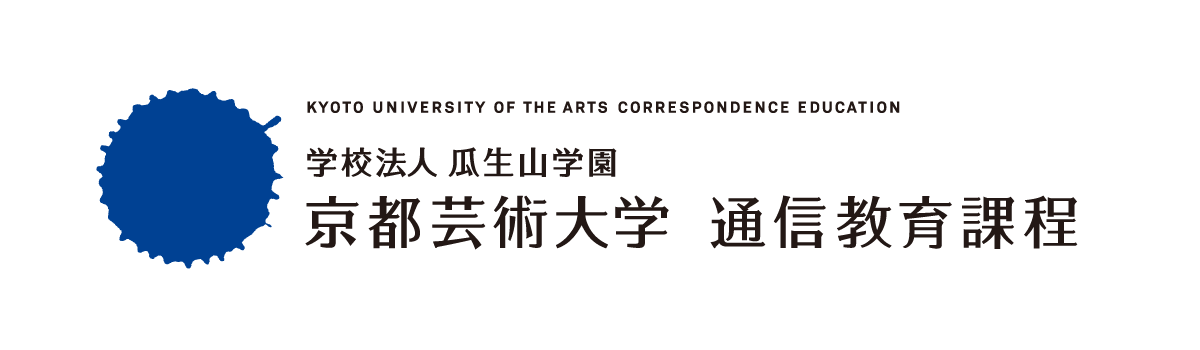通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】芸術にとって研究とは何か(文芸評論家・池田雄一)―文芸領域リレーエッセイ⑤
2022年11月30日
【通信制大学院】芸術にとって研究とは何か(文芸評論家・池田雄一)―文芸領域リレーエッセイ⑤

2023年度に新設する文芸領域への入学を検討する「作家志望者」「制作志望者」へのエールとして、作家、編集者、評論家の方がリレーエッセイとしてお届けします。
今回は文芸領域の教員で文芸評論家の池田雄一さんのエッセイをご紹介します。

池田 雄一(いけだ・ゆういち)
1969年、栃木県鹿沼市生まれ。1994年に「原形式に抗して」により、第37回『群像』新人文学賞の評論部門を受賞。文芸評論家として、批評、書評、文芸時評などを執筆。
著書に『カントの哲学ーシニシズムに抗して』(河出書房新社)、『メガクリティック―ジャンルの闘争としての文学』(文藝春秋)がある。また共著に『思想としての3.11』(河出書房新社)、『戦後思想の再審判―丸山眞男から柄谷行人まで』(法律文化社)などがある。
これまでに早稲田大学、東京工業大学、東京大学などで非常勤講師をつとめる。また2013年から2017年にかけて東北芸術工科大学にて准教授をつとめる。現在は、法政大学、武蔵野大学、京都芸術大学で非常勤講師を、朝日カルチャーセンター新宿教室にてオンライン講座の講師をつとめている。専門領域は現代文学、美学、哲学、政治思想など。
芸術にとって研究とは何か
芸術における「研究」が創作活動そのものだとしよう。だとすると、その活動は、自然科学や歴史学、経済学などのような一般的な学問分野における研究と、いったいどのような違いがあるのだろうか。
いまあげた学問のなかで、とくに文芸に隣接していると思われる歴史学について考えてみよう。この学問分野において前提とされているのは、ひとえに「事実」である。歴史というのは、この事実の連鎖であり、事実でない出来事は歴史には組み込めないし、組み込んではならない。歴史をめぐる問いは、この事実の判定をめぐって展開されることになる。
おなじく自然科学や、経済学、人類学などの学問もまた、この「何が事実であるのか」という問いを前提として運営されている。この問いを外して論文などを書き始めてしまうと、とたんにそれは宗教的な教義、陰謀論、偽史、あるいは「小説」のようなものへと変身してしまうだろう。
このように一般に学問というのは「事実」というファクターを前提として成立している。考えてみれば当たり前のことである。ところが、創作活動においては、前提となっているものがこれらの学問とまったく違うのである。芸術においては、何が事実であるのかは二次的な問題、もしくは積極的に排除される問題である。フランシス・ベーコンの絵画に描かれている怪物をみて、そんな生物は存在しないと文句を言う人間がいるだろうか。萩原朔太郎の「死なない蛸」を読んで「自分のカラダを食べ尽くして消える蛸などいるわけがない」などと怒りだす人間がいるだろうか。そもそも創作活動とは、事実の認定とは関係のない、特殊な知的活動なのである。
じつは同じことが大学のいわゆる「文学部」においても言うことができる。文学部において主な研究対象となるのは、個々の「作品」である。あらためて確認するまでもないが、それらの作品は芸術作品である。あつかう対象が芸術作品である以上、先ほど述べたような前提のシフトがおこるはずである。おこるはずなのに、どういうわけかおこらなかったので、文学部でもまた「事実の認定」を前提として研究領域を組み立ててしまい、あげくのはてに作家の伝記のような記述に終止してしまい、野心的な学生が落胆する、ということが起きたりするのである――もっともロラン・バルトによる「作者の死」宣言をうけとめた世代はその限りではないかもしれないが。
いずれにしても芸術における研究、すなわち創作においては、前提とされているものがちがう。研究としての創作活動が、事実の認定にこだわってしまうと、おそらく活動そのものがストップしてしまうだろう。それはそうである。しかしそれなら芸術における創作、あるいは芸術そのものの研究が前提とすべきファクターというのは、いったい何なのか。
ここで現象学という学問を召喚しよう。現象学とは、フッサールという、二〇世紀前半に活躍したドイツの哲学者によって開始された、哲学のサブジャンルである。
現象学がやろうとしたこと、それを一言でいうならば「ひとの意識とは切り離されたものとして、この世界は揺るぎなく存在する」といった素朴な世界観を保留することによって、この世界と意識の相関関係を見定める、というものである。
たとえば目の前にサイコロがあるとしよう。いちどに見ることができるのは、せいぜい三面だとしよう。それぞれの面には「五」と「四」と「六」の目がでている。現象学による保留をへたあとでは、この「三面のサイコロ」という「現象」が、観察者にあたえられたサイコロの全てである。このように限定された「現象」から、いかにして物体としてのサイコロが構成されていくのかを、現象学は記述していくのである。
現象学の専門用語を使うのは面倒なので、現象学によって記述されるものを、ここでは「意識のメカニズム」と呼ぶことにしよう。そして芸術において前提とされてるものは、この意識のメカニズムなのである。
こうした現象学の方法によって、はじめて成立する研究や概念は、思いのほか多い。たとえば社会学における「理念型」という概念がそうである。あるいはマクルーハンによるメディア論なども、暗黙のうちに現象学を導入していると言える。そしてフッサール自身が取り組んだものとして知られているのは「時間論」である。
フッサールは、過去、現在、未来を個別のものとして考えていない。フッサールによれば、「今」という時間には過去と未来が同居しているのである。
何やらあやしげな理論のようにみえるが、たとえば何らかのメロディラインのある音楽を聞いている際に、どのように意識が動いているのかを確認してみると、このことは容易に理解できる。ひとがひとつのメロディラインを認識できるのは、それまでに聞いた音を記憶し、なおかつこれから来るであろう音を予測するからである。そしてこの「予測」を助けるために、メロディラインは「反復」される必要があるのである。
おなじことが「音読」の現象学についてもいえる。
音読する側が棒読みにならずに、あたかも本人が誰かに演説するかのように読むためには、じっさいに読み上げている箇所よりも、かなり先の部分まで目を通して、なおかつ理解している必要がある。うまく音読するためには、ここでも過去、現在、未来を同居させる必要があるのだ。
おなじく詩や小説においても、それ固有の時間が流れている。作品を書くときも、作品を読むときも、それぞれ固有の時間が流れているのである。ここで具体的な作品にそくして、そのメカニズムを確認したいのだが、そうなるともはや、このエッセイの範囲をこえてしまう。
それについては、そのうちどこかの授業でやりたいと考えている。
■文献リスト■
谷徹『これが現象学だ』講談社現代新書,2002年.
創作をはじめるのに、フッサールの著作を読む必要はないが、現象学の発想を知っておくと何かと便利である。その点この本は、現象学をざっくりと学ぶのに適している。各所にはさまれているコラムも創作のヒントになる。
斉藤慶典『フッサール起源への哲学』講談社選書メチエ,2002年.
入門書よりふみこんだ考察が展開されている。フッサールの書いたことをオウム返しに述べるのではなく、筆者なりに消化したフッサール理解を得ることができる。後に紹介するデリダによる現象学批判より後の世代が書いた概説書と言える。
フッサール『イデーンⅠ−Ⅰ』渡辺二郎訳、みすず書房,1979年.
フッサールといえばこの本である。晦渋としか言いようのない書きぶりであるが、たまに妙に具体的な例があげられていて、そこだけ読むと小説のようである。前掲の二冊と併読すれば、なんとか理解できるはず。
サルトル『嘔吐』鈴木道彦訳、人文書院,2010年.
グロテスクに描かれたマロニエの樹の描写で知られる小説。この描写が現象学の影響を受けているのも有名な話である。
デリダ『声と現象』林好男訳、ちくま学芸文庫,2005年.
フッサールの考える「今」というのは、それほど純粋なものではなく、すでに文字のような痕跡によって汚染されている、という観点からの批判が展開されている。こうした批判を読むと、逆に現象学が理解できるようになるというのが不思議である。
イーザー『解釈の射程―〈空白〉のダイナミクス』伊藤誓訳、法政大学出版局,2006年.
イーザーは「受容美学」もしくは「受容理論」を唱えたことで知られている。受容理論とは、文学作品は読者に読まれ解釈されることによって、はじめて完成する、という観点から作品と読者の相互作用を解析するという理論である。この説明からわかるとおり、この受容理論は、もろに現象学の影響を受けている。ただしこの本は非常に読みづらい。
——————————————————
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ

▼国内唯一、完全オンラインで芸術修士(MFA)が取得できる京都芸術大学通信制大学院webサイト

【通信制大学院】小説を書く理由とは?―文芸領域イベントレポート