

和の伝統文化コース
- 和の伝統文化コース 記事一覧
- 【和の伝統文化コース】「飴屋踊り」のご紹介
2024年07月21日
【和の伝統文化コース】「飴屋踊り」のご紹介
こんにちは。
和の伝統文化コースの三津山智香です。
梅雨らしいじめじめとした日が続いておりますが、お変わりありませんか。
あっという間に一年の半分が終わり、もう7月。これから暑い夏が始まりますが、暑さをふきとばすくらい熱いお祭りが、日本各地で開催されます。
お祭りのかたちは地域によって様々ですが、お神輿を担ぐ勇壮な姿、華やかな山車、踊りだしたくなるようなお囃子……とても賑やかな景色を想像される方が少なくないのではないでしょうか。そんなお祭りを盛り上げる存在のひとつに、民俗芸能があります。
民俗芸能とは、地域の人々が担い手となって演じる歌や舞、踊、演劇といった芸能を指します。地域の人々が担い手になっていることから、地域の風土や信仰といったものがあらわれる、という特徴があります。かつては地域の祭礼や行事の中で披露されることが主でしたが、近年は、「民俗芸能大会」、「郷土芸能大会」などの名称で、複数の地域の芸能が一堂に会する機会も多くなっています。
そんな民俗芸能のなかで、今回は私が調査を行っている「長井町飴屋踊り」を紹介します。
飴屋踊りは、神奈川県や千葉県、埼玉県、東京都、茨城県といった地域に分布する芸能です。呼称は地域によって異なり、「万作踊り」、「中山節」などと呼ぶ地域もあります。飴屋踊りは神奈川県で多く用いられる名称です。飴屋さんが太鼓を叩いて歌って踊りながら飴を売っていた様子を取り入れた芸能であることから「飴屋踊り」と名づけられたと考えられています1)。
長井町飴屋踊は、長井町飴屋踊り保存会によって神奈川県横須賀市長井町で継承されています。昭和49年(1974年)6月1日に横須賀市指定重要無形文化財に指定されました。

写真のように、舞台ではばっちり白塗りのお化粧をし、華やかな衣装で踊ります。
踊り手は主に小学生から高校生の子どもたちで、週に一度、練習に励んでいます。現在は男女関係なく踊りに参加し、和気あいあいとした様子で練習を行っていますが、かつては男の子が踊るもので、練習もとても厳しかったそうです。
踊りには、ねんねこ、三番叟、新川、白枡粉屋など複数の種類があります。踊りによって、衣装や化粧が変わります。また、それぞれの踊りには唄がつき、鉦とツケ2)とでリズムをとります。
いくつか、踊りの様子を紹介しましょう。

これは、ねんねこの様子です。子守の女性をイメージしており、踊り手は子供の代わりに人形を背負っています。「こねだもよぅ 権現(ごんげん)様(さま)のお祭りで村の若い衆と話をしてたらよぅ この子が泣いてばっかりいて ちっとも話をさせなかったのよ」3)のような、観客をくすっとさせる歌詞が魅力です。

これは、三番叟です。
「このやお村は めでたいお村で 浜は大漁 丘、満作」4)のように、喜ばしい出来事を歌詞に並べたり、「寿」の文字を書くように頭を動かす所作があったりと、とてもめでたい舞です。
長井町飴屋踊りは、神奈川県民俗芸能保存協会の主催する「かながわ民俗芸能祭」に出演したり、横須賀市内の総合公園「ソレイユの丘」で演舞したりと、精力的に活動しています。
現在は7月14日(日)に横須賀市長井の熊野神社で行われるお祭りでの披露に向けて、練習に励んでいます。
興味を持たれた方。ぜひ、飴屋踊りを観に行ってください!


ところで、神奈川県内には、長井町飴屋踊り以外にも、川崎市や三浦市などに飴屋踊りがみられます。同じ名称の踊りもありますが、歌詞やリズム、衣装が異なります。複数の地域の踊りを見比べて違いを知ることも、飴屋踊り、そして、民俗芸能の楽しみ方のひとつです。一方で、少子高齢化等による担い手不足といった民俗芸能を取り巻く課題も存在します。精力的に活動する長井町飴屋踊りも、後継者不足には頭を悩ませています。
地域の人々によって脈々と受け継がれてきた民俗芸能とはどのようなものか?次の世代にどのようにつないでいくのか?そんな民俗芸能の“歴史”や“今”を探究してみませんか。
註
1)石川博之 1999「飴屋踊り」 福田アジオほか編『日本民俗大辞典 上』吉川弘文館
2)2本の木を板に打ちつけて音を出すものを指します。
3)長井町飴屋踊り保存会からの提供資料より
4)長井町飴屋踊り保存会からの提供資料より
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

和の伝統文化コースの三津山智香です。
梅雨らしいじめじめとした日が続いておりますが、お変わりありませんか。
あっという間に一年の半分が終わり、もう7月。これから暑い夏が始まりますが、暑さをふきとばすくらい熱いお祭りが、日本各地で開催されます。
お祭りのかたちは地域によって様々ですが、お神輿を担ぐ勇壮な姿、華やかな山車、踊りだしたくなるようなお囃子……とても賑やかな景色を想像される方が少なくないのではないでしょうか。そんなお祭りを盛り上げる存在のひとつに、民俗芸能があります。
民俗芸能とは、地域の人々が担い手となって演じる歌や舞、踊、演劇といった芸能を指します。地域の人々が担い手になっていることから、地域の風土や信仰といったものがあらわれる、という特徴があります。かつては地域の祭礼や行事の中で披露されることが主でしたが、近年は、「民俗芸能大会」、「郷土芸能大会」などの名称で、複数の地域の芸能が一堂に会する機会も多くなっています。
そんな民俗芸能のなかで、今回は私が調査を行っている「長井町飴屋踊り」を紹介します。
飴屋踊りは、神奈川県や千葉県、埼玉県、東京都、茨城県といった地域に分布する芸能です。呼称は地域によって異なり、「万作踊り」、「中山節」などと呼ぶ地域もあります。飴屋踊りは神奈川県で多く用いられる名称です。飴屋さんが太鼓を叩いて歌って踊りながら飴を売っていた様子を取り入れた芸能であることから「飴屋踊り」と名づけられたと考えられています1)。
長井町飴屋踊は、長井町飴屋踊り保存会によって神奈川県横須賀市長井町で継承されています。昭和49年(1974年)6月1日に横須賀市指定重要無形文化財に指定されました。

(2023年12月3日三津山撮影)
写真のように、舞台ではばっちり白塗りのお化粧をし、華やかな衣装で踊ります。
踊り手は主に小学生から高校生の子どもたちで、週に一度、練習に励んでいます。現在は男女関係なく踊りに参加し、和気あいあいとした様子で練習を行っていますが、かつては男の子が踊るもので、練習もとても厳しかったそうです。
踊りには、ねんねこ、三番叟、新川、白枡粉屋など複数の種類があります。踊りによって、衣装や化粧が変わります。また、それぞれの踊りには唄がつき、鉦とツケ2)とでリズムをとります。
いくつか、踊りの様子を紹介しましょう。

(2023年4月5日三津山撮影)
これは、ねんねこの様子です。子守の女性をイメージしており、踊り手は子供の代わりに人形を背負っています。「こねだもよぅ 権現(ごんげん)様(さま)のお祭りで村の若い衆と話をしてたらよぅ この子が泣いてばっかりいて ちっとも話をさせなかったのよ」3)のような、観客をくすっとさせる歌詞が魅力です。

(2023年4月5日三津山撮影)
これは、三番叟です。
「このやお村は めでたいお村で 浜は大漁 丘、満作」4)のように、喜ばしい出来事を歌詞に並べたり、「寿」の文字を書くように頭を動かす所作があったりと、とてもめでたい舞です。
長井町飴屋踊りは、神奈川県民俗芸能保存協会の主催する「かながわ民俗芸能祭」に出演したり、横須賀市内の総合公園「ソレイユの丘」で演舞したりと、精力的に活動しています。
現在は7月14日(日)に横須賀市長井の熊野神社で行われるお祭りでの披露に向けて、練習に励んでいます。
興味を持たれた方。ぜひ、飴屋踊りを観に行ってください!

(2024年1月28日三津山撮影)

(2024年1月28日三津山撮影)
ところで、神奈川県内には、長井町飴屋踊り以外にも、川崎市や三浦市などに飴屋踊りがみられます。同じ名称の踊りもありますが、歌詞やリズム、衣装が異なります。複数の地域の踊りを見比べて違いを知ることも、飴屋踊り、そして、民俗芸能の楽しみ方のひとつです。一方で、少子高齢化等による担い手不足といった民俗芸能を取り巻く課題も存在します。精力的に活動する長井町飴屋踊りも、後継者不足には頭を悩ませています。
地域の人々によって脈々と受け継がれてきた民俗芸能とはどのようなものか?次の世代にどのようにつないでいくのか?そんな民俗芸能の“歴史”や“今”を探究してみませんか。
註
1)石川博之 1999「飴屋踊り」 福田アジオほか編『日本民俗大辞典 上』吉川弘文館
2)2本の木を板に打ちつけて音を出すものを指します。
3)長井町飴屋踊り保存会からの提供資料より
4)長井町飴屋踊り保存会からの提供資料より
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

和の伝統文化コース
2023年12月21日
【和の伝統文化コース】「伝統文化実践II-4(茶の文化)」のご紹介
こんにちは。コース主任の野村です。 今回は和の伝統文化コースの授業の様子をお届けしたいと思います。 授業をご担当下さった中村幸先生からのレポートです。 11月4…
-
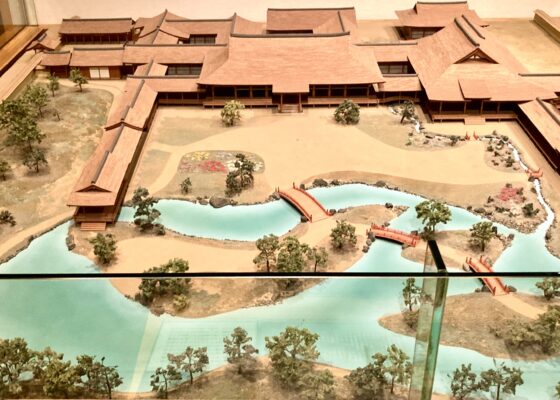
和の伝統文化コース
2024年04月09日
【和の伝統文化コース】大河ドラマ「光る君へ」でわかる平安時代の建物
みなさま、こんにちは。和の伝統文化コース非常勤講師の叉東(さとう)愛です。 今年の大河ドラマ「光る君へ」の舞台は、平安時代ですね。 江戸時代や戦国時代に比べ、平…
-

和の伝統文化コース
2024年06月03日
【和の伝統文化】「利休忌月次(つきなみ)法要 於 大徳寺聚光院」
みなさま、こんにちは。和の伝統文化コース非常勤講師の青木です。 春から夏への変わり目、皆さまいかがお過ごしでしょうか? 今回は茶の湯文化にゆかりの深い大徳寺(注…






























